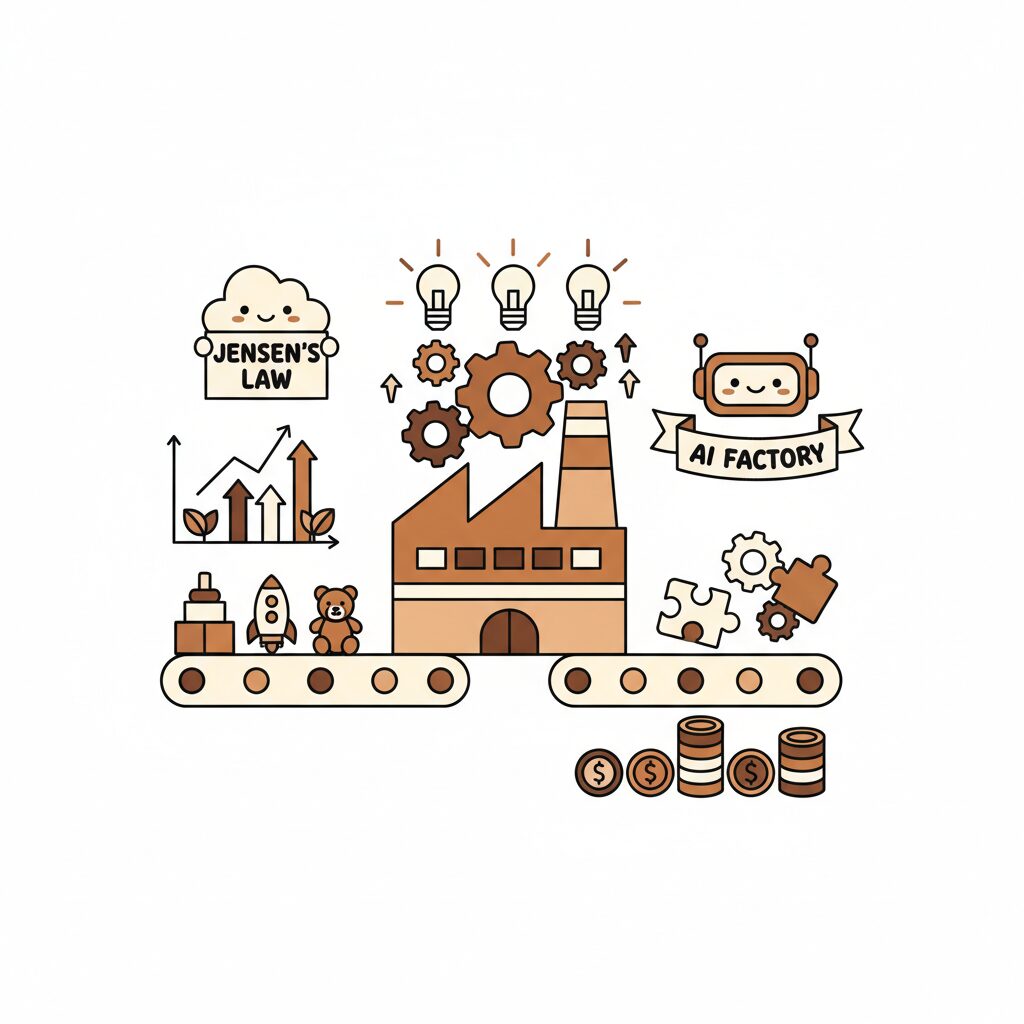
ジェンセンの法則って聞いたことありますか?NVIDIAのジェンセンさんが提唱した「AIファクトリー経済学」って知ってますか?なんだか難しそうに聞こえるかもしれませんが、実は子育てにすごく役立つ考え方なんです!
AIファクトリーって何?家庭でわかりやすく説明すると
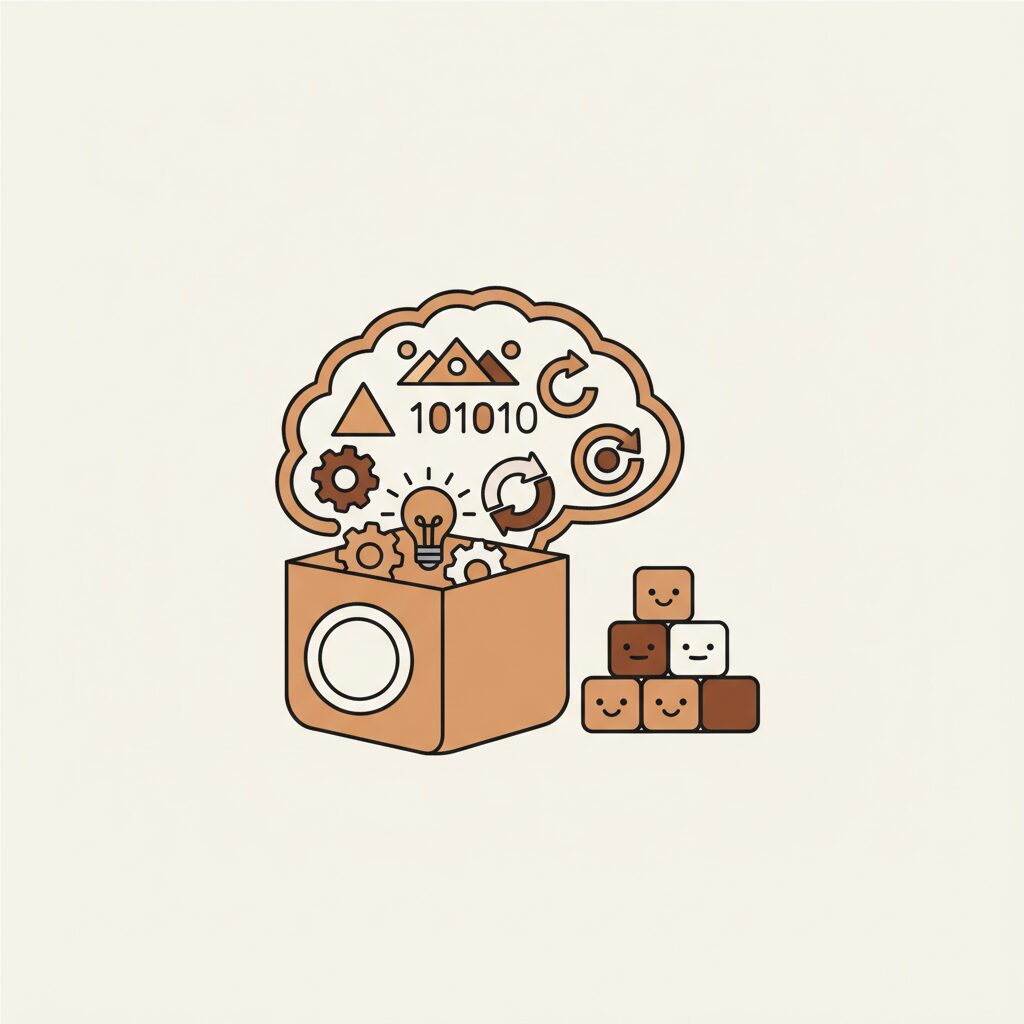
AIファクトリーって、要はデータを保存する倉庫じゃなくて、知性を作り出す工場みたいなもの。うちの娘が「パパの頭の中もAIファクトリー?」って聞いてきたときは笑っちゃいましたけどね!
韓国のことわざに「三日坊主」という言葉がありますが、新しい知的好奇心も同じで、最初の熱情をどう持続させるかが大切です。効率的に収納したおもちゃ箱みたいに、よく使う好奇心ほど手の届くところに置いてあげたいですよね。
「もっと買えば、もっと作れる」は子育てにどう活きる?
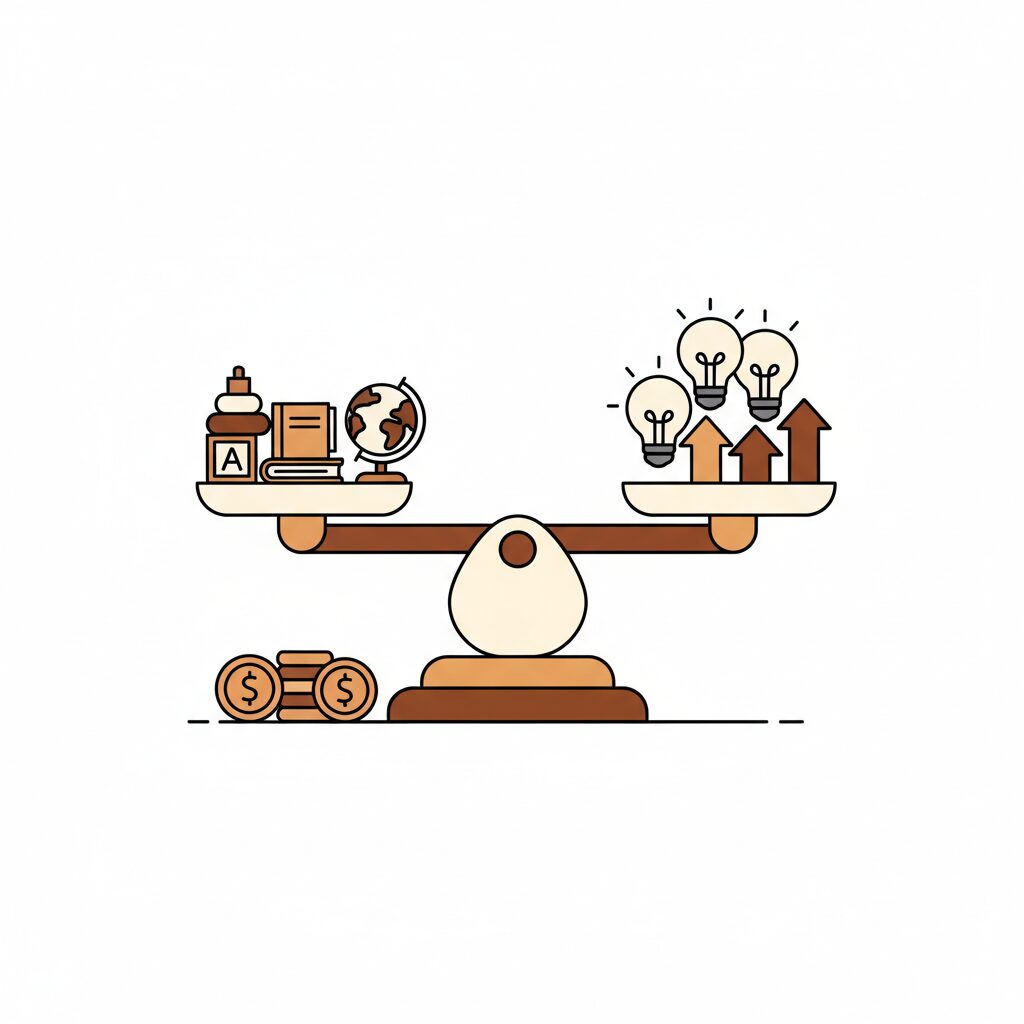
AIファクトリー経済学って聞くと難しそうでしょ?でも大事なのは、どうやって「活用するか」ってことなんだ!例えば先週、娘が「ブロックで大きな城を作りたい」と言い出したとき、新しいブロックを買う代わりに、既にある部品でどう組み立てるかを一緒に考えました。
これってまさに、ジェンセンの法則で言う「投資(買う)」じゃなくって「生産性(創る)」ですよね。研究でも証明されているように、子どもの興味を引き出す(効率性)と、それを活かす(活用率)のバランスが、学びの鍵なんです。
AI時代に必要な力って何だろう?

うちの娘は時々「パパ、これってAIができるの?」と聞いてくるんです。そういう瞬間が、技術と人間の感性の境界線を感じさせます。例えば折り紙で新しい形を作るとき、AIは指示通りに折れても、その「ワクワク感」まじゃ作れないですよね?
子どもたちに必要なのは、自分の資源(時間・能力・好奇心)をどう「楽しく」活用するか、という感覚。公園で落ち葉を見つけて「これは何の形?」と想像するクセこそ、将来AIと働く時に役立つ創造性なんです。
家庭で始めるAIリテラシー教育

難しい話は抜きにして、今日からできることありますよ!例えば夕飯の支度を「どうしたら早くできるか」ゲームにしたり、おもちゃの数を半分にして「どう遊び方を変えるか」考えたり。これらは全てAIファクトリーの原則「効率性×活用率」の練習になるんです。
先日、娘と片付け中に発見したんです。「このおもちゃ、1年使ってなかったね」って。使わない資源は価値を生まない――まさにAIファクトリー経済学が教える真理を、親子で実感した瞬間でした。
未来を見据えた子育てのヒント

曇り空の日だって、傘の代わりに踊りだすとかえって楽しいですよね。ジェンセンの法則が教えてくれるのは、資源の量より「どう輝かせるか」が大事だということ。
もし我が家が小さな「AIファクトリー」だとしたら、どんな知性を製造したいですか?技術じゃなくて、困っている人にそっと寄り添える心とか、新しい遊びを発明するワクワク感とか――それが人間らしさの工場かもしれませんね。
出典: Reframing Jensen’s Law: ‘Buy more, make more’ and AI factory economics, Silicon Angle, 2025/08/30
