
光はただ明るくするだけじゃない。朝の優しい光で目覚め、夕方の温かい灯りで家族団らん…そんな日常に、AI照明のような技術が新たな彩りを加える時代が来ました。とはいえ、最先端技術とどう向き合うべきか?例えば我が家ではこう試してみました:
⋆ 朝は「朝日モドキ」でスッキリ!お気に入りのBGM再生と同時スタート
⋆ 夕食時は「温かい家族時間」モードで、会話が弾んでるんです!
さて、具体的に何が変わるのか一緒に見ていきましょう?
AI照明が作る、家族のちょっと特別な日常

ベルリンのIFAイベントで見た未来の照明、思いっきりワクワクしませんでしたか?レプロの新ラインナップは音声認識で光の色と明るさを変えられるんです。これって子どもの創造性を引き出す意外な方法になりそう!天井の星のシールを見ながら「今日は宇宙王女様モード!」って娘がさっき言ってた遊び心が、やんわり形になるんじゃないかな。
例えばイマジネーションの遊び:
<使うシーン> スカートルームでキャンドルナイト実践中(←←ロウソク2本だけのミニ版)。子どもが「ここはちょっと暗すぎる?」って聞いたら、見えないゲームをしてみたり。
<結果> 光の濃淡が遊びそのものになったんですよ。声で「パッと明るく」→一瞬で空間がパッと変わり、「ママとやれたらええな」的な会話が自然に🌟
光と色の「魔法」で育む心とからだ
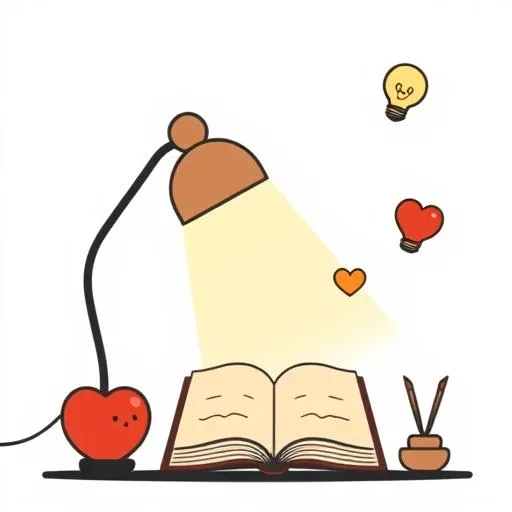
いやあ、調べてみると面白いデータがありますよねぇ!光の色で子どもの気分が変わるって、なんかシアワセの秘密みたいなワクワクさも。「ナチュラルなリラックス」モードの赤みの光、我が家でも試してみたら、娘が抱っこを急に求めてきたりして✨٩(๑>◡<๑)۶
こんな工夫で感情サポート:
• 調子を崩した時にアクアブルー系でクールダウン←←想像力を巡らす会話が繋がる
• 宿題のときは蛍光灯の白さをソフトに調整→自然と集中スイッチが入るんですって!
<パパあるある>風邪の時に「病院みたいに光りたくない」と娘に訴えられました(笑)
便利さと、大切な人の絆とのバランスをどう取る?

技術の進化って本当に楽しいんですけど、ついつい使いすぎないか不安になるのもパパ目線で😅先週は中学生の姪っ子が「音声コントロールやり過ぎると、うるさく感じることもあるかも」って言ってきたんです。若い子たちも本当に色んなアイディアを持ってて…リレーで考えさせられた夜でした✨
例えばこんな問いかけ:
「今の光の色は家族で話そう」って感じじゃないかな?
<気づきのメモ> despuésは「色を選ぶ前の会話」がヲツカシイということを娘が教えてくれた日があるので、そこも大切に(続く)
スマホとの絶妙のつき合い方:近代的”家庭の光”ガイド

我が家流子ども向け光セッティング(←気分変換にもなる)
• 原色系でレゴ遊び ←←動きと色合わせで新世界へ(๑>ڡ<)☆
• 落ち着きモードが夕食中に安定←同じオレンジ色を使ってますけど、nyanと朝は違いますね。
【スモールスタートのコツ】
① 固定の朝・夜モードを作る→タイマー機能に任せると子どもが自分で線維をつける習慣もplus!(お片付け支援が入りそうならYa-Y!)
② 星探しモードで親子クイズ ←「この光ってどこの星座 resembles🐶?」って色んな話が広がるטו
アナログな温かさとデジタルの美しさ:しかし大事なのは?
娘は今5歳半、絵本の時間に「お絵描きの後に本読もう」と手を和紙ランプに当てて光る様子を見ていました。AIがサポートするのは、そういう「人が包み込む」空間のあくまで脇役。
「便利さを受け入れすぎずに信頼を取り戻すには?」と聞かれたら、答えは「使う acts で悩むより、問いかけにしてみたらどうかな?」でしょうか 🌈⭐️
じゃあ子どもとつくる未来の光って?
…今から「このバランス、どうしよう?」って考えるのが、楽しい悩みずら💦
ソース: Lepro Reveals New AI Lighting Pro Series During IFA 2025, Bleeding Cool, 2025/09/05 11:32:03
