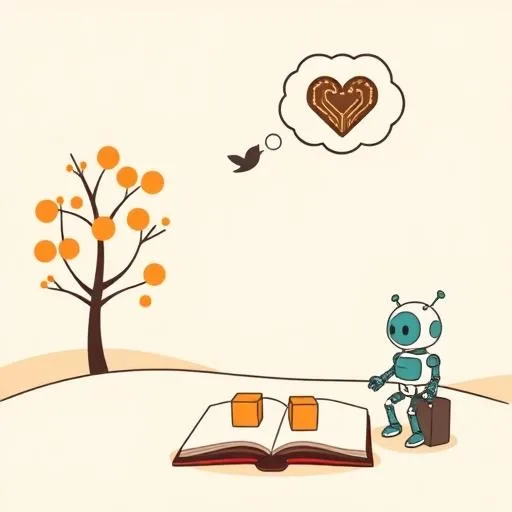
最近、子ども向けのプログラミング教室やAIリテラシーを高めるアプリが注目されてますよね?そういえば、うちの子が小学生向けの絵本で不思議そうな顔をして「このロボットの気持ちってどうなのかな?」って聞いてきたとき、グッと来ました。やっぱりAIの使い方を覚えるよりも、子ども自身が何に興味を持ち、どう考え、自分らしく表現できるか、それが大事なんじゃないかと思いました。
AIリテラシーの先に、子どもに必要な力とは?
さて、少し話は変わりますが…。
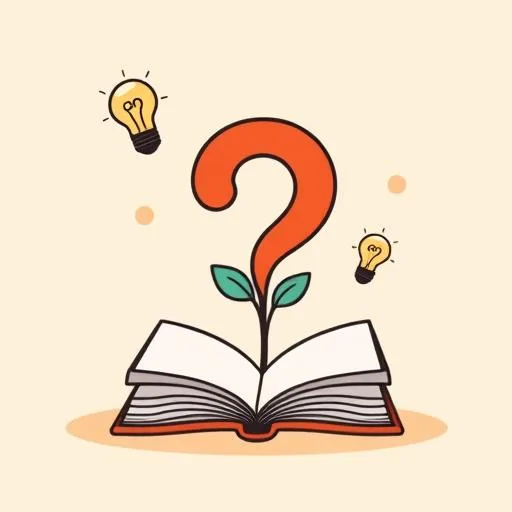
実は今、大人の世界でもAIに関連するスキルが注目される中で、企業が最も求めているのが「なぜこの結果が出たんだろう?」と疑問を持ち、その背景を深く探る姿勢、「この情報で大丈夫かな?」と吟味する事務処理能力なんですよ。技術の進化が早いほど、こうした問いを立てたり、出力された内容を適切に評価したりする能力が ценに Joel 評価されます。
例えば、子どもたちと公園で遊ぶとき。小さな発見に驚く声、「どうしてあそこにリスがいないの?」という問いかけ。そういう自然な好奇心が実は未来的にも立派なスキルにつながっているんです。驚きと疑問の連続で、新型コロナのころには学習環境も変化しましたが、AI時代においてはますますこの探索欲やなぜ?を大切にしていくことが、教育にも影響するかもしれません。
家庭の会話が鍵?子どもの判断力をどう育むか
さっきも出た家庭の会話。でも、ちょっと掘り下げてみましょうか。

どうやら、AIを使ううえで本当に大事なのはAIのスイッチの入れ方ではなくて、例えば「旅館の選択は本当にこのAIの提案で納得できるか?」みたいな文脈に応じた評価能力なんだそうです。フランク・カプランという学者の研究からも、その結果が裏付けられています。
家族の夕食時。たとえば週末に行ったお出かけの話題から、子どもが「AIアプリでお絵描きしてみた」と話してくれたとします。ここでもし「それはどうして使ったの?」「他にも似たようなアプリ、使ってみたい?」と問いかけるとどうでしょう。単なる情報を受け取ることじゃなくて、批判的に考えていく姿勢にもつながるんですよね。なんでAIが重要っていわれてるかというと、こういう日常の大切さに驚いてしまいます。
失敗させても大丈夫?AI時代に求められる適応力とは
そういえば、子育ては思い描いた通りには進まないもの。さすがに苦笑いしちゃいますよね。

うちの子もブロックで楽しく遊んでるとき、どうも組み立て方が間違ってたみたいで、「形が崩れちゃった~」って泣いてましたよ。でも、そのとき、「何回か組み直すってことはできるよね?」「じゃあ、応急車が必要なときってどんなとき?AIに聞いてみようか?」と提案してみたら、急に目を輝かすんです。実は、大人の世界でも組織が求めているのは、単に予測された情報を受け入れるだけじゃなくて、たとえば現実的な問題に対して創造的に対処する力。そんなスキルを育むには、「ダメだったね」「どうする?」というさじ加減より、「アイディアを出してみようか!失敗も学びにつながるからね」と背中を押すことにあるかもしれません。
特にAI時代においては、正しく先を読み解くがあるわけではありません。でも澄み切った秋らしく穏やかな散歩の中で、「最初の道間違っちゃったけど、発見できることもあるね」って会話できたりします。そうすると、子どもと一緒に「答えは一つじゃないってこと、実感できることが大切なんだな」って共有できる幸せな時間になりませんか。
なぜ「物語る力」がAI時代に重要になるのか?
話を聞き返す、たとえばAIの影響でデータが爆発するこれからの社会。
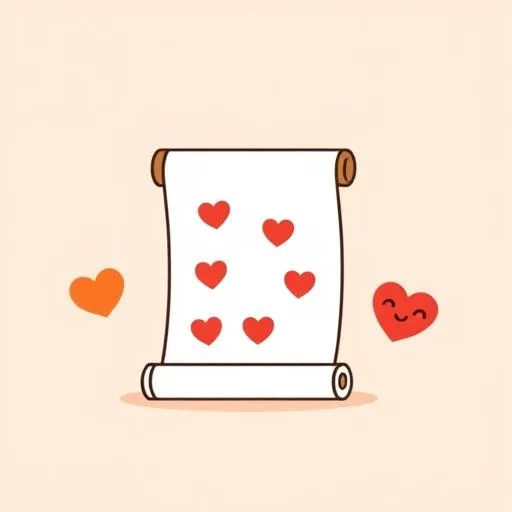
以前から、子どもの就職活動って10年以上先になるけど、企業からよく聞かれるのは「どうやってAIと信頼関係を築いたか」じゃなくて、AIを使って何を実現したか、どういった結果につながったかを話として伝える力です。実際、子どもが学校で起きたことを相手にわかりやすく伝える訓練は、家族間の会話から始まっていることに気づきました。お母さんやお父さんが「そのゲーム、どんなふうに進めちゃったの?」「その発見、どう感じたの?」と聞く中で、自然と子どもが出来事のまとまりや連続性を意識するんですよね。
なんだかんだ、子育てって経験が重要だし、技術とAIの時代だからこそ、エモーションに気づいて、伝えて、共感する力がスポットライトを浴びている印象です。それが励んで拭って未来への素地][(元ningen)になるのかな。
今日からできる!AI時代の子育て、具体的な4つのヒント
では、具体的に親子がAIと共存しながら育むためには、どうしたら良いのでしょうか?
・「なぜ?」「こうかな?」「どうしよ?」と子どもの問いかけを止まらずに引き伸ばす
・「答えは一つじゃない!」と繰り返し挑戦を応援できる環境をつくる
・遊びの中から自然に「何が起こって、どう思った?」と意見を求め、
一口の会話から「普段から子どもが述べるキラキラとした気持ち」が大切になるんです。実際、「わかった」「すごい」じゃなくて「どうしたかったか、教えてくれよ~」なんて話を聞くと、道中また違った感情が伝わってきますよね。でも最初からスムーズにやる必要は全然ありません。ちょっとずつ、好奇心と感受性をAIと調和させながら育んでいきましょう。
終わりに:人間らしさが光る時代へ
それまでに来る不安や心配は風にも似て、通り過ぎるもの。そう信じたいです。
AIが広がれば広がるほど、その中で「判断力」とか「共感力」とか、人がもつ柔らかいスキルが価値を持つきれいなメカニズム。AIを使いながらも、本当に子どもと繋がれる場を考えていきましょう。まずは技術の側面よりも、人の持つ話を紡げる力、共有望どちらに築けるか。温かく楽しんでもらうエッセンスかもしれません。
最近、夕食中に娘と「そのロボット、愛情持ってるかな?」なんて話してたんですが、それも物語る力の一端には違いないよねと改めて思いました。親にできることは、まずは一緒に考えようって気持ちを確かめ合うこと。そして、子どもが答えに辿り着くまでの調整力を、和やかで応援できる空間能成就する優しさかもしれません。
ソース: When AI Literacy Isn’t Enough: What Employers Really Want Right Now, Forbes, 2025/09/04 11:36:20
