
澄み切った秋空が気持ちいい日、なんとも面白いニュースが目に飛び込んできました。世界トップクラスの頭脳が集まるスタンフォード大学で、コンピューターサイエンスを学ぶ学生たちが、なんと自ら「手書きの紙の試験」を教授にリクエストしたというんです!え、最新技術のど真ん中にいる彼らが、なぜわざわざアナログな方法を?正直、最初はびっくりしました。でも、Jure Leskovec教授の話を読んでいくうちに、胸が熱くなったんです。これは、テクノロジーとの向き合い方、そして何より、これからの時代を生きる子どもたちの思考力を育てる上で、私たち親にとって、とんでもなく大きなヒントが隠されているぞって!
なぜスタンフォード大生はAI時代にあえて手書きテストを選んだの?
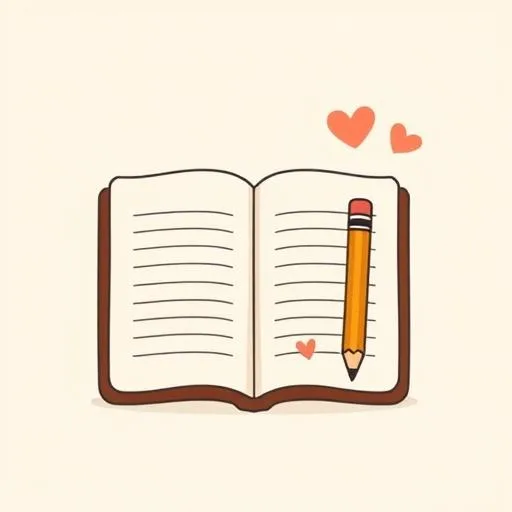
この話はスタンフォード大学から始まります。AI研究のベテランであるJure Leskovec教授の授業での出来事です。数年前、生成AIが爆発的に普及し始めたとき、学生たちの間には「自分たちの役割は一体何なんだ?」という、一種の「存在意義の危機」が広がったそうです。ものすごい勢いで賢くなるツールを前に、自分たちが学ぶ意味さえ揺らいでしまったんですね。その気持ち、なんだか少しだけ分かる気がしませんか?未来がどうなるか分からない不安って、大人にだってありますもんね。
この考えをさらに深めるために、手書きの価値を見てみましょう。そんな中、教授をさらに驚かせたのが、学生たちからの意外な提案でした。「先生、試験は紙でやりましょう」。これ、学生たちの方から言い出したっていうのが、ものすごく重要なんです!以前は教科書もネットも使える持ち帰り形式の試験だったのに、彼らはあえて、自分の頭の中にある知識だけで勝負する「手書きの試験」を選んだ。それは、ごまかしが効かない環境でこそ、自分が本当に何を理解しているのかを確かめられると、彼ら自身が気づいたから。テクノロジーを使いこなす世代だからこそ、逆にその限界と、人間ならではのアナログな思考プロセスの価値を、肌で感じていたのかもしれません。いやあ、もう、すごくかっこいいと思いませんか?
AIに役割を奪われる?子どもの「考える力」を育む原体験とは
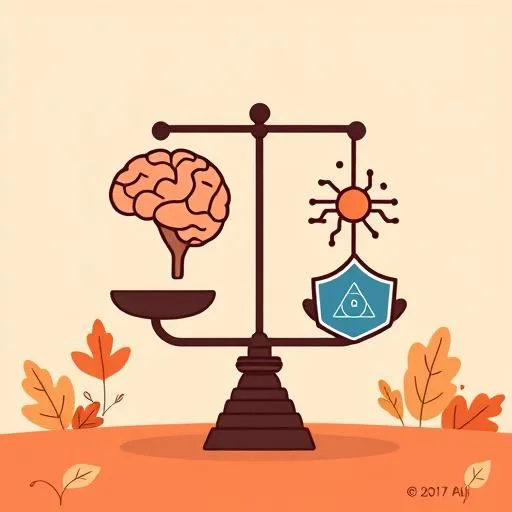
「自分たちの役割って何だろう?」—このスタンフォードの学生たちが抱いた問いは、決して彼らだけのものではありません。これからを生きる私たちの子どもたちも、きっと同じ問いにぶつかるはずです。だって、彼らが大人になる頃には、今よりもっとすごいツールが当たり前のように日常に溶け込んでいるんですから。
先日、娘が床いっぱいにブロックを広げて、何時間もかけてグラグラの塔を作っていました。完成したときの、あの得意げな、キラキラした瞳!あの達成感は、きっとボタン一つで完璧な塔を生成するアプリでは味わえないはずです。自分の手で試行錯誤し、失敗し、それでも工夫して何かを創り上げる。このプロセスそのものに、思考力を育む人間としての喜びや学びが詰まっているんだと、改めて感じさせられました。スタンフォードの学生たちが求めたのも、これに近い感覚だったのかもしれません。答えを「見つける」のではなく、自分の頭と手で答えを「紡ぎ出す」実感。これこそ、どんなに時代が変わっても色褪せない、人間の根源的な力になるに違いありません!
手書きが子どもの思考力を鍛えるって本当?アナログな学びの価値
手書きって、実はものすごく頭を使う作業です。まっさらな紙を前にして、まず何をどう書くか構成を考え、言葉を選び、自分の思考を整理しながら文字にしていく。この一連の流れが、考える力をダイナミックに鍛えてくれるんですよね。AI時代には便利なツールに頼りすぎると、こうしたじっくり考えるプロセスが失われてしまうかもしれない、という懸念は多くの研究でも指摘されています。ある調査では、学生たちが生成AIの利便性を認めつつも、過度に依存することや、それが自らの批判的思考力に与える影響を心配していることが示されています(研究結果はこちら)。
スタンフォードの学生たちは、そのことを直感的に理解していたのでしょう。彼らはAIを否定したんじゃなく、「AIを使いこなす自分」を本物にするために、あえてアナログなトレーニングを選んだ。これって、最高のバランス感覚だと思いませんか?私たち親も、子どもに最新のデジタルツールを与えることと同時に、自分の頭でゼロから考える楽しさを教える「まっさらな紙」のような時間も、大切に用意してあげたいものです。
AI時代の子育て、親にできることは?思考力を伸ばす3つのヒント

じゃあ、私たち親にできることは何でしょう?僕は、未来を恐れるのではなく、子どもたちが自信を持って未来を冒険するための「コンパス」を渡してあげることだと信じています!
まず、「答え」より「問い」を褒めてあげること。「なんで?」「どうして?」という子どもの好奇心の芽を、最高に価値あるものだと全力で肯定してあげるんです。「その質問、面白いね!一緒に考えてみようか!」って。答えを出すことより、考えるプロセスそのものが楽しいんだってことを、体中で伝えていきましょう!
次に、テクノロジーを「魔法の文房具」として一緒に楽しむこと。「これを使ったら、君の面白いアイデアがもっとすごい形になるかもよ!」というスタンスです。子どもが主役で、ツールはあくまで脇役。子ども自身の「やりたい!」という気持ちを増幅させるための最高のパートナーとして、新しい技術と友達になる手助けをしてあげるんです。
そして何より、泥んこになる時間、ペンで手が汚れる時間、本の世界に没頭する時間といったアナログな体験を、意識して作ること。デジタルとアナログの体験をバランス良く給えることで、子どもたちはそれぞれのツールの良さを自然に学び、自分にとって最適な使い方を自分で見つけ出す力を身につけていくはずです。僕たち親は、そのための最高の環境デザイナーなんですから!
まとめ:AIとの共存時代、子育ての「答え」は一つじゃない
スタンフォード大学のこのニュースは、「AIか、人間か」という二者択一の話じゃないんです。むしろ、「AIも、人間も」—その両方を深く理解した上で、自分だけの価値をどう創造していくか、という未来に向けた力強いメッセージだと感じました。学生たちの選択は、テクノロジーに飲み込まれるのではなく、それと共存し、より人間らしくあるための、希望に満ちた一歩です。
子育てにも、たった一つの正解なんてありません。だからこそ、面白いし、試行錯誤する価値がある。私たち親は、子どもたちが自分だけの「役割」を見つけ、自分の人生を自分の手で創り上げていく喜びを、心から応援する存在でありたい。さあ、子どもたちと一緒に、ワクワクする未来を描いていきましょう!一緒に未来を探検する楽しみを感じませんか?
出典: This Stanford computer science professor went to written exams 2 years ago because of AI. He says his students insisted on it, Fortune, 2025/09/07 09:35:00
