
先日、Urban Companyというホームサービス企業のIPO(新規公開)に関するニュースを目にしました。このニュースから、子育てのヒントを考えてみました。投資家向けの資料には、持続的な損失や競争の激しさ、ギグワーカーへの依存など、さまざまなリスクが記載されていて、ハッとさせられました。これって、私たち親が子どもたちの未来を考える上でも、とっても考えさせられませんか?テクノロジーが急速に進化する中で、どんなスキルを育み、どうバランスを取っていくべきか、一緒に考えてみましょう。
ギグエコノミーと子どもたちの未来はどうなる?

Urban CompanyのIPO資料を読むと、ギグワーカー(フリーランスのサービス提供者)への依存度の高さがリスクとして挙げられています。ギグっと考えてみると、これからの経済のあり方を象徴する出来事ですね。私たちの子どもたちが大人になる頃には、こうした働き方がさらに一般的になっているかもしれません。
そこで思うのは、adaptability(適応力)の重要性です。例えば、うちの娘が大きくなった時、彼女がどんな職業に就くとしても、変化に対応できる柔軟性や、自分で考え行動する力を身につけてほしい。固定観念に縛られず、新しい働き方や技術を受け入れられる心の広さこそ、未来を生き抜くカギになる気がします。
親としてできることは、小さな頃から「自分で決める」体験を積ませてあげること。例えば、週末の予定を子どもと一緒に計画してみる。公園に行くか、家で工作するか、彼女の意見を尊重しながら決める。こんな小さな習慣が、実は大きな力になるんです!
テクノロジーと人間らしさのバランスはどう取る?

Urban Companyのようなプラットフォーム企業は、テクノロジーを駆使してサービスを効率化しています。でも、IPO資料には「品質管理の問題」や「パートナーの離脱」といったリスクも記載されていました。テクノロジーが進化しても、結局は人間同士の信頼関係が基盤になるんだな、と改めて感じます。
これは子育てにも通じる話で、いくらAIやデジタルツールが発達しても、子どもたちに必要なのは温かい人間関係や共感する力です。例えば、画面越しのコミュニケーションも便利ですが、やっぱり直接顔を合わせて遊んだり、話したりする時間はかけがえがない。あなたの家族では、どんなバランスを取っていますか?
我が家では、夕食後の30分は「ノーデバイスタイム」と決めて、家族でカードゲームをしたり、その日の出来事を話し合ったりしています。そんな小さな習慣が、テクノロジーと人間らしさのバランスを育む第一歩になるかもしれません。
失敗から学ぶ力の育て方は?
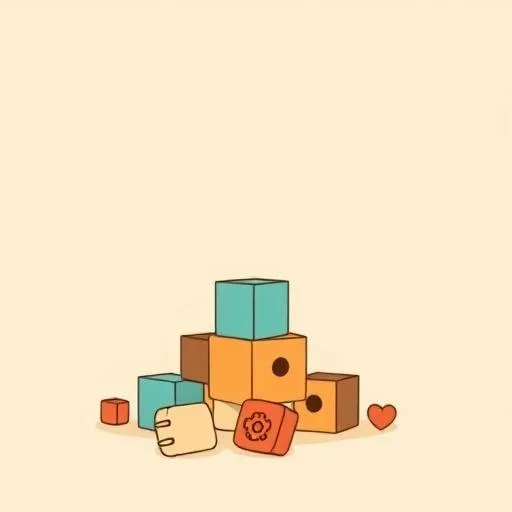
Urban CompanyがIPO資料で「持続的な損失」をリスクとして公開していること、じつはすごく潔いなと思いました。失敗や課題を隠さず、正面から向き合う姿勢は、企業だけでなく、子育てにも大切なことです。
子どもたちにも、失敗を恐れず挑戦する心を育んであげたい。例えば、工作で思うようにいかなくても、「次はどうしようか?」と前向きに考えられるように。小さな失敗を経験することで、レジリエンス(回復力)が自然と身についていくんです。
先日、娘が初めて自分でお菓子を作ろうとして、ちょっと焦がしちゃったことがありました。でも、「次は火加減に気をつけてみようね」と話したら、彼女はニコニコしながら「今度は成功させる!」と意気込んでいました。そんな瞬間、子どもの成長を心から誇らしく思います。
変化の時代を生き抜く家族の知恵とは?

Urban CompanyのIPOが示すように、ビジネスも子育ても、予測できない変化の連続です。でも、そんな時代だからこそ、家族の絆や温かいコミュニティの価値が輝くのかもしれません。
例えば、近所の友達と公園で一起に遊ぶ、地域のイベントに参加する——そんな当たり前のつながりが、子どもたちに安心感や所属意識を与えてくれます。テクノロジーが発達しても、人と人との触れ合いが育む情緒は、何ものにも代えがたいですから。
最後に、ひとつ提案です。週末に家族で「未来の仕事」について話し合ってみませんか?AIができること、人間にしかできないこと、子どもたちの自由な発想は、きっと私たち大人にも新たな気づきを与えてくれますよ。子どもたちの声に耳を傾けると、未来への希望がひろがりますよね。
ソース: Urban Company IPO risks explained: 12 warnings on operations, regulations and valuation, Economic Times, 2025/09/06 07:22:28
