
ふとニュースを見れば、米国がインドのIT輸出にIT関税を検討しているという話題が。Tata Consultancy ServicesやInfosysといった企業が懸念を表明しているようですが、これって遠い国の話じゃないんですよね。だって、これが現実になれば、AIをはじめとするデジタル技術の進化のスピードや方向性が変わるかもしれない。そしてそれは、私たちの子どもたちが大人になる頃の世界と、そこで求められるデジタルリテラシーのあり方を形作る大きな要素の一つになるから。
IT関税は、私たちの家庭にどう影響するの?
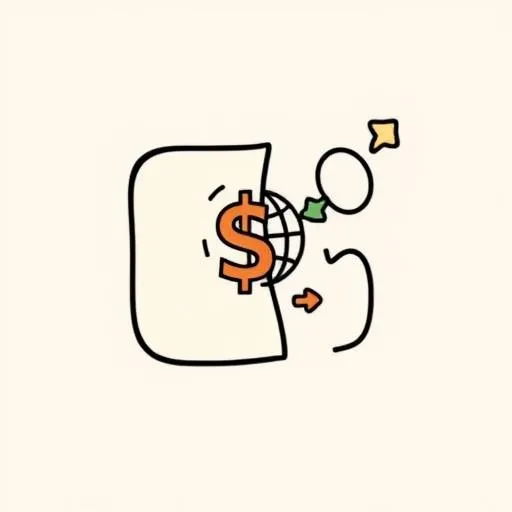
ええ、2830億ドル規模のインドIT産業の60%以上が米国市場に依存しているという現実。ここに関税が導入されれば、コスト増は避けられず、そのしわ寄せは結局、技術の進化スピードやサービス品質に影響するかもしれません。この影響は、家庭でのデジタルツールの利用にも及ぶかもしれませんよ。
例えば、我が家では週末によく新しいアプリや教育ツールを試すんですが、もし開発元の企業がコスト増でイノベーションに注力できなくなったら?子どもたちがアクセスできる技術やデジタル教育の質が変わってしまうかもしれない——ほんとに他人事じゃないんですよ!
AI時代を生きる子どもたちに、本当に必要なスキルとは?
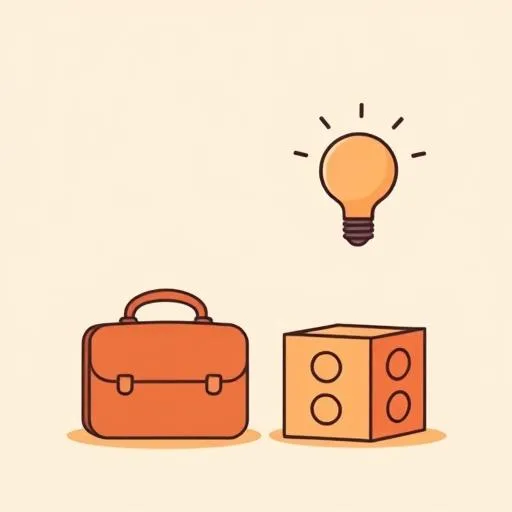
経済が不安定でAIがどんどん進化する今、関税問題はさらに複雑な要素を追加します。でも、どんな状況でも子どもたちが強く生き抜くために必要な力は変わりません。好奇心、適応力、創造性——これらはデジタル世界でもリアル世界でも通用する普遍的なスキルです。
たとえば、週末に親子でコーディングゲームに挑戦したり、AIがどう動くかを豆腐のレシピ検索アプリで説明したり。そんな楽しい体験が、本物のデジタルリテラシーの土台を作るんです。国際情勢は変わりやすくても、子どもたちが内側に育む力は未来を切り開く宝ものですね。
親子でデジタルな未来について、どう話せばいい?

世界がますます繋がりながらも分断の動きが見える今、家族としてどうデジタル世界と関わるかがカギになります。子どもたちの笑顔を守るため、私たち親ができる小さな一歩を一緒に考えてみませんか?
夕食の時に『もしAIがお手伝いしてくれるなら、どんなことを頼みたい?』なんて質問から始めてみるのもいいですね。国際的な出来事と自分たちの生活の繋がりに気付いた瞬間こそ、未来への希望が生まれるチャンスです。
明日から親子で実践できる、具体的なアクションは?
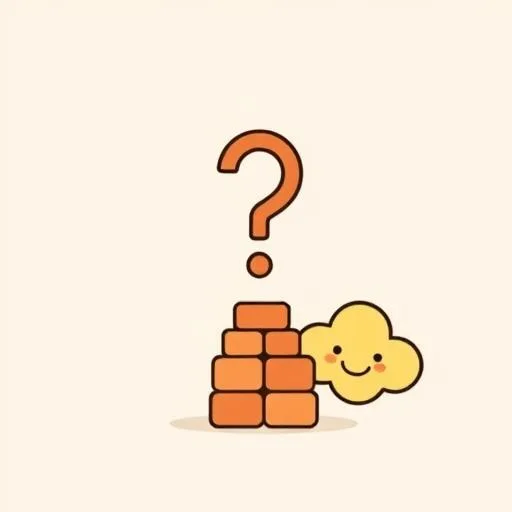
大きな問題は時に無力感を覚えさせますが、家族レベルでできることはたくさん!まずはデジタルリテラシーを高める楽しい習慣から——オンラインで学びながらも、目の前の家族との会話を大切にすることが何より大切です。
実践のヒント: YouTube動画を見ながら『この技術の裏側ではどんな人が働いているんだろう?』と想像してみる。海外の開発者への感謝を子どもと話し合うだけでも、世界はぐっと身近になるはず。だって技術が進化しても、支え合う人間の心こそが未来を変える原動力ですから!
出典: IT Inc worries as US may slap tariffs on software exports, Economic Times, 2025/09/07 00:30:00
