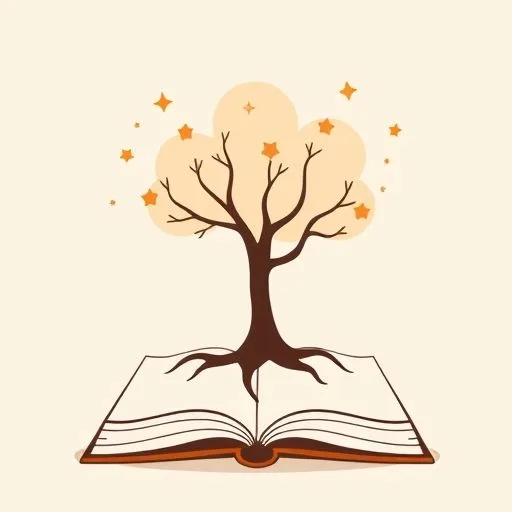
朝の支度をしながらニュースを見ると「AIによる大規模失業」の見出しが目につきますよね。でも実際のデータを見てみたら…ちょっと違った景色が見えてきました。うちの7歳娘とAIを組み合わせて遊ぶ日々のなかで感じていること、ちょっと聞いてくれませんか?
AIで失われる仕事?データから見える意外な現実とAI教育

TechWolfという会社のデータを見ると驚くべきことがわかります。仕事のタスク18%が完全自動化可能だと。でも62%は人間でないとできないなんて…むしろ安心できますよね!それにですよ、75%のテクノロジー企業の社員がAI支援職に移行可能なんて。会社の偉い方たちは、なぜスキルアップを選ばないのでしょうかね。
Built Inの記事にもあるように、企業の組織運用そのものに問題があるってことです。どれだけAIが優れていても、人間関係や役割がガタガタだったら意味がない。うちの娘と遊ぶときもそう感じます。ルールがわかるボードゲームほど楽しくないから、しっかり一緒にルール作りするために楽しんでますよ!
パパの視点を活かす:AI教育で変えるべき2つのこと
やりたいことを賛成してくれるAIよりも、子どもの創造性を引き出すパパが不可欠というのは、インチョンの国際学校でも共通する話。ちょっとカナダっぽい例えですが、トランプの山を何枚でもAIで並び替えられると夢中にさせたことがあります。
でも、DOGEの例が示すように、最後は人間としての価値観とつながりが未来を築く力になるのだと、しみじみ感じます。うちの会社でも課長の頃からずっとそう思ってました。娘が幼い頃から教えてきたんです、技術よりも思いやりのほうが大切だと!
子どもたちに未来を託す:AIを味方にするパパ流実践法と教育
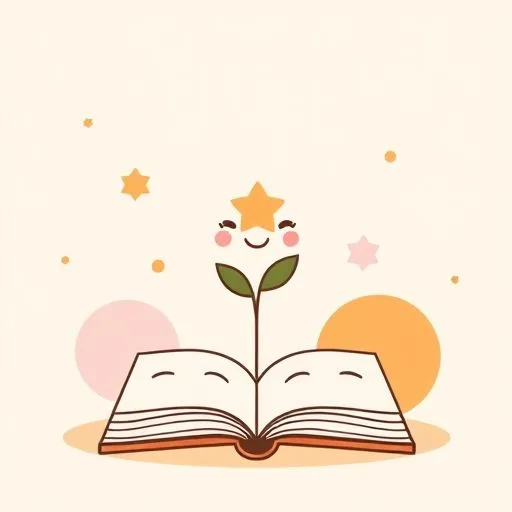
Grammarlyから始まるAIの成長を実感してたら、7歳娘の創造絵本づくりにも活用できると気づきました。一緒に旅行プランをAIで考えたときは、風景の魅力を発見する子どもたちの瞳が印象的でした。
データをいじる職業柄(笑)、これらの経験を分析して得た答えは「消化不良せず成長のパートナーに」。なんていいんでしょ?AI-assisted codingツールで例えるなら、親子でコードする時間こそが学びの深さですね。会社でも、この親子でのコード体験こそが学びを深める鍵だと熱く語ったのですが、なかなか聞いてもらえなくて…
娘が昆虫図鑑と一緒に遊ぶように、現代のパパはAIとどう付き合うか試されているんです。子どもたちの想像力とAIの分析力を結び付けたら、とんでもない可能性が開けますよ。一緒に boarded that crazy train of discovery しましょう!
不安に打ち勝つパパ力:技術変化時代の家庭とAI教育

会社でAI導入するたびにシニア世代が影で涙しているのを見てきたんです。だからこそ、5・6年生になる子どもたちにもそっと伝えます。「アイデアを共有できる場が大切なんじゃないか」と。最近娘が言いました。「パパ、ロボットと遊びたいって言ってるけど、パパと遊びたいって言ってるほうが絶対多いよ!」と。
エングルワイズな見方はこんなこと。「現在のAI導入で失業する職はわずか2.5%」。真相は、実世代と実AIの融合てき工夫が足りないことだと感じます。家庭でもそうですよね。ゲームを禁止するよりも、一緒にプレイしながらルールを作ることが大事だと。
働きながら家庭を守るパパの責任は、子どもの教育的瞬間と技術の可能性をむすぶ橋渡し。うちの娘と作る「AIで歌う伝統歌」なんて、伝統と革新の共存を毎日体現しています。(7歳にしては難しかったけどね~笑)
将来への希望:AIと共生する家族教育と子どもの未来

データ分析して40年、現場で学んだことは「人間らしい想い出こそが価値」ってこと。Google Trendsを見ると「AI教育」というワードが注目されつつありますが、まずは遊び心で取り組むのが一番ですよ。
AIが子どもの成長の一部になることは避けられない。でも心の教育はパパが主役。長年の職場経験を通じて確信するのは、「共感能力」こそ親子の絆を強くする力。
娘が大好きだったのは「AI素材で伝統キムチポットデコ」。サンクンシティで拾ったものに最新デザインソフトを使って個性を発揮。伝統と現代の融合を、この年で楽しめるんですから驚きですね。
IMFのデータにもある通り、AIが子どもの成長の一部になることは避けられない。でも心の教育はパパが主役。長年の職場経験を通じて確信するのは、「共感能力」こそ親子の絆を強くする力。技術が進化しても、子どもたちが「パパに教えてもらいたい」って瞳を輝かせる瞬間を守ってるんです。
Source: The AI job apocalypse is a myth: layoffs are the real problem, Slashdot, 2025/09/11
