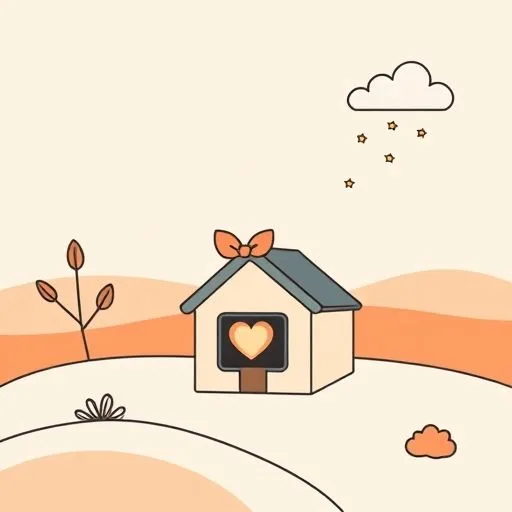
夕食の支度中、お風呂上がり、寝る前の5分──そういえば、最近子どもが「なんで?」と聞いてくる瞬間が減ったな…と気づいたことはありませんか? 特別な知育教材も高価なおもちゃもいりません。今日ご紹介するのは、台所で、通園途中で、布団の中ですぐに始められる「好奇心の育て方」です。
子どもの「知りたい」を消さない魔法の返し方
公園で拾った石を嬉しそうに見せる我が子に「汚いから捨てて」と言ってしまったこと、ありますよね。日常には無意識に好奇心の芽を摘んでしまう瞬間が潜んでいます。実は大切なのは「正解を教える」ことより「一緒に不思議がる」姿勢です。
- NG対応:「今忙しいから後でね」→ OKフレーズ:「面白いもの見つけたね!どこが気になる?」
- NG対応:「そういうものなの」→ OKフレーズ:「ママも不思議だな…一緒に調べてみる?」
先月、5歳の息子が「雨ってどうして止むの?」と聞いてきた時、洗い物の手を止めて「本当だね、急にやんだね。もしかして雲さんが…?」と想像を膨らませたら、翌日保育園で「ママと雲の研究をしたんだよ!」と得意げに話していたそうです。
家庭でできる探求のスイッチ3つ
好奇心は特別な時間を作らなくても、日常の些細なやりとりで育ちます。我が家で実践している簡単な習慣をご紹介しましょう。
1. 「質問番長」リレー
毎週日曜日に家族で「質問番長」を決めます。番長は気になることを家族に質問し、みんなで仮説を考えます。「パンはどうして膨らむの?」という質問に「イーストさんがプープーするから!」と4歳の娘が答えた日は、実際にパン生地を触らせて発酵の不思議を体感させました。
2. 間違い探検隊
「間違えたらラッキー」を合言葉に、お互いの間違いを面白がる習慣を作りました。
こんな変な答え、考えたことありますか?
先日「カタツムリの殻は取れるの?」という問いに「取れたら着替えられるかも!」とわざと変な答えを言うと、子どもたちが大笑いしながら図鑑で確認していました。
こうして、日常に溶け込む小さな習慣が、子どもが思う存分「なんで?」と探索できる、心の余白を作り出すのです。
好奇心が育つ「間」の作り方
子どもの「なんで?」が減る大きな理由の一つが「待てる環境」の不足です。保育園の送迎中、ふと立ち止まってアリの行列を見つめた時──
「早く行こう」ではなく「どんな発見があったの?」と一言待つことで、子どもの観察眼は研ぎ澄まされます。
我が家では「不思議メモ帳」をリビングに置き、気づいたことを絵や文字で自由に書けるようにしています。先月は「なんで冷蔵庫は冷えるの?」という質問がきっかけで、家族で冷蔵庫の裏を覗くという冒険が始まりました。
答えよりプロセスを楽しむ姿勢が、生涯消えない探求心を育てるのです。
消えかけた「なぜ?」に火を灯す方法
「最近質問してこないな」と感じたら、逆に親から問いかけてみましょう。我が家で効果があったのは「パパの不思議ノート」作戦です。台所に張ったホワイトボードに日替わりで「今日のなぜ?」を書いておきます。
- 月曜:「トマトは野菜?果物?」
- 水曜:「虹はどうして7色?」
- 金曜:「飛行機雲はどうやってできる?」
最初は反応が薄くても、3日目あたりから子どもたちが自主的に調べ始めます。先週は小学2年生の娘が「風ってどこから来るの?」という質問に、得意げに「空気の温度差が生み出すんだよ」と教えてくれました。その知識よりも、娘の頬がリンゴのように赤らみ、目がキラキラと輝いていた姿が、何よりも宝物でした。
Source: Lessons from using AI in Discovery, Thoughtbot, 2025/09/15 00:00:00
