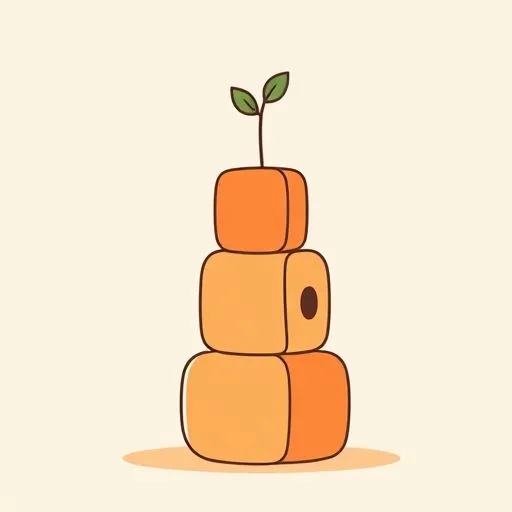
今朝、電車に乗っていたら、隣にいた人が話しているのが聞こえてきたんです。ある大企業の会議で、“いちいちスマホの設定を覚えるのは面倒くさい”と技術学習を避ける社員の存在が問題になっているとか。
その話を聞いて、ふと娘の顔が浮かびました。昨日の図工の時間、AIのお絵描きアプリで、それはもう、すごい作品を完成させたんです。
「便利なだけじゃダメな理由」~デジタルリテラシー教育の本質とは?
このニュースを聞いて、職場の状況と自宅がリンクしました。娘の絵本アプリ、最初は「タッチすれば自動でめくれる」だけで満足していました。
でもある日、娘が「どうして絵がうごくの?」って聞いてきて。その時、.imgタグの数式や.pngの仕組みを考え始めることの大切さに気づいたんです。
「なんでだろう?」って探求する気持ちは、デジタルリテラシー教育の基礎となります。
「デジタル時代の遊び方革命」~AI時代の子育てで楽しみながら学ぶには?
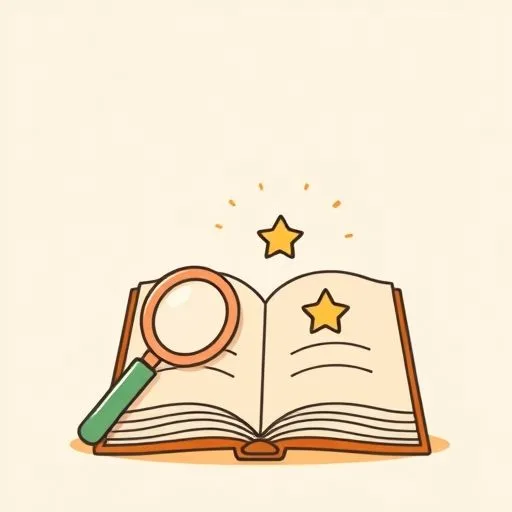
思い出されるのは昨年、家族での伊豆旅行。海をバックにした『ARお絵描き』に娘が夢中だったこと。
消える波打ち際の絵を追いかけながら“どうやって表示されるの?”って問い詰めてきたのをきっかけに、今では娘自身がアプリのフィーチャーをカスタマイズしてます。
これって、なんだか職場で新しいシステムを導入する時にも通じる考え方ですよね。失敗を恐れず試すことで、タフさも自然と身につくんだな、って思いました。
「面倒くさがり屋を打破する戦略」~ゲーム感覚でデジタルリテラシーを高める方法
職場的にはゲーム要素の導入が効果的と聞いてますが、家庭の場合はどうでしょう?我が家では毎週「パパと娘のおもちゃハックデー」があります。
娘の積み木のおもちゃにセンサーを組み込む遊びがマイブーム。この考え方は教育機関の実践例からヒントを得ました。
HTMLタグの概念と積み木が合体するのを見て、娘はこう言いました。“パパ、おもちゃがお話し始めた!(笑)”
「未来のスキルは今から降る雪のようで」~AI時代の子育てで育むべき能力とは?
雨の日の外遊びが危ないとか言いながらも、娘は水たまりでカメラアプリの映り込み実験しています。あるときはブランコの動きが画像補正アルゴリズムにどう影響するかを。
まだ小1ですが、こうした体験は大人の定型業務に挑戦するようなスキルの土台になります。
あまり深刻にならず、遊びの中で咀嚼するのが私の流儀です。
「技術学習の落とし穴を回避」~デジタルリテラシー教育で気をつけるべきポイント

話し変わって、先日働いている姿を娘が見てしまった時の話。作業中のAdobeアプリ画面に娘が興味津々。“パパ、それ楽しいの?”って顔が印象的でした。
その夜、一緒に”デジタル坂道”企画を考えました。娘が好きなキャラクターを紙で描き、それをスキャンしてAIが動かすという工程。ブログにも紹介されるくらいはまりました(笑)
「パパ的未来準備術」~AI時代の子育てで子どもに伝えたいこと
これからの世の中で、娘のような世代に必要なのは「未知へのワクワク感」だと感じてます。学校のプログラミング必修化にも、“どうしてこれをやるの?”と問う姿勢を見たくなります。
課題はありますが、例えば広告にも出てくる“ジェネレーティブAIで小学生が小説を書く”なんてのも悪くない。大切なのは‘“機械任せ”のとらえ方ではなく、ツールとの共生視点’です。
「パパ道、ここにあり」~デジタルリテラシー教育の実践的なアドバイス
結局、私たち親世代が“分かりにくいしパス”って思ってる時間、子どもたちは既に新しいツールを使ってます。
検索結果分析から導き出している心得とは、【技術への抵抗をまず“遊び”の中で溶かす】というシンプルな発想。先週の船のハンドル遊びだって、今や親子でパラメータ調整の実験道具化しちゃって。
子どもの成長には見えないガラスの屋根がありますが、破るコツは遊びの中に。うちの食卓では、お味噌汁とフライドポテトが並ぶことも珍しくなくて、そんなハイブリッドな日常が、娘の探求心を刺激しているのかもしれません。
Source: Why Beliefs About Technology Training Hurts Workplace Innovation, Forbes, 2025-09-14.
