
あるオープンソースプロジェクトがAI生成コードの全面禁止を決めたと聞いた時、ふと先週の出来事を思い出しました。
隣のパパさんがつぶやいた言葉が胸に刺さった。「ブロック遊びもAI教育も、結局は一緒に作る過程が大事なんだよね」
技術と人間の関係を考える時、子育ての日常から学べることが意外に多いのではないでしょうか?
表面の便利さの裏側にあるもの
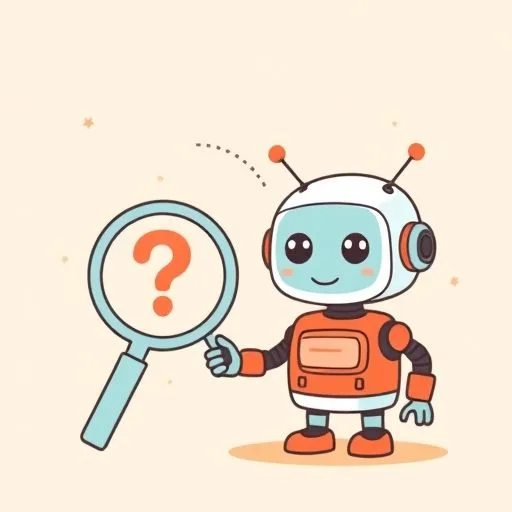
AIが生み出すコードの何が問題なのか──ふと子供が描いた絵を眺めながら考えてみます。完成図は色鮮やかで一見完璧でも、描き方のプロセスが見えない不安。
それはまるで、生成AIが作るコードって、実は『わかったつもり』になりがちなんだよね。
オープンソースコミュニティが懸念する3つの悩みどころは、子育ての葛藤にも重なります。
まず『おとぎ話症候群』──ハローキティのような架空のライブラリ参照の危険性。
次に『記憶の迷子』問題。コード片の由来がわからず著作権侵害の連鎖を引き起こす可能性。
そして最も皮肉な現実、AIを検証するために人間の労力が増えるという逆説的なジレンマ。
これって子育ての『どうして?攻撃』と同じでしょ?
コーヒーブレイクのような共同作業

オープンソースプロジェクトのコードレビューが、公園で砂のお城を作り直す親子の会話みたいなものなのかも。『コーヒーブレイクのようなもの』と言われる理由を考えてみると、そこには子育てとの意外な共通点が。
ベテランと新人が意見を交わす中で生まれる気付き──宿題を一緒に解く親子の時間に似ています。
すぐに答えを教えるのではなく、考え方を整理する過程こそが大切。
あるプロジェクトリーダーが『コードより思考の軌跡が人を育てる』と言っていたのが印象的でした。
技術の進化が加速するほど、人間同士のこうした交流が貴重になるのかもしれません。
料理教室方式のバランス術
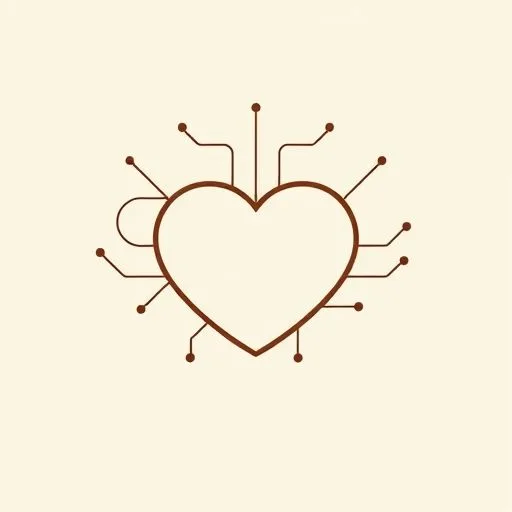
完全拒否か全面受け入れか──その二択ではない第三の道を探す時、家庭の調理台がヒントになります。
AIを材料の下ごしらえ担当に、人間を最終調理役にした『お料理教室方式』。
エラーチェックにはAIを活用しつつ、創造的工程は人間が主導するハイブリッドモデル。
ふと思い出したのは、面白い『逆転教育』のアイディア。
AIが書いたコードを教材に、間違いを修正しながら学ぶ方法は、子供の落書きを一緒に直しながら絵の基礎を教える姿に通じます。
透明性という名のお小遣い帳
あるプロジェクトが採用した『透明性マイルストーン』制度が興味深いです。
使用したAIツールを明記する義務付け──これを聞いた時、子供にお小遣い帳をつけさせる教育法を思い出しました。
砂場で共同制作する子供たちのように、オープンソース開発の未来は『作っては壊し、直し合いながら進化する』姿かもしれません。
技術の進化速度より、信頼関係の密度が未来を形作る。
子育てと技術革新、一見遠いようで実は近いこの二つの営みが教えてくれることです。
技術も子育ても、信頼関係が育むもの。次の世代へバトンを渡す瞬間を、私たちはちゃんと見届けていきたいですね。
Source: Cloud Hypervisor says no to AI code – but it probably won’t help in this day and age, TechRadar, 2025/09/15Latest Posts
