
夕飯の支度をしながら、家族みんなで野菜を切る手を止め、小さな子供の質問に耳を傾けている姿です。
「AIってなにが得意なの?」「人間より頭がいいの?」。スマートスピーカーに話しかける息子の横で、私たちはスマホを取り出すでもなく、「どう思う?」と問い返していました。
AI時代の子育てで本当に大切なのは、答えを即座に与えることじゃないんだと。
「すぐ調べない」勇気が育む考える力

週末の公園でのことです。子どもが突然「AIはどうして間違えるの?」と聞いてきました。
私たちは立ち止まり、少し考えてから「人間が作ったものだからかな」と答えました。でもそこで終わらないのはすごいんだね。「じゃあ、どうすれば間違いを少なくできると思う?」と逆に質問を投げかけたんです。
子どもが頭をひねりながら考えている姿を見て思いました。正解のある問いではなく、思考を深める問いかけこそが、これからの時代に必要だね。
親も知らないことで一緒に成長する

ある日の夕方、子どもに「AIの、人間として守るべきことって何?」と聞かれたことがありました。正直、私たちも十分に理解していないテーマです。でも私たちは顔を見合わせ、「一緒に調べてみようか」と提案しました。
スマートスピーカーに質問しながら、そしてときには図書館の本を開きながら、家族で学ぶ時間が始まりました。大切なのは、親がすべてを知っていることではなく、知らないことを認めて一緒に学ぶ姿勢なんだと気づかされた瞬間でした。
子どもの「パパも知らなかったんだ」という言葉に、親子で「わかった!」と声をあげた瞬間、ふと温かな気持ちが広がりました。
デジタルとアナログのバランス術
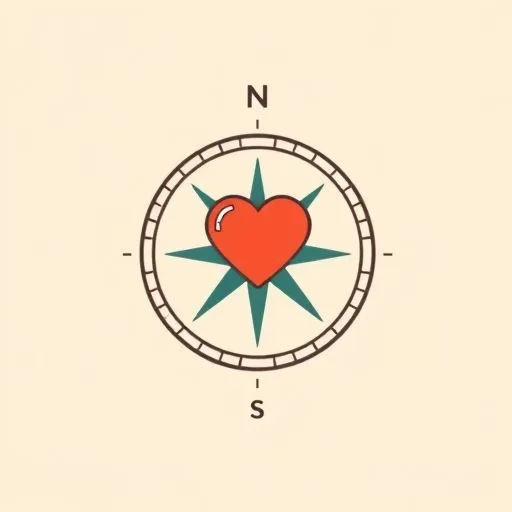
我が家の面白いルールがあります。どんなに面白い動画を見つけても、必ず実際にやってみること。
例えば鳥の飛び方についてのAI動画を見た後の週末には、公園で実際に羽ばたく動作を真似てみます。私たちが「画面の中と外を往復する旅のようだね」と話していたのが印象的でした。
デバイスの前に積み木を置き、AIが回答する前にまず自分の考えを積み上げさせる工夫にも感心させられます。 テクノロジーは教師ではなく、問いを深める道具として活用する——そのバランス感覚こそが、これからの親に必要なのかもしれません。
子どもの「なぜ?」を未来の羅針盤に

先日、子どもがAIに「幸せって何?」と質問しているのを耳にしました。返ってきた答えに納得していない様子の息子に、私たちは「人間にしか分からないこともあるんだよ」とそっと伝えていました。
昨日の夕方、こんな光景を目にしました。リビングで子どもがスマートスピーカーを前に「AIさん、君は自分で考えてるの?」と真顔で質問している姿です。
その横で私たちが笑いをこらえながら見守っている様子に、ふと思いました。子どもたちの純粋な質問こそが、AI時代の本質を突いているのではないかと。私たち親ができることは、そんな問いの種を大切に育てることかもしれません。子どもの目がキラキラと輝く瞬間——その瞳に映る未来を、一緒に見つめていきましょうね。子どもの「なぜ?」を育てることが、10年後の社会を変える第一歩かもしれない… 皆さんはどう思われますか?Source: FUTR Launches Closed Beta of AI Agent App Empowering Consumers to Monetize Data, Financial Post, 2025/09/15
