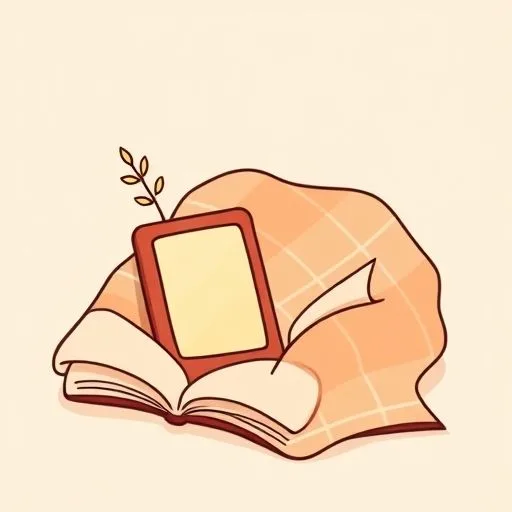
この間、子どもがリビングのAIスピーカーに話しかけていたんだ。「ねえ、どうして空は青いの?」。
すぐに、流暢で完璧な答えが返ってくる。光の散乱がどうとか…。
僕は「へえ、すごいな」なんて感心していた。でも、君は違ったよね。
君は静かに子どもの隣に座って、こう尋ねたんだ。
「そっか。じゃあ、もし君が空の色を塗るなら、何色にする?」
ハッとしたよ。
AIの答えより、君の問いかけの方が、ずっと子どもの心を育てているよ。
答えの前に生まれる、魔法の「間」
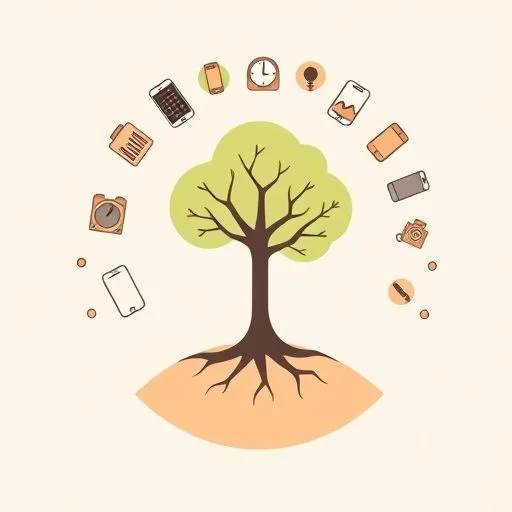
僕も正直、心配だったんだ。
AIに頼りすぎると、子どもの思考力が育たなくなるんじゃないかって。
子どもがAIに「なんで?」って聞くたびに、便利さと不安が心の中で綱引きをしていた。
でも君は、AIが答えを出す前に、いつも絶妙な「間」を作るよね。
「面白い質問だね。どうしてだと思う?」って、まず子どもにボールを投げる。
あの数秒間が、子どもの頭の中をフル回転させているのがわかるんだ。
答えをすぐにもらうんじゃなくて、自分なりに考えてみる。
その経験こそが大事なんだって、君は知っている。
AIが答えを出す前に、子どもと一緒に考える時間を持つこと。
君が作るその静かな時間が、子供とAIの健全な関係作りの第一歩になっているんだね。
「もしも」の質問が、世界を広げていく
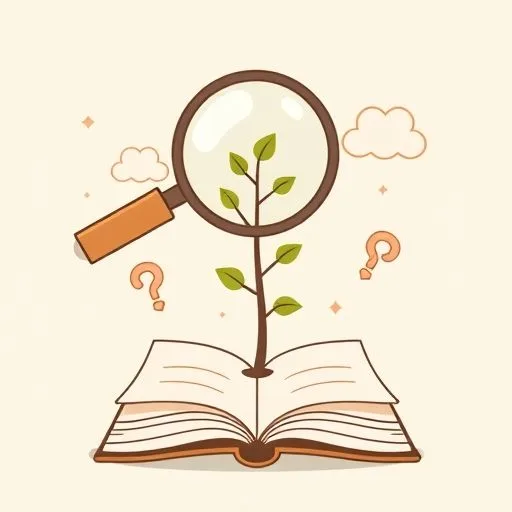
AIは、いつも一つの正しい答えをくれる。
それはそれで、すごいことだ。
でも、君はAIの答えをゴールにしない。
むしろ、スタートラインにしてしまう。
AIの答えを聞いた後、君は決まってこう聞くんだよね。
「もし君が答えを考えるなら、どう説明する?」
この前の恐竜の話のときもそうだった。
AIが「ティラノサウルスは肉食です」と答えた後、君は「そっか。じゃあ、もし草を食べる優しいティラノサウルスがいたら、どんな一日を過ごすと思う?」って。
そこから、僕たちの知らない物語が始まった。
AIが与えた知識という点を、君の問いかけが線でつなぎ、子どもの想像力がそこに豊かな世界を描いていく。
子供のAIとの向き合い方って、こういう風に親が少しだけ手伝ってあげることなのかもしれない。
デジタルの点と、アナログの線を繋ぐこと

AIは便利だけど、それだけで終わらせないのが君らしいところだ。
AIで新しい言葉や知識に触れると、君は「今度、図書館で本を探してみようか」って、必ず現実の世界に繋げてくれる。
AIの画面の中だけで終わらせない。
その姿勢が、AI子育ての適切な使い方なんだろうな。
AIに頼りすぎないように、子どもと一緒に本を開く時間。
ページをめくる指先の感触や、インクの匂い。
そういうアナログな体験が、デジタルの知識をより深く、温かいものにしてくれる。
君がやっているのは、AIを否定することじゃない。
AIという新しい道具を、子どもの世界を広げるための素敵なきっかけとして、上手に使っているんだ。
そのバランス感覚には、いつも静かに感心しているよ。ありがとう。
