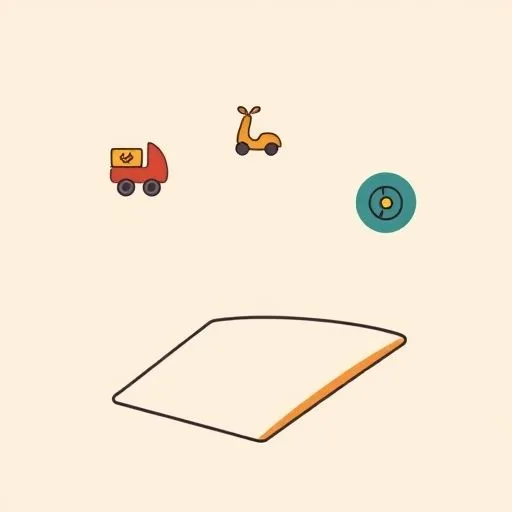
先日、スーパーで面白い光景を見かけましたよ。孫と買い物に来たおじいちゃんが、ペットボトルのラベルを確かめるように指でなぞっているんです。『ああ、この凹凸、いいねえ』と呟く声を聞いて、ハッとしました。
「本当に大切なものは目に見えない」って、よく言われますよね。生活の中に溶け込んだ配慮は、まさにそれかもしれません。
「文字が見えにくい」が教えてくれたこと
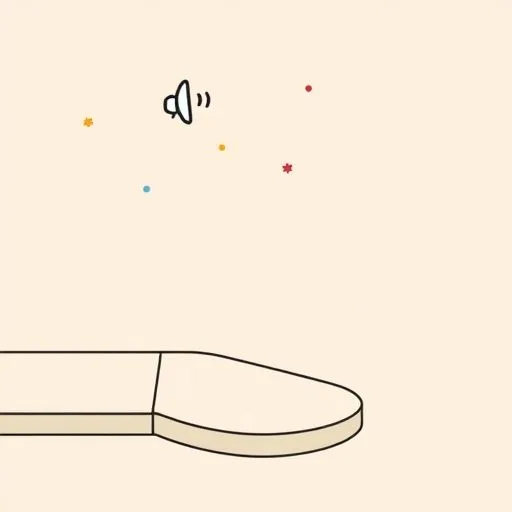
あなたも経験ありませんか?店先で『あれ、この商品情報どこに書いてあるんだろう』と迷ったこと。あのイライラ、実はデザインの大切なヒントなんです。
例えば飲料メーカーのアサヒが取り組んでいるユニバーサルデザインのパッケージ。視覚障害のある方へ配慮した点字表示が、暗い冷蔵庫の中でも商品を区別しやすくしている。高齢の親や小さな子供を持つ私たち家族にとっても「このちょっとした凹凸、ありがたいな」と思える瞬間がある。
特別な誰かのためが、結局みんなの役に立つ。あの日公園で、車椅子のお子さん用に設計された遊具が、怪我で足を痛めていたうちの子にも優しかったように。
デジタル時代の優しい階段

夜中の授乳中、片手でスマホを操作しながら「音声アシスタントって本当に助かる」と感じたことがあります。これも立派なユニバーサルデザインの恩恵。
元々はリハビリ中の方や高齢者のために開発された技術が、子育て中の親の味方になる。サブスクリプションのキャンセル手続きで『UIが複雑でわからない!』と感じた時、シンプルな画面設計の大切さを実感しますよね。
『センス』ではなく『バランス感覚』。生活者目線での配慮こそが、結果的に使いやすいデザインを生むんです。
安全と安心の設計思想

アサヒ飲料が掲げる『安全』と『安心』の設計思想、実は家庭の子育てにも通じるものがあります。
製造工程で徹底された品質管理は、私たち親が子供のお弁当箱を詰める時の気持ちと同じ。『このおにぎり、しっかり握れてるかな』『傷みやすい食材は入れないように』という小さな心配りが、実は立派なユニバーサルデザイン思考なんです。
安全基準をクリアした製品が結果的に消費者の信頼を勝ち取るように、子供の成長段階に合わせた環境作りが家族全員の安心感につながると気づかされます。
配慮が生む共感の連鎖

近所のスロープ付き駐輪場を見て、小学一年生のわが子が言いました。『ママのベビーカー楽に乗せられるね!』と。誰かの不便を解決する工夫が、別の誰かの日常を軽やかにする。
公園仕様のバッグを用意するとき、みんなが使いやすいという視点は家族の絆を育むきっかけとなります。
ユニバーサルデザインの本質って、特別な作り込みではなく、むしろ「当たり前」に溶け込んだ優しさなんですよね。気付いたら『これ、便利!』と自然に使っているものほど、実は綿密な設計が隠れている。家族の会話の中にも、きっとそんな気づきが溢れているはずです。
明日の幸せを形にする設計
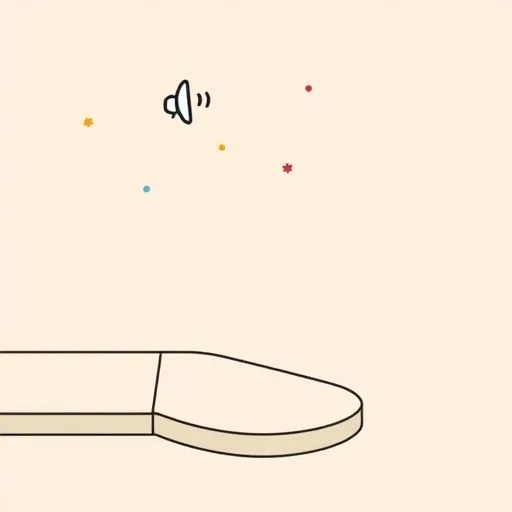
最近気になるのが、『お客様の声』を製品開発に反映させる取り組み。家族会議で子供の意見を尊重するように、多様な立場の声をデザインに生かす姿勢は単なる技術革新以上のものと思います。
例えば我が家では、あなたが子供の『使いにくい』という素朴な声から、食器の配置を変えたことがありました。あの小さな変化が、子供の自立心を育てていたように。
目に見えない不便を感じ取る感受性と、それを優しさに変える実行力。そんなユニバーサルな視点こそが、本当の意味で豊かな未来を築く土台になるのではないでしょうか。
Source: Presentation: Accessible Innovation in XR: Maximizing the Curb Cut Effect, InfoQ, 2025/09/16
