
昨日も子どもの寝かしつけが終わる頃、時計は深夜1時を回っていました。妻がそっとホットココアを差し出しながら、「学校のICT支援員、結局ママ任せじゃない?」とつぶやいたんです。
その言葉に胸がぎゅっとなりました。近所のカフェでママたちの声が頭をよぎりました。「なんでうちの子だけICT授業で取り残されるの…」。
技術より大切だったのは、子どもの目をまっすぐ見て「大丈夫?」と伝える、その一瞬の温もり。
都会に住んでいても、この考えは変わりません。ICT教育だって、子どもの前でスマホを“使えるか”じゃなくて、“使う姿を見せられるか”が大事なんです。
一緒に歩むから怖くない:ICTの“初めの一歩”
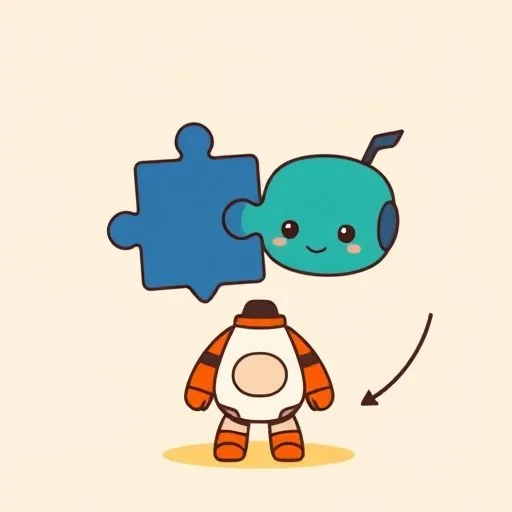
覚えていますか?「ICTって何?」と目を丸くしたお母さんたちが、気がつけばLINEで幼稚園のランチ写真を共有しているんです。
実はね、先週、妻が職場のママ友たちと“スマホで動画撮りっこ会”を始めたんです。みんな緊張しながら録画ボタンを押すママたちの姿を見て、温かい気持ちになりました。
ICTの悩み、実は“1人で解決しなきゃ”という思い込みから生まれてるんじゃないでしょうか?
ある地域の自治体では地域の祖母たちが“孫に見せるYouTube講座”を自主開催。「最初はLINEのスタンプも使えなかったのに、今じゃ孫に『見て!』って送るのよ」って。技術が変わるんじゃなく、共に笑う仲間が増えるから、自然と手が動くんです。
地方移住したママがSNSで出会った先輩ママに「ARで伝統人形を説明するコツ」を教わった話も。ICT子育てのコツ?それは“わからない”を認めて、隣にいる誰かを頼る勇気かもしれません。
小さな実験が育む:「使える」より「楽しむ」を

先日、保育園の先生が衝撃の発言。「プログラミング学習? 100均の積み木でいいんです」。
子どもの発達支援員がゲーム実況のコツを学ぶ姿を見て、本当の学びは“目的なし”から始まるのだと気づかされました。
ICT教育の利点なんて大げさなことじゃなく、子どもの「なんで?」にスマホで答えを探したり、ARアプリで祖父母の郷土話を重ねたりする、そのさりげなさ。
地方の小学校では、保護者が集まって“ロボットおもちゃ修理会”を開催。壊れた学童用ロボットを直しながら、「技術より子どもの好奇心を壊したくない」と語り合う熱さ。
まさにSTEAM教育の本質ですよね。ICT活用格差が問題になっても、子どもが夢中になる瞬間はいつも同じ。“みんなでやってみよう!”と差し出す小さな手。
ICT子育て活用術の一番のキーワードは、子どもの目を輝かせる“遊び心”なんです。
デジタル時代に必要な“温もりのインフラ”

実家の祖母が衝撃のスマホ活用術。孫の誕生日に“AIで作る絵本”をリクエストしたんです!でも、注目すべきは技術じゃありません。
妻が祖母にスマホを教える時、絶対に忘れない“魔法の言葉”があるんです。“いいよ、一緒にやってみよう”。
ICT支援員が不足している現場でも、子どもが困っている隣で静かに寄り添う教師の姿こそ真の解決策。
地元の福祉施設では高齢者が“孫へのLINE愛のメッセージ”を練習する授業が始まったそう。震える指でタイピングしながら「孫に“ありがとう”って送れるようになったの」と涙ぐむおばあちゃん。
地方移住の不安をICTで解決?それより、隣のママが「同じアプリ迷ってます?」と話しかけてくれる偶然の温もりが、心を支えるインフラになる。
ICTって何?答えはここにある。共に試行錯誤する仲間へのやさしさです。
Latest Posts
