
ふと夏の夕暮れに娘の「なんでライオンはマヌケな顔なんですか?」って問いかけが頭に浮かんで。そういえばAI時代に必要なスキルって、このめっちゃおちゃめな問いの広げ方に似てませんか? Accentureの分析では47%のリーダーが人材適応力に不安を感じてる現状。でもね、親子のふざけた日常会話こそが希望の種なのかもしれません。
AI教育の問い方で差がつく?企業が求める人材の特徴
「AIにコントロールされるのではなく、パートナーとして導く技術」——これがキーポイント。実際に、IBMの2025年レポートでも「フレーム設定力」が頭角を現してます。たとえば娘が自由研究で<i>『どうしてアサガオは晴れの日だけ開くの?』</i>って聞いてきた時、『朝露の味が教えてくれるんだよ』とユルく返すことで本人の探求スイッチが入るんです!
いやーメチャクチャ共感なんですけど、このスキルって<u>砂場で遊ぶ時と全く一緒</u>ですよね!最初は単に山を築いただけだったのが、「わ!せせらぎが流れた」と急に会話が深化。AIだって同じで、ルールを守りつつも剛腕にアイディアがぐるぐる拡がるプロセスが必要なんですよ。
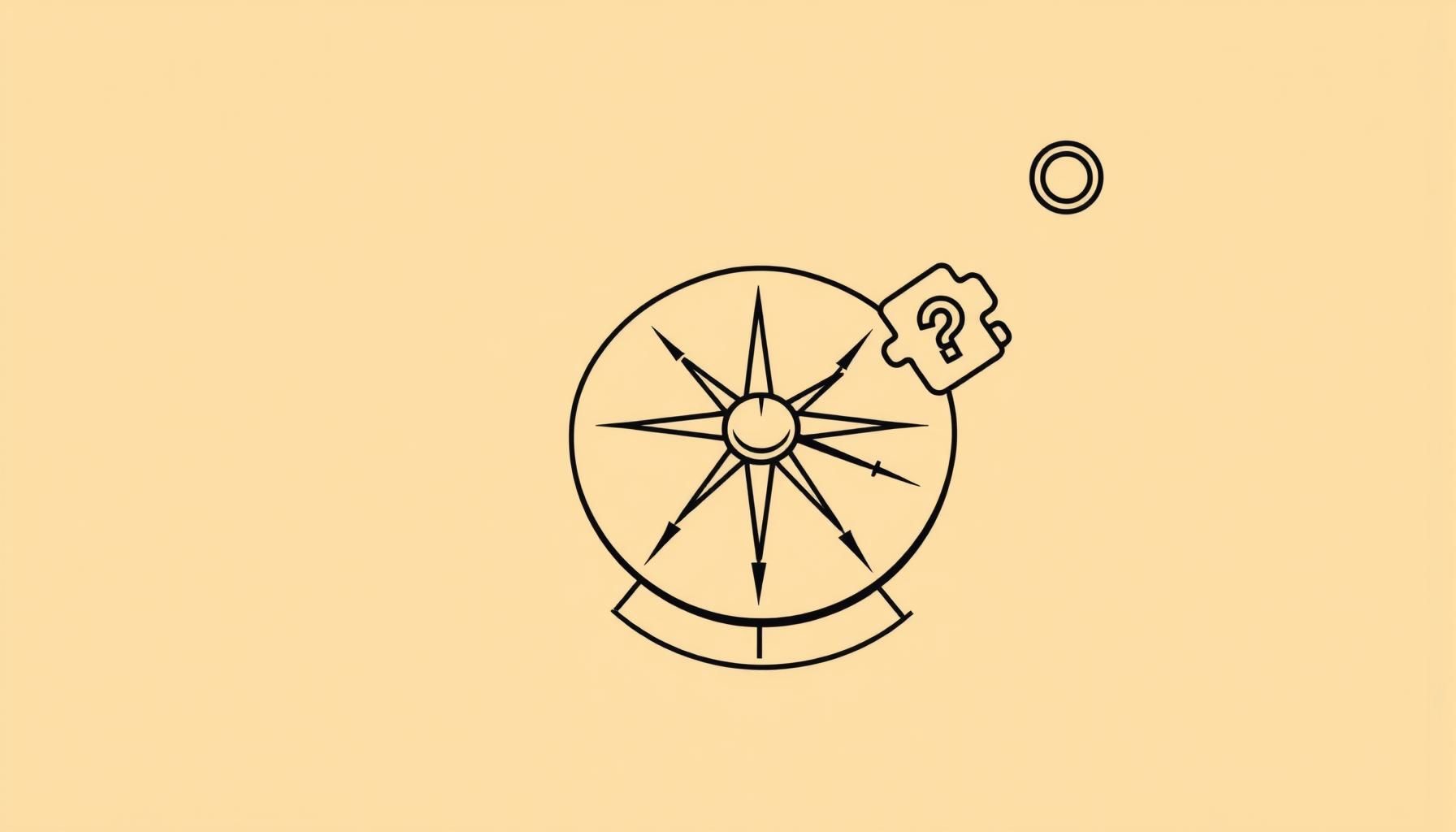
砂遊びでわかるAI適応力|感情を乗せた課題解決法
Sand playが<strong>「問いのダイナミズム」
※適応力に必要なのはこう! パーフェクトさじゃなくて「<em>こんな人はこうしてみてるんです
AIのフレームがしっかりしていても<a href=”https://www.ibm.com/think/insights/ai-skills-you-need-for-2025″ target=”_blank” rel=”noopener”>日常教育でおやつメッセージ型学習が爆発する。例えば朝メシのスープで何度も「<i>味噌のとこにトシが入ってる]</i>って娘が言ってたのが印象的。デジタルとリアルの融合=子どもの勝手な感覚から革新が始まると、しみじみ。
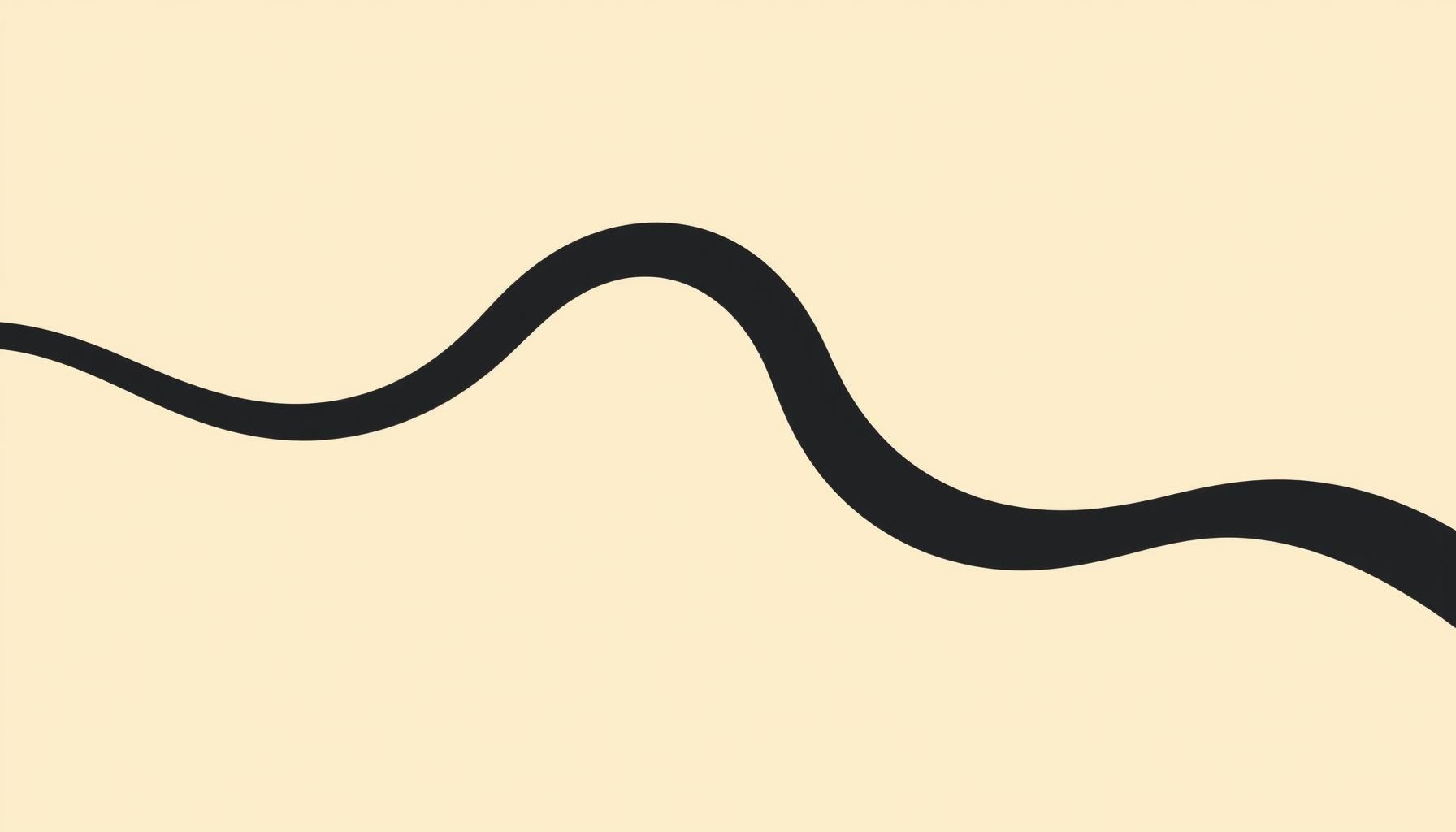
共創が問う未来クエスチョン|AI時代の「らしさ」を見つめて
子どもはもちろん、私たち親もAIとの共創レッスンが必要。実にAccentureではガバナンスあるある企業の成果が2.7倍に!って fileId=E04CD1A6.jpgくってるデータあります。<span class=”important”>重要なのは絶えずに疑問を持ち続けること</span>。娘がリサイクルの針金で迷路作った時なんて、「AIもこんなのデジタルでやってるかもね!」って盛り上がりました。
<small>今日の「問い」ワーク総括</small>: 遊びを通して「自分の興味」と「外部からの刺激」のバランスを見つける。ai実装教育の基本は親子の笑み交じりの日常対話、なんだと思いました~。
——<br>Source: IBM THINK Insights “AI Skills for 2025″(2025/08/15)
<strong>問いから始まるfffファミリーアドベンチャー</strong>
明日のAI時代には「指示」じゃなく「ワクワクする問い」を用いた家族との対話が鍵。例えばこれは<u>娘が考えた『せたがわ君グラフ』</u>だったり、<em>未来枠チャレンジシリーズの一環</em>だったり。いっちょ親子での問い力アップに継続して挑もうかと!
