
子どもたちが寝静まった後、リビングの明かりで気づいた――デジタル機器の輝きよりも眩しかった、あの小さな手の温もり。
夕食の片付けが終わった頃、テレビから流れてきたニュースが心に引っかかりました。『早期デジタル教育が創造性に影響』という見出しに、ふと娘が先週つぶやいた言葉を思い出しました。『この忙しさの中、ついタブレットに頼りすぎてない?』洗濯物をたたむ手が止まったあの瞬間を、今でも鮮明に覚えています。
画面に映る世界と、小さな手の中にある世界
育児情報サイトや教育アプリが溢れる中で、ふと疑問に思うことがありました。最新の知育動画よりも、段ボールを剣に見立てて遊ぶ子どもの目が輝くのはなぜだろう?と。先月、君がリビングにダンボールの城を作り始めた時のことを思い出します。空き箱と色画用紙で作られたそのお城で、子どもたちが繰り広げる冒険ごっこ――デジタル画面にはない、手触りと香りのある物語がそこにありました。
忘れられないのは、『発明タイム』と名付けた君のアイデア。夕食後の30分間だけ、家中の不用品を使って自由に創作する時間。タブレットゲームでは見せない、集中した表情で工作する子どもたちの姿が教えてくれたことがあります。
朝の5分間が教えてくれたこと
ある木曜日の朝の出来事です。君がそっとスマホの電源を切り、子どもたちと向き合う『おはようハグタイム』を始めました。どんなに慌ただしい朝でも、この5分間だけは何にも邪魔されない――最新の育児アプリより、子どもたちの髪の香りや体温の方が、大切なものを教えてくれることに気づいた瞬間でした。
特に印象的だったのは、娘が鼻歌まじりで『パパの腕時計、今日はチクタク音が違うね』と言ったこと。デジタル時計の画面では気づけなかった、機械のささやきに耳を澄ますその姿に、ハッとしました。
テクノロジーとの新しい付き合い方
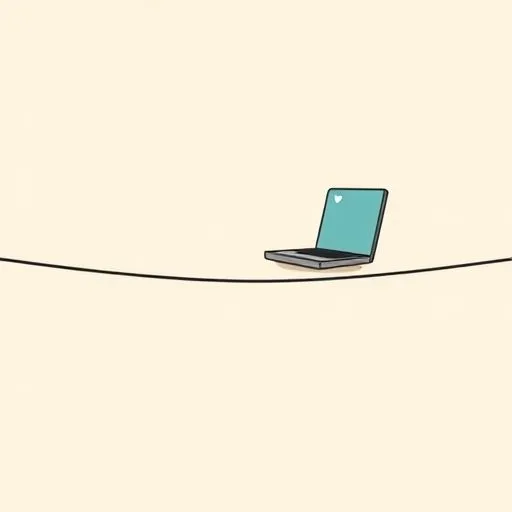
先週の夜更け、娘が宿題を悩んでいる様子と向き合った時のことです。『AIに教えてもらうのはズルかな?』と迷っていた君に、ふと思い出したことがありました。先月参加した勉強会で聞いた『AIは新しい鉛筆のようなもの』という言葉。一緒にタブレットを開き、問題の解き方をヒント形式で調べ始めた時のこと――答えそのものではなく『考え方の道筋』を学ぶツールとしての可能性に気づかされた夜でした。
でも同時に、寝る前に娘がぽつりと言った言葉が忘れられません。『ロボット先生より、パパとママの方が間違えても笑ってくれるから好き』。デジタルツールの便利さと、人間の温もりのバランスの大切さを教えてくれた瞬間でした。
加速する世界の中で守りたい光景
どんなに時代が変わっても、やげり絵本の温もりは特別だね。ページをめくる時の紙の感触、読み手の体温が伝わるあの時間――その中で育まれるものが、きっとあるはずです。
昨夜、子どもの寝顔を見ながら君が言った言葉が今も胸に残っています。確かにそう思います。デジタル絵本の動くイラストも素敵だけれど、その中で育まれるものが、きっとあるはずです。
今朝、急いでいた通勤前のひととき。ふと子どもたちがリビングでやっていたことに目を留めました。タブレットではなく、昨日作った段ボールの城を改造していたのです。ガムテープの切れ端を剣の飾りに変えるその手つきに、未来を生きる力の原型を見た気がしました。
