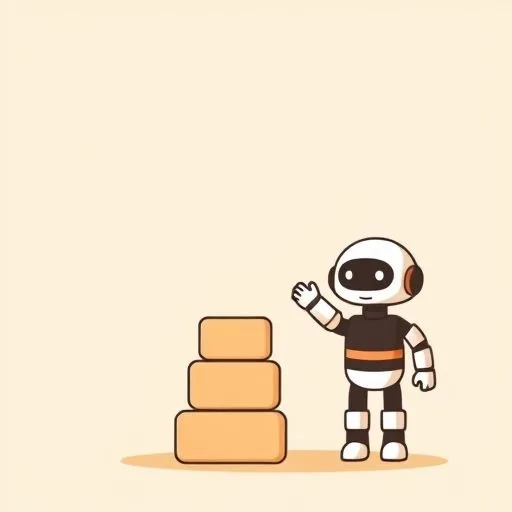
先日、娘が学校から持ち帰った工作を見て、ふと考えました。彼女が一生懸命に色を塗ったその作品には、どこか温かみがあって、たとえ形が少し歪んでいても、そこには確かな『何か』が込められていました。そして最近よく耳にする『ワークスラップ』——見かけは立派だけど中身のない仕事——という現象が頭をよぎりました。私たち大人の世界でも、同じようなことが起きているのではないでしょうか?テクノロジーが進化するほど、なぜか失われていく大切なものについて、今日は熱く語りたいと思います。
AIワークスラップが子供の創造性に与える影響は?

娘が描いた絵を見て「すごいね!」と褒める時、私たちは単なる技術的な完成度ではなく、彼女がその作品に込めた想いや努力を認めています。ところがAIが生成するコンテンツには、この『込められた想い』が決定的に欠けているように感じます。
なんか、キラキラした包装紙で包まれた空っぽの箱みたいだなって思っちゃうんです
子育てにおいても、私たちは時々『見かけだけの関わり』に陥ることがあります。スマートフォンを見ながらの「うんうん」という相づちや、ながら作業の読み聞かせ…。でも子どもたちは敏感です。彼らは本物の関わりと表面的な関わりの違いを、直感的に感じ取っています。
先日の夕食時、キムチチゲを囲みながら娘が突然こう聞いてきました。「パパ、AIって何でも知ってるの?」。その瞬間、フォークを置いて本気で向き合いました。「AIは情報を教えてくれるけどね、お姫様のドレスの色を決めるのはAIじゃなくて○○ちゃんの想像力だよ」
AI使用が創造性を奪うメカニズムとは?
驚くべきデータがあります。どこかで読んだのですが、AIツールを使うと作業に約20%も時間がかかるようになるそう!でも本人たちは効率化したと錯覚するらしいんですよ。
我が家では、娘が何かを作りたいと言った時、すぐに答えや完成形を示すのではなく、「どうやって作ろうか?」「どんな材料がいるかな?」と問いかけるようにしています。時には失敗することも、遠回りすることもあります。でもそのプロセスこそが、本当の学びと創造性を育むのではないでしょうか?
家族の生産性をどう再定義するべきか?

ある調査では、大企業で年間数百万ドルもの生産性損失が発生していると言われています。しかし、家族の『生産性』を数字で測れるでしょうか?
夕食時の会話の質、一緒に過ごす時間の濃密さ、子どもたちの笑顔の数——これ、数字にはできないけど、本当に、本当に、かけがえのない宝物だと思いませんか?
子どもたちの未来に必要なAIリテラシーとは?

娘が成長する世界は、さらにAIが浸透した社会になるでしょう。だからこそ、私たち親世代がすべきことは、単にツールの使い方を教えることではなく、『技術と人間らしさのバランス』を実践して見せることではないでしょうか。
我が家では、時々『AIなしデー』を設けています。その日はすべてのことを自分の頭と手でやってみる。たとえ非効率でも、そこから生まれる発見や失敗の経験が、子どもたちの創造性を育む糧になると信じています。
家庭で実践できるAIとの健全な関係構築法
結局のところ、AIとの付き合い方も子育てと同じで、バランスがすべてです。完全に遠ざけるのでも、依存するのでもなく、適度な距離感で付き合っていく。
子どもたちとAIについて話し合う時、私はいつもこう伝えています:「AIは便利な道具だけど、君たちの想像力には敵わないよ」。だって本当にそうでしょう?AIが生成できるのは過去のデータの組み合わせだけど、子どもたちの創造性は無限大ですから。
出典: Is AI-generated ‘workslop’ to blame for a lack of productivity gains?, Fortune, 2025-09-23
