
夕食の準備をしている時でした。テーブルにスマホを置いていたら、子供の手が届く距離になっていたので、「30分だけね」って声をかけた。その目に映るのは、子供の成長を嬉しく思いつつも、少しずつ離れていってしまう寂しさや不安が交じる複雑な気持ちだ。親なら誰もが通る道です。スマホに夢中になる子供の横顔を見つめながら、ふと感じるのは、デジタル機器が与えてくれた新たな家族の絆の作り方かもしれません。
ゲームの画面から見える親の学び

子供が夢中に画面を操作している姿を見ると、どうしても心配になってしまいます。でも、その体験を共有してみませんか?
ある時、僕が子供の隣に座り、「どうしてこれが好きなの?」と尋ねた場面がありました。すると、子供が驚くほど熱心に、ゲームのストーリーや世界観を説明し始めたのです。
親が知るべきは、ゲームの内容ではなく、ゲームの世界に何を感じるか。その時間を、子供の成長を感じる小さなきっかけに変えてみる。
そんな視点の変化が、親子の関係を深めるきっかけとなるかもしれません。
思春期の子供と向き合う、静かなる親の強さ

「最近、全然言うことを聞いてくれない」それは、ある意味、子供が自立した証拠。親が気づかないうちに、子供は自分の世界を築きつつあります。
その変化に気づいた時、僕がとった行動は意外でした。無理に話を聞こうとするのではなく、子供の好きなアプリやゲームを少しだけ調べてみる。
そんな小さな努力が、会話のきっかけを作る。朝の準備時間に、スマホの使い方ルールについて話しかけて、自然に会話を始める。
その方法は、まるで季節の変化のように、ゆっくりと子供の成長に合わせて変化していくのです。
2025年へ向けた、家族のルール作り
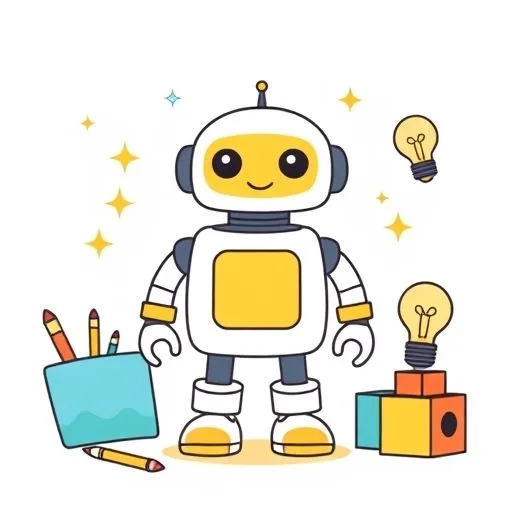
デジタルデバイスとの付き合い方には、家族ごとの答えがあります。私たちが大切にしているのは、「ルールを一緒に作る」ということ。
その夜、僕が机の前に並べたのは、スマホの利用時間を記録した紙。子供の提案を元に、ルールを決めるそのプロセス自体が、家族の絆を作る。
例えば、ゲーム時間の代わりに家族で一緒に料理する時間を増やす。その取り組みが、子供の自立心を育むきっかけにもなります。
デジタル時代のルール作りは、親子で共に成長するための、新しいチャレンジ。その過程こそが、未来の家族の強さを培う土台となるのではないでしょうか?
源: 総務省「小中学生のスマホ利用率> 3%」調査(2025)を参考に。
