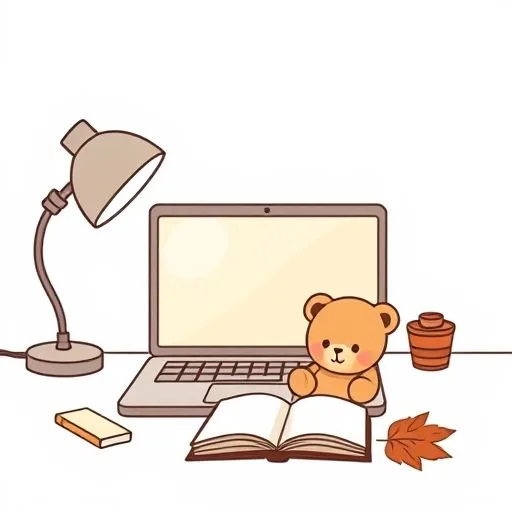
夜、子どもたちが寝静まった後、テーブルを整えながら。横に座って麦茶を飲みながら、今日も子どもたちが夢中になってゲームをしている姿を見守っていました。あの夢中になる瞳の輝きと、その横で時々感じるちょっとした不安。この両方の気持ちを、私たちは親として、よく知っています。ゲームの世界が広がる時、親子の絆も一緒に育んでいける方法について考えてみませんか。
「制限する」ではなく「整える」発想

子どもたちがゲームの世界に没頭する時、その姿を見て「このままで大丈夫なのか?」と不安になることがありますよね。実は、ゲームの時間管理は「制限」だけの考え方ではうまくいかないことも。
私たちが試してみて良かったのは、ゲームの時間を「創造性の時間」として整えること。例えば、週末に家族で一緒にゲームを楽しむことで、新しい発見が生まれることがあります。ゲームの中で出会う問題を親子で解決する時、子どもの考える力が育っているのが感じられます。そんな時、私たちは、ゲームの力を「治療ツール」としても活用できることがあると感じるのです。
子どもの特性と向き合うヒント

子どもたちが発達特性を抱えている場合、特にゲームの世界との関わり方が悩みどころになることがあります。ある時、あるご家庭でお母さんが「ゲームの世界が、発達特性を持つ子どもとのコミュニケーションのきっかけになった」と話す姿を聞き、心に響くものがありました。
ゲームの世界を否定する前に、そのゲームがなぜ子どもに楽しいのかを一緒に理解する。そんな関わり方から、子どもたちの適切な距離感を探す航路が開けていく。私たちは、子どもたちのゲームの楽しみ方を、家族で共有する大切な時間に変われたんです。
明日への希望リストを作る
ゲームの時間管理は、単なるスクリーンタイムの制限ではなく、子どもたちの世界を広げるための時間。
「ゲームの時間管理」について、家族で話し合う時間を作ってみませんか?私たちは、ある日の夜、子どもたちと一緒に「ゲームの価値基準」を話し合う機会をもちました。それは、単なるルール決めの時間ではなく、子どもたちの未来へ向けた「希望リスト」の時間。
その中で、子どもたちが「ゲームの知識を学びに活かしたい」と話す姿に驚かされました。ゲームの世界を切り口に、子どもの興味や可能性を育てていく。そのような親子の関わりの時間は、ゲームの時間を「創造性を育む時間」に変える第一歩になるのです。
一緒に楽しむ習慣が生む安心感

子どもたちがゲームの世界に没頭する時、私たちは時に「ゲームの世界が広がりすぎて、ちゃんと向き合えるかしら?」と不安に感じることがあるかもしれません。そんな時、私たちは、ゲームの話題を一緒に楽しむ習慣を大切にしています。
例えば、子どもたちがゲームの中で達成したことや、面白い発見を共有する。たったそれだけのことが、子どものゲーム時間を「安心感」のある時間に変える。ゲームの世界を楽しむ習慣を守ることで、どんな未来にも怖くない親子の絆が育っていく。私たちは、そう信じるようになりました。
デジタルとアナログの探検者
子どもたちは、ゲームの世界と現実世界を行き来する探検者。ある時、ゲームのアイデアを活かして、家族で一緒に自然の中を探検する日を過ごしたことがあります。その時感じたのは、ゲームの世界が子どもたちの探検心を育てていることのリアル。ゲームの時間管理は、単なるスクリーンタイムの制限ではなく、子どもたちの世界を広げるための時間。そんな時、子どもたちの成長を支える「航路の開拓者」としての親としての役目に気づかされます。デジタルとアナログ、両方の世界をバランスよく育むことが、私たちの大切な役割なのです。
