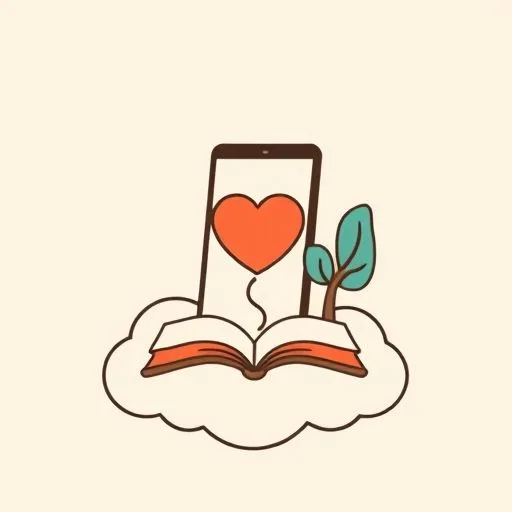
子供のランドセルが重いほど、「日本の教育格差」が透けて見える
子供が寝静まった後、リビングのテーブルに広がる塾のプリントの山を見て、ふと数えました。この1週間のうち、家族と一緒に夕食を取れたのは何日だったでしょう。
最近の「お母さん、お腹が空いたよ」という言葉は、いつも19時半を過ぎてから。他の家庭の子どもたちは、どんな時間を過ごしているのだろう…そう考える瞬間、あなたもきっと気づいてしまうんですよね。教育格差は、私たちが思っているよりずっと身近な問題だということを。
「学力の差」はお財布の中身の差?
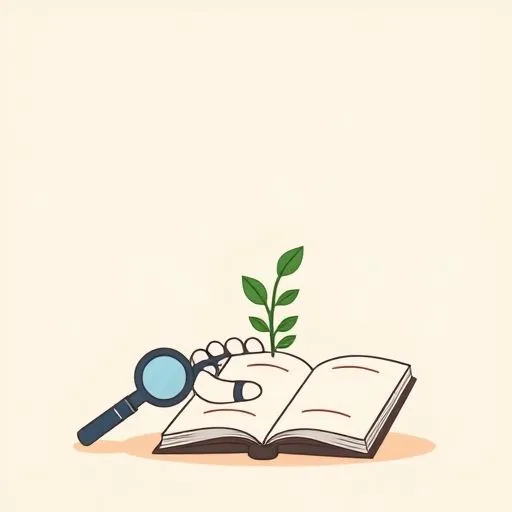
塾の送り迎えをする時、車の窓から見える他の家庭の車をふと見てしまいますよね。『あの車は、うちの倍くらいの授業料を払っているんだろうか…』
OECDのデータでは、日本の公的教育費支出はGDP比で先進国で最低レベル。でも、教育費の私的負担率は13.5%と、アメリカやフランスに並ぶ高い数字です。
この数字、今のあなたにとってはどんな感じがしますか。塾の通い始めを決めたあの時、『子供のためには』と、自分が小学校の時にはなかった選択肢を選ばざるを得なかった。そんな気持ち、よくわかります。
「低学年から塾通い」のナゾの弊害

「小さいうちから勉強させておけば安心」という考えが、実は子供の成長を阻害するケースがあります。小学3年生のAさん(仮名)は、週3回塾に通う中で『算数が嫌い』になりました。
原因は、塾のカリキュラムが学校の進度を半年早くしているため、ついていけなくなる。そして、その子供の親は、『塾の費用が高いのに効果が出ないなら、塾を増やさなければ…』と考える。
このような状況が、まさに教育格差の拡大を生み出す、見えないループなのです。幼少期の過度な学習が、将来の「学ぶ意欲」を喪失させる可能性があると指摘されていました。
「学びの時間」を変える家族の習慣
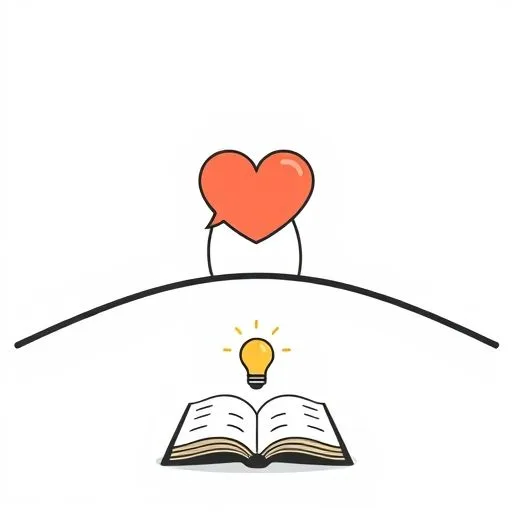
「勉強しなさい!」と言いたくなるのは、親として普通のこと。でも、ある母親が「毎日、20分の物語りタイム」を始めたところ、子どもの国語の成績が劇的に上がりました。
決め手は、単純な「勉強」ではなく、一緒に考える時間でした。たとえば、こんな質問がいいでしょう。「おばあちゃんの家に行く道中、土の色や感触の違いに気づいたらどうなる?」(地理の話)「昔のこの話を、今の生活に応用するとどうなる?」(歴史の考察)などなど。
家庭学習のサポートは、お金の多さではなく、質が問われるのです。子供の成長を、親が一緒に歩く準備が大切だということを、私たちは教えてくれます。
もう少し、こんな風に意識してみてはいかがでしょうか。この「学びの時間」は、まさに、お金を払わないとできない、きっと、教育格差を埋める一つの力になるはずです。
「教育の断捨離」でできること

ある塾講師が言うように、『何を捨てるかが、子どもの学力を伸ばす鍵』。家の本棚を整理した時、子供の成長に合わない教材を処分した経験はありませんか?
教育の断捨離とは、子供が「本当に必要とするもの」だけを選ぶこと。最近、我が家の小学3年生が、『この問題を解く必要ある?』と聞いてきたことがあります。
その時ほど、親として、子どもの学習の質を深く考えることになりました。成績が上がらない原因は、『学んでいない』からではなく、『学びすぎる』ことで子供の成長が阻害されている可能性があります。
教育の断捨離の第一歩は、子供の「学びの時間」を整理することから始まります。あなたの、そうした、小さな気づきが、子供の未来をより豊かにしていくことでしょう。
Source: OECD「子どもの学びと人間発達に関する調査報告」2023
