
ある晩のことです。リビングでタブレットを見つめる子どもの横顔が、ふと懐中電灯の光に浮かび上がりました。画面に吸い込まれるようなその瞳を見て、ハッとしたんです。私たち親子の日常に、いつの間にか深く入り込んできたデジタル機器。便利な道具であるはずが、時に子どもの世界を狭めてはいないか――そんな思いが胸をよぎりました。
スクリーンタイム通知と子育ての温度差
『1日4時間使用』という通知を見て、はたと手が止まった経験、ありますよね。数字は淡々と事実を伝えますが、そこに子どもの創造性や好奇心は映らない。先週、隣で妻がタブレットの利用制限を設定しながら呟きました。「この設定、本当に子どものためになってるのかな」と。
機械的に時間制限するだけでは、子どものデジタルとの関わり方は育たない――そう気付かされた瞬間でした。
AI育児支援ツールも同じかもしれません。便利な機能が増えるほど、逆に私たちの育児感度を鈍らせてはいないだろうか。ある日の夕飯時、子どもが突然「今日、アプリの先生が褒めてくれたよ」と話し出した時の妻の表情が忘れられません。喜んでいるようで、どこか複雑なその表情から、デジタルツールと私たち親子の関係性を改めて考えさせられました。
アナログとデジタルを行き来する子育て

子どもが動画に夢中になる姿を見ると、つい「やめなさい」と言いたくなりますよね。でもよく見ると、その動画の後に折り紙を広げて真似をしているではありませんか。デジタルツールがきっかけで広がる子どもの世界もあります。
先月、妻が面白い試みをしていました。YouTubeの工作動画を一緒に見た後、実際の材料を準備して挑戦するんです。「画面の中の楽しさを、実際に手で感じてほしい」という言葉が印象的でした。
スマホ育児に罪悪感を感じる保護者の方は多いと思います。でも考えてみてください。昔の親だって、忙しい時には絵本を渡して“時間稼ぎ”をしたでしょう? タブレットも同じ“道具”の一つ。
肝心なのは、使いっぱなしにしないこと。食事中は家族の会話タイムと決め、デバイスは別室に置く――そんな小さなルール作りから始めてみるのはいかがでしょうか。
AI時代を生きる子どものためのリテラシー
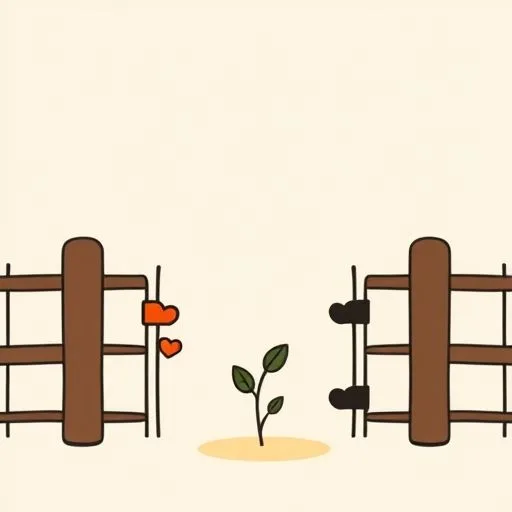
先日、小学生の姪っ子が「ChatGPT先生に算数教えてもらった」と話していました。AIが身近な存在になるこれからの時代、禁止するよりも正しい付き合い方を教えることが大切かもしれません。
妻が最近始めた習慣は、検索結果を鵜呑みにせず『この情報、本当かな?』と子どもと一緒に考えることです。デジタルリテラシーの種まきは、日常のちょっとした会話から始まるのだと気付かされました。
とはいえ、完全な答えなどありませんよね。私たち保護者も試行錯誤しながら、その時々にできる最善の選択をしているだけ。大切なのは、テクノロジーに子育てを“任せきり”にしない姿勢かもしれません。
深夜、子どもの睡眠データを見ながら妻が呟いた言葉が胸に残っています。「このグラフより、抱っこの時の鼓動の方が正確かもね」と。
デジタル漬けを心配する前に、まず私たち親自身がスマホから目を離してみませんか。子どものデジタル習慣は、実は私たちの生活を映す鏡なのですから。
画面の向こうにある本物の笑顔を見逃さないよう――今日も子どもたちのデジタルとアナログの境界線を、そっと見守りたいと思います。
出典: Forbes(2025年10月1日)「Firewalls Are Old-School: AI Needs New Approaches」
