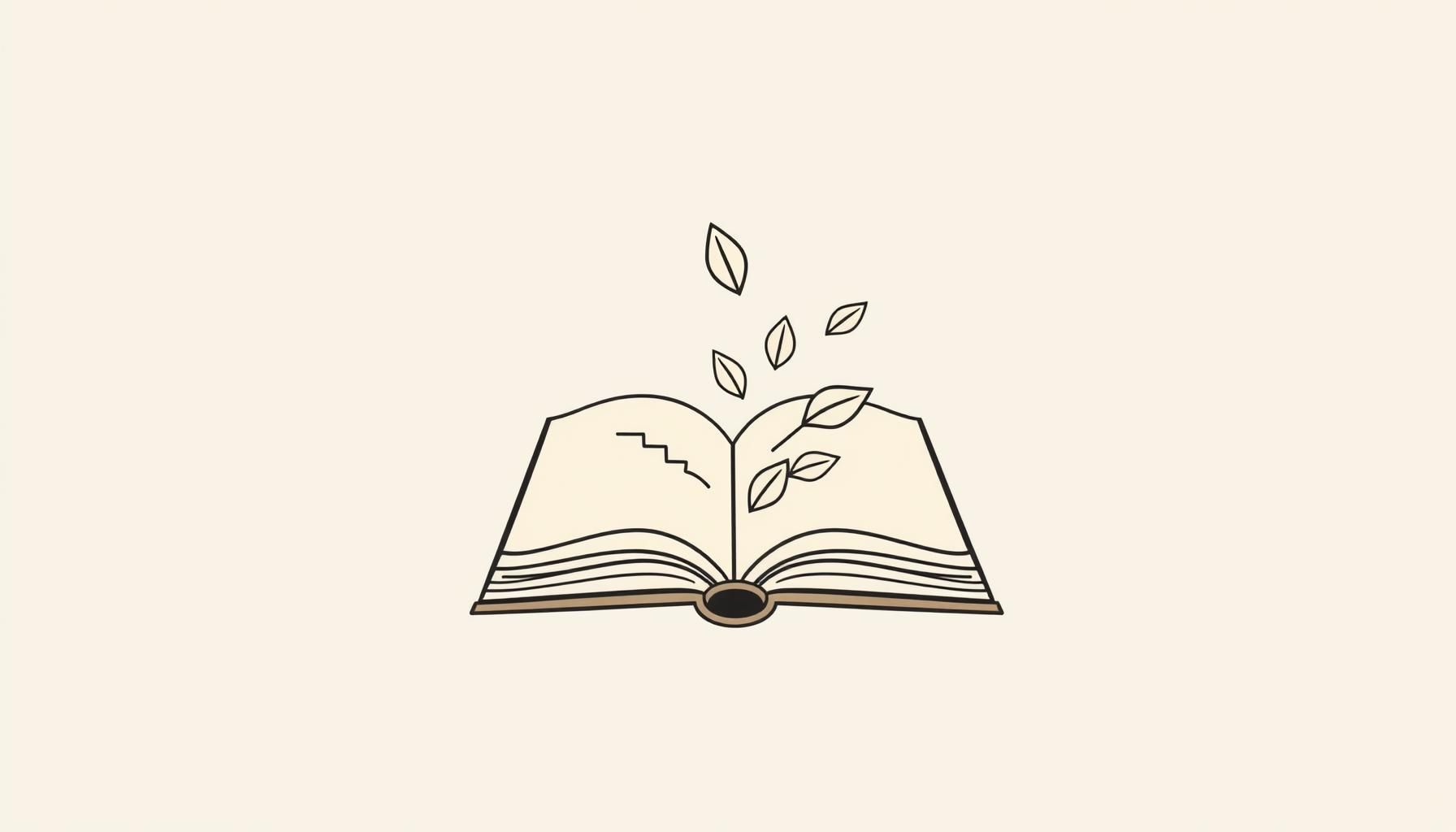
朝の通学路で娘が突然立ち止まり、スマートフォンで桜の絵を描き始めたあの日のこと。2025年春、1年生になったばかりの子がAIアプリで共同制作する姿を見て、技術と子育ての関係がじわじわと変わっていく実感が湧きました。Ayumi Moore Aokiさんの言葉にハッとさせられたのは、きっとこの日常の光景と重なったからなんでしょうね。
管理するってこと、結局は信頼の育て方
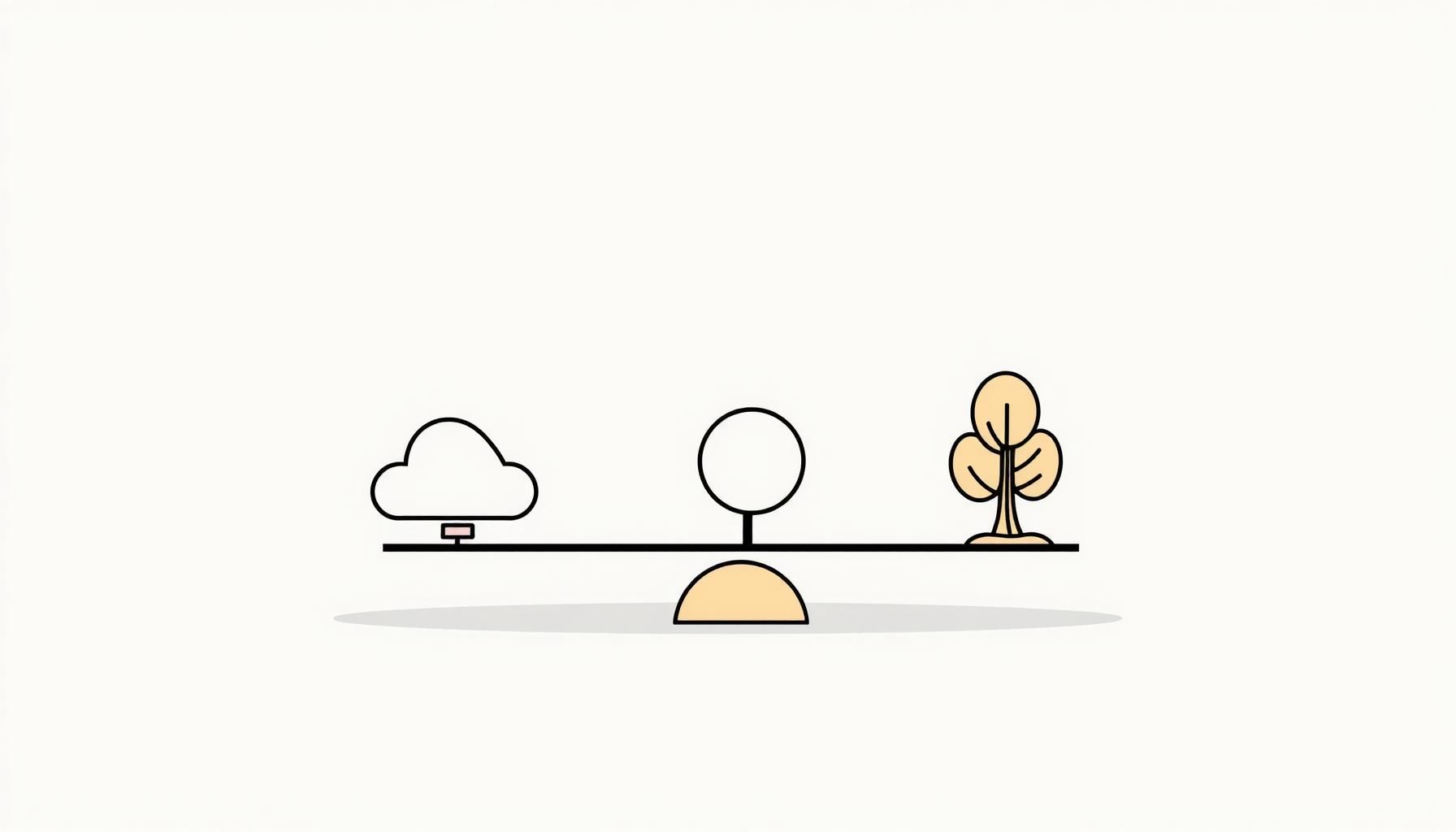
AIエージェントを任せるときも、我が家で娘にスマートアプリを使うときも、同じようにドキドキしますよね?Forbesで紹介されたAyumi Moore Aokiさんの指摘がまさにその心の内を言い当ててる気がしました。
技術をただ放任するのではなく、ルール作りを一緒に考える時間が意外と重要だって気づかされました。まるで韓国流のキムチスープをだしで煮るように、伝統も革新も混ぜ合わせながら、自分たちらしいバランスを探ってる感じ。AIと向き合うのって、案外家庭の文化のバランス感そのものなんですよね。
本当にバランスが大事だって実感するよね?さじ加減ひとつで、会話の温度が変わるっていうか
上記の視点に関連する我が家でのエピソードをご紹介すると、娘が教育アプリで工作のアイデアを探すときの話です。通学途中の桜の木を見て「AIで似た絵描けるかな?」と言い出し、一緒に桜のデータを入力。ただ見守るんじゃなくて、「次はおばあちゃんの手紙をAIで昔話ゲームにする?」と3世代で遊べるアイデアに発展させたんです。
共創造で育む、子どもの未来スキル

もちろん、アレよね…AIツールってつい一人で没頭しちゃうもの。でも
AIとどう向き合うか、悩み中のパパママさんも多いですよね?我が家では「週末は家族AIゲームデー」を設けて、アプリでみんなの思い出を物語にする遊びを始めました。最初は娘が一人でこっそり操作してたけど、「お父さんはこれが正解」じゃなくて「一緒に変えてみよう」って伝えると、目がキラッと光った瞬間が今でも忘れられません。
その時感じたのは、ほんとね、バランス感覚が大切なんだなってこと。技術も教育も、「絶対このルール」より「今だけはこの方法」って柔軟に変えられる姿勢が、子どもから信頼されるポイントなんですよね。何百回失敗しても、最後に達成感を共有できたときの笑顔が、親として学ぶことが多いなぁって実感させてくれます。
AI枠?アナログ枠?それとも共に存在する新しい第三の選択?
Source: AI Agents Are Joining Your Team. Are You Ready To Manage Them?, Forbes, 2025-08-14
先日、保育園の先生が呟いてた言葉がずっと頭に残ってます。「子どもは未来の旅人」って。確かに技術も育児も目的地より道中が大事。AIを怖がるんじゃなく、今日の通学路で一緒に笑えたことが、何十年も先の強さになるんですよね。
