
最近、7歳になる娘が本当にびっくりするほど夢中になって描いた絵を見せに来てくれました!線は少しガタガタで、色使いも大胆不敵!でも、その一枚には彼女が見た夢や、公園で感じたワクワクが、これでもかというくらい詰まっていて、思わず目を丸くしてしまいました(笑)。完璧じゃない、でも、そこにしかない「魂」がある。そんなふうに娘の絵を見ていたら、トム・ムーアという高校教師の「AIは人続け性に取って代わることはできない」という言葉が、ドキッと胸を打たれるんです!本当に!娘の絵、うちでは「ハングルで名前を書き添えよう!」って家族のルールになっているんです。彼が言うように、AIが生成するものは、まるで本物のブドウの代わりに、安物のジェリービーンズを渡されるようなものかもしれません。見た目はカラフルでも、本物の果実が持つ深みや瑞々しさがない。こんなこと、私たちの仕事や学びの場でも、すごく大事な視点だと思いませんか?ジェリービーンズとブドウの違い、忘れちゃいけませんよね!
蛍光灯の部屋と、太陽の光:AIが生み出す「平坦な」世界とは?

スタンフォード大学のジェーン・リスキン教授は、AIが生成したエッセイを「平坦で、特徴がなく…文学における蛍光灯のようだ」と表現しています。うわー、これ、めちゃくちゃ分かりやすい!って思わず叫んじゃいました!正直なところ、この表現には少し驚きました。学生が一生懸命書いた文章を読むことは、まるで「人間の思考と表現という太陽の光を浴びる」ような体験だ、と。そこに込められた悩みや喜び、発見のきらめきが、読む人の心を温めてくれるんですよね。ところが、AIが作った文章は、窓のない蛍光灯だけの部屋で、ただ黙々と作業をしているような感覚に近いのかもしれません。効率は良いかもしれないけれど、心が躍るような感動は、そこにはない。こんな体験、ありませんか?
ある研究では、AIとの対話が繰り返されることで、その無機質さから感情的なつながりが失われ、創造的な思考が制約されてしまう可能性が指摘されています(PMC)。正直なところ、この結果にはちょっと驚きました。まるで、決められたレールの上を走るだけの列車みたいに。でも、人間の創造性って、もっと自由で、道なき道を行く冒険のはず!この「人間ならではの温かみ」を、私たちはどう守っていけばいいんでしょうか。それは、ただ感傷に浸ることではなく、未来の働き方や学び方を考える上で、めちゃくちゃ重要な鍵になるはずです!
最高の相棒?それとも思考の松葉杖?AIとの絶妙な距離感の取り方
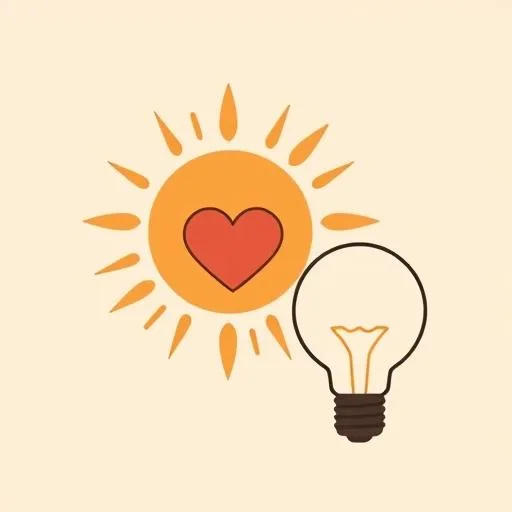
じゃあ、AIは創造性の敵なのか?というと、話はそんなに単純じゃないのが面白いところ!ある大学の研究で、学生たちに「ペーパークリップの使い道をできるだけ多く考えて」という課題が出されました。最初は自分の頭だけで、一ヶ月後にはChatGPTを使って。するとどうでしょう!AIを使った方が、より多くのアイデアが出たというんです。えっ、ほんとに?!正直なところ、この結果にはまさか驚きました!なるほど、AIはアイデア出しの「壁打ち相手」としては、最高の相棒になってくれる可能性があるんですね!(サウスカロライナ大学の研究)
でも、ここからが重要!その研究では、同時にいくつかの懸念も浮かび上がりました。学生たちの中から、「AIに頼りすぎると、自分の頭で考える力が弱まって、自信まで失ってしまうかも」という声が上がったんです。さらに、AIが生み出すアイデアは、個々で見ると良くても、全体で見ると似たり寄ったりになる傾向があったとか。つまり、AIはたくさんの「正解っぽい」答えを素早く見つけてくれるけれど、誰も思いつかなかったような、突拍子もない「ユニークな大発見」は苦手なのかもしれません。このAIの限界こそが、私たち人間が本当に光を放てる場所なのかもしれませんね!
これは、まるで旅の計画を立てるのに似ています!便利なツールが最適なルートを教えてくれても、あえて裏道に入ってみたり、予定外のカフェに立ち寄ったりするからこそ、忘れられない思い出ができる。私がカナダと韓国のハイブリッドな文化の中で育った経験から言うと、計画通りにならない旅ほど、思い出が深いものですよ!AIは素晴らしい地図やガイドブックですが、旅の主役は、あくまで私たち自身。そのことを忘れちゃいけないんですよね!
さあ、創造性の筋トレを始めよう!AI時代を乗りこなす3つのヒント

AIというパワフルな道具を前に、私たちの「創造性の筋肉」が衰えてしまうのは、もったいなさすぎる!ええっ、そんなことないですか?!じゃあ、どうすればいいのか?僕なりに考えた、今日からできる「創造性の筋トレ」を3つ提案させてください!
- AIを「解決策の提供者」ではなく「共同作業者」と位置づける!
AIに答えを丸投げするんじゃなくて、「君ならどう考える?」って問いかける壁打ち相手にしちゃうんです。AIが出した答えに対して、「本当?」「もっと面白い考え方はない?」と、あえて反論してみる。そうやって対話することで、自分の思考がどんどん深まっていくはずです。これは、ビジネススクールでも提唱されている考え方で、AIを思考の起爆剤にするんです!(AACSB)うちの娘にも「この絵、AIはどう思う?」って聞いてみたことがありますよ!なんて笑えるんでしょう! - 「面倒くさいプロセス」を愛する!
効率化は素晴らしいことですが、創造性はしばしば非効率で面倒なプロセスから生まれます。僕の体験談なんですが、娘が粘土で何かを作るとき、部屋中が大変なことになります(笑)、その試行錯誤の中でこそ、彼女だけの傑作が生まれるんです。ブレインストーミングで付箋を壁に貼りまくったり、何度も書き直したり。その「無駄」に見える時間こそが、思考を熟成させ、ユニークなアイデアを育む最高の肥料になるんです。韓国の伝統的な「間」という美意識にも通じるところがありますよね! - 自分だけの「ブドウ」を育てる畑を持つ!
AIが学習するのは、過去の膨大なデータ。つまり、まだ誰も経験していない「未来」や、あなただけの「個人的な体験」は、AIには生み出せません。だからこそ、散歩中に見つけた面白い形の雲とか、友達との何気ない会話で感じたこととか、そういう自分だけの体験の引き出しをたくさん持つことが、ものすごく大事!正直なところ、特にカナダと韓国のハーフ文化の中で育った僕の娘は、この独自の体験が宝物です!それが、AIには真似できない、あなただけの「ブドウ」になるんです。日記を書いたり、写真を撮ったり、とにかく五感で世界を感じることが、最高のインプットになります。
未来への希望を込めて:私たちの手で、より豊かな世界を築くには?
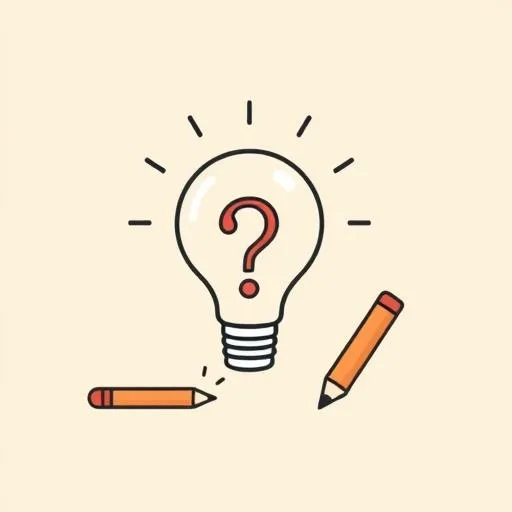
AIの登場で、私たちは「人間らしさとは何か?」を、改めて問われている気がします。それは、効率や正解を出す能力ではなく、不完全さの中からユニークな価値を生み出す力、共感し、物語を紡ぐ力なのかもしれません。ある研究が示すように、AIの導入は慎重なアプローチが求められます。創造性をサポートする可能性がある一方で、自信を損なうリスクもはらんでいます。(ScienceDirect)この問題から目を背けることはできませんよね!
だからこそ、私たちは賢い使い手になる必要がある!AIを便利な道具として使いこなしつつも、それに魂を乗っ取られないように。私たちの仕事や学びが、味気ないジェリービーンズで満たされるのではなく、一つひとつ形や味が違う、生命力あふれるブドウの実で豊かになるように。それは、私たち一人ひとりの心がけにかかっています。韓国の「기름지다(豊か)」という言葉のように、私たちの創造性も豊かで多様でなくてはならないんですよね!
完璧じゃない絵ほど、心に響くものってありますよね。私が子供の頃、描いた不格好な絵を見てくれた母の笑顔は、今でも忘れられません。娘が描いた、ちょっと不格好だけどエネルギーに満ちた絵のように。私たちも、自分だけのユニークな線を描き続けていきたいですね。その不器用さこそが、きっと誰かの心を動かす、かけがえのない輝きになるはずだから。未来は、私たちの手の中にあります。では、あなたの「ユニークなブドウ」を育てるために、今日からできることは何でしょう?さあ、一緒に、希望を持って、この新しい時代を冒険していきましょう!
Source: Jelly Beans for Grapes: How AI Can Erode Students’ Creativity, EdSurge, 2025/09/08
