
この涼しさが心地よい朝、娘を学校へ送り出した後で、ふと窓の外を眺めていました。曇り空が広がる仁川の朝、父親として胸をかきむしるのは、やっぱり…AIの進歩が速すぎて、それに伴う安全面での課題が追いついていないこと。ニュースで見た「CISOが語るAI混乱」って、なんだか変な感覚で、自分の育児にも重なってくるんです。だって今の子供たちの教室にもAIが入り込んでいる時代。どうしたら「安心」と「冒険」のバランスが取れるの?
AI時代の情報教育:小さな冒険から始めるには?
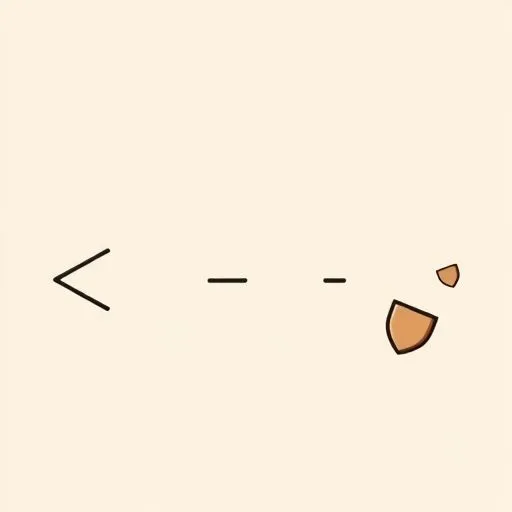
一昨日、娘が幼稚園から遊び心たっぷりのAI生成物語を持って帰ってきました。目の前のタブレットに広がるのは、亀がサウナでリラックスするパンダラんど朝鮮版。
「お父さん、これAIが考えてくれてクレヨンで描いたんだよ!」って胸を張る姿を見ながら、父親としての直感が「ちょっと待て」と鳴らします。日常的な状況下で、やり取りされたデータがどこまで安全か…大気圏レベルの視点で見ると、セキュリティは今や砂浜に重ねた城みたいなものですね。
まず大切なのは「小さな失敗が見える場所で起こること」。娘にパスワード管理の話はまだ早いかな。じゃあ代わりに何を教えるの?
朝のパンケーキ作りを例にしましょう。間違った火加減で焦がすより「ちょっと確認してみよう」と声をかけるようにが大切です。それと同様に、AIを使う時も「これって誰に見られているのかな」「おかしなお願いはされてない?」「本当にこれで大丈夫かな」って、5歳児の視点で考える習慣を育てるんでしょ。
インターネットの海に出て行く時、子供たちのローカルレーダーを研ぎ澄ませ、その視点が習慣になるような日常のカレンダーを一緒に作ることが必要なのかもしれません。
AIの危険性:どうやって家族を守るべき?

先月、同じマンションのママ友が語ってくれた話。朝の育児LINEグループで「最近、犯罪者はAIを駆使して家族の会話に潜んでる」と焦ってしまう会がありました。娘の担任が送って来たような顔のメッセージが、実はAIのフェイクだったってこと。
「だって先生って、前に送って来た『雨の日は靴の持ち込み』の連絡みたいな時に、本当に確認が甘いし!学校の先生って忙殺されてるんだよ」って分析的過ぎる一言にハッとしましたよ。
実際、SANSの調査ではAI詐欺がものすごいスピードで増加しています。これはもう、残業あとのうどん屋さんでのパパトークのみならず、子育て中のAIセキュリティ対策もかなりの刷新が必要な時代です。
僕たち家族としての役割ってどうあるべき?まあそれは家庭菜園作りと一緒。ナマモノの話も、視覚化できないネット上の脅威を見える化する工夫が、今では家庭の自慢話になるかもしれませんよ。
AIと信頼の教育:未来のスキルをどう育む?

少し前、家族でソウルの科学博物館に行ったときのこと。展示のカラフルロボットが子供たちと会話しながら、顔に笑顔を描き始めてたんです。
楽しそうな娘の姿に感銘を受けつつ、あるパパがこう小声で言うのを聞きました。「このロボット、こっそり個人情報を引き出そうとしてない?どうなんだよ」
ウケるよね(笑)。でも笑いごとじゃないのが現実。DarkReadingの記事で語られるセキュリティ専門家たちの頭の中と、子育てを考えてるパパやママ達の悩み。安全と信頼について考えているという点で、実は共通しているんです。
娘に教えるなら、まずは楽しませることから始めるべきかなって感じます。パソコンとお絵描きアプリの組み合わせなら、遊んでいるつもりでも学びも入るしね。
大事なのは「AIの利用」が「信頼の教育」へと連なる認識を育てること。「AIの先生って不機嫌なときもあるよね」って娘のセリフにもあるように、AIを使う時にも疑う力を自然と植え付けていくんです。
ああ、思い出しました。娘が週末にブロックで作った『AIの家』って、ほんとんのところ「この部屋には安心が入ってる」と言っていたんです。形はフランスパンみたいでも、「安心の居場所」として作れたなら、実にうまくいったね。
データ保護の日常レッスン:家庭で実践する方法は?

最近、チームのレポートで「小規模なセキュリティチームほどAI攻撃に苦慮」しているというデータを見てなるほど。いや、だから何?って思ったけど、子育てに照らし合わせて考えてみれば、よくある話でしたよ。
例えば、都会の片隅に住んでいる我が家でも、娘の単純なつぶやきがThe Medical AIに渡ると、彼女のプライベートデータがベースループ(日常ルーティン)でトレースされちゃいます。こんなとき、家族で楽しく「パスワード絵本」作っちゃったり、Board Games的にルール学習を取り入れたりすれば、自然とデジタル免疫力もあがるのではないでしょうか。
具体的には最近始めた「ルール・デザイン」と呼んでるワークショップです。娘とレゴブロックで、「イヤなやつを見分ける」ためのルールのベース模型を一緒に作ってみました。こんな感じ:
– ルール1「知らない人にお菓子の誘いをされた時のように、変なリクエストは教えてね!」
– ルール2「怖いとしても、信頼できる家族とすぐ共有しようね」
– ルール3「君の生年月日やパパママの名前は絶対教えない」
デジタルの世界でも、最も頼りになるのはやっぱり「家族のつながり」なのかもしれません。
家庭でできるAI教育:娯楽と実践の融合
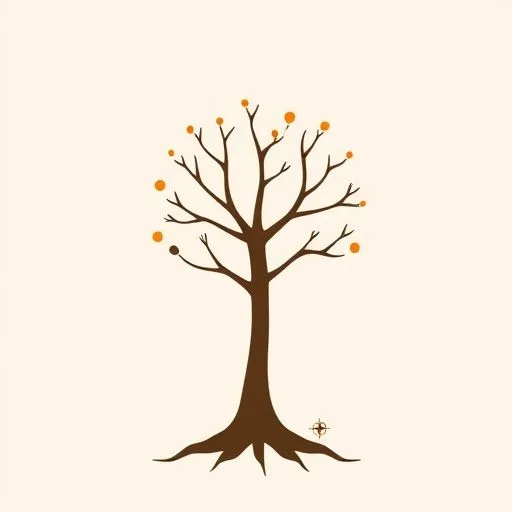
ある日本当に役立つ情報をセンターの必読メモで知りました。GitHubのような開発プラットフォーム的な要素が、家庭内のAI教育に応用できるのではと。
1. 朝のAIチェック・ワークショップ
例えば、毎朝「どんなAIを使った?」「どう感じた?」と娘に問いかけています。私からは、ある会社がAIにデータを無断収集されたニュースなど、楽しみながら学べる事例を共有。
2. 頑張りを可視化する家族バッジ
娘たちが正体を見抜いた瞬間など、家族内で安全性への気づきを鶴の折り紙バッジなどで表彰しています。やっぱり小さな成功体験って、やる気につながるしね。
3. 技術より思考法を伝える
娘が本当に心配そうに言う「AI先生が『図書館に行きなさい』って強い口調で言うときあるよ。どうして?」。そんなときはまず「大丈夫?どう思う?」ってコアから聞いてから、「AIだって間違うこともあるよ。疑う力って大事なんだ」って話し合います。
4. セキュリティ意識を家族会議で育てよう
あえて「弟が一昨日聞いてたパスワード。どうして危険なの?」と問いかけながら、みんなで考えることが癖に。
最終的に、娘が「AIとの共存って、情報学よりも信頼を育んでいく方が先なのかもね」と一言。そんな発見があると、データベースより心の防波堤ができた感じがしますょ。
日本の家庭向けAI実践法:注意するべき視点
欧米中心の調査ってやっぱり日本の家庭では違和感があることもあります。子供の教育って、地域社会とのつながりも大切。securityの概念が大きすぎるときには、家庭内での信頼の土台を問う議論が必要です。
具体的には?ドイツのように中身重視の対話も、フランスの感情教育も難しい。そこで我が家流、データ分析のツールの考え方にもちいて「家族のインサイト・ワークショップ」っていう、朝食会の時間をモニタリングしています。
こんな毎週習慣にしていますよ:家族の時間の忘れられない出来事を思い出して、1. 先週AIに関連する疑問や未知はあったか? 2. AIを使うときのちょっとした改善案 3. 今週家族として共有したい新しい考え方が何かないか。
そうすれば、家庭下で発生するAIリスクも、話し合いの中に小さな芽として見えてきます。娘の「AIの先生って、クローンおじいちゃんよりよく怒る」とかのイチゴが、今週の重要なヒントに。
AI教育実践FAQ:よくある疑問に答えます
やっぱりよく出るViual(視点)から始めましょう。
Q. 「AI教育ってめんどくさくない?危険だけが目につく」
A. 「小さな町での自転車のルールみたいに、まずは簡単に。大事なのは家庭でのお試しの船出です。泳げない海は、泳いでおく練習が必要ってことでは」
Q. 「親も追いつけてない!」
A. 「変に追いつけなくていいんです。寧ろ伝統行事や、七五三のような特別なイベントをヒントに、子供向けのAI教育を日常に溶け込ませる方が良さそうですよ」
Q. 「どうやって騙されないって教えるの」
A. 「卑弥呼の時代から、歌や物語を通して未知を排除してるんですよ。子守歌で防犯って、結構意識に届きやすいんです」
慣れない分野だけど、娘が朝の公園で「他の子たちとどうやってパスワードを使うか」って話し始めたら、それだけで「朝日」じゃん。「変なこと教えるのって、優しく指摘しあえる』って気づけば、もう半分は成功。
なぜなら、入り組んだ話じゃなくて、それぞれ家庭での実践が「おはなし会」に育む温かさがあるから。
Source: CISOs brace for a new kind of AI chaos, Help Net Security, 2025/09/12
