
「ママ、このロボットってどうして泣かないの?」が大切な対話の始まりに
リビングの床に広がるタブレットと折り紙。夕飯の支度をしながら、子どもの「AIってどうやって生まれるの?」という質問に丁寧に向き合う妻の横顔を見つめながら、子育ての世界は多面的に変わったと感じます。
スマホを片手に、画面上のプログラミング課題と向き合う子どもの隣で、遠巻きに見守る妻の視線。画面越しの対話と、現実の温もりが混ざり合う瞬間は、この時代ならではの光景なのでしょう。
デジタルが教えてくれた、人間らしさの尊さ

洗濯物を畳みながら聞いていた、子どもとスマートスピーカーのやり取りがふと耳に残りました。「ロボットは寂しいって感じる?」の問いに、AIが返した定型文の答え。それを見て「やっぱり人間の気持ちは特別だね」と呟く子どもの声に、妻が優しく頷く姿がありました。
【失敗から学ぶ価値】プログラミングで作ったゲームが動かなかった夜、一緒に原因を探る姿から生まれる対話
【デジタルと現実の境界線】VR体験後の「ママの手の温かさは特別だね」という気づき
【疑問を共有する時間】「AIにママの料理の味は作れる?」にどう向き合うか
画面から離れた夕食時、ふと子どもの口から飛び出した「AIよりママの説明の方がわかりやすい」という言葉。デジタル機器では代替できない、人の持つ温かみが伝わってくる瞬間です。
不安を力に変える家族の対話術
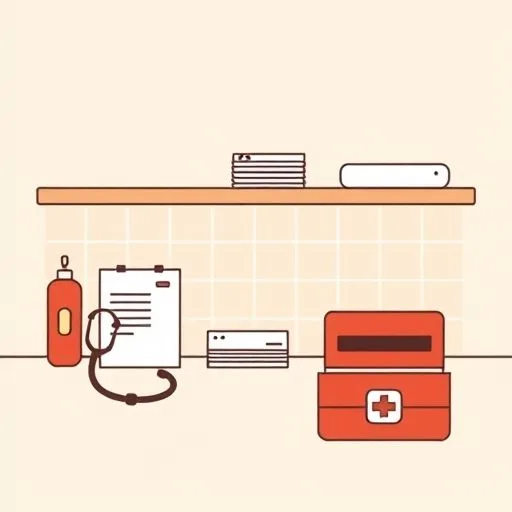
周囲がAI教育に熱心な中、焦りを感じた時期もありました。そんな時、妻が「何を学ぶかより、どう考え続けるかが大切だよ」と子どもに語りかける姿に、大切な視点を教えられた気がします。
【比較しない子育て】「お友達の家はロボットがあるんだって」への答え方の工夫
【感情を育む時間】デジタル機器の制限よりも、共に感じる体験を優先する基準
【夫婦の連携】「AIと私たちの違いって何?」への回答協力
子どもが初めて作成したプログラムが消えてしまった夜、涙を拭きながら「失敗したらまた一緒に作ろう」と背中をさする妻の手。デジタル社会で最も必要なのは、こうした回復力なのだと気付かされました。
テクノロジー越しに見える本質
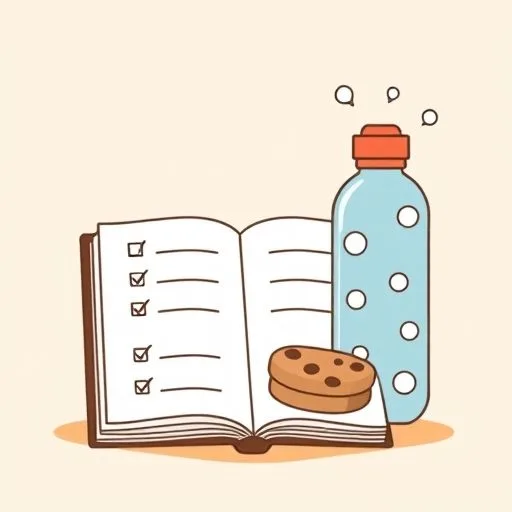
通勤バスの中で、子どもがタブレットの心拍計機能を使って「今日のママ、少し緊張してる?」と話しかけてきた日がありました。デジタル機器がきっかけで生まれた、思いがけない気遣いの形に驚かされます。
【疑問を学びに変える術】「なんでAIは嘘をつかないの?」から始まる倫理の話
【自己調整能力の育み】ゲーム時間を決めるルール作りよりも大切にしていること
【親子共成長】子どもの「なぜ?」に答えられないことで気づく学びの本質
深夜、子どものプログラミング教材に目を通しながらうつむく妻の後ろ姿を見て、そっとお茶を差し出した時のこと。「ありがとう」の一言もなくても伝わる労わり。デジタル機器は高度になっても、人の心を通わせる小さな瞬間こそが、家族の絆を深めるのだと感じます。
テクノロジーが進化すればするほど、人間らしさの価値が際立つ。君から教わったこの気づきを、子ども達と一緒に育んでいきたいと思います。
出典: A New Lever – Unlocking Entrepreneurship With AI, Forbes, 2025-09-30
