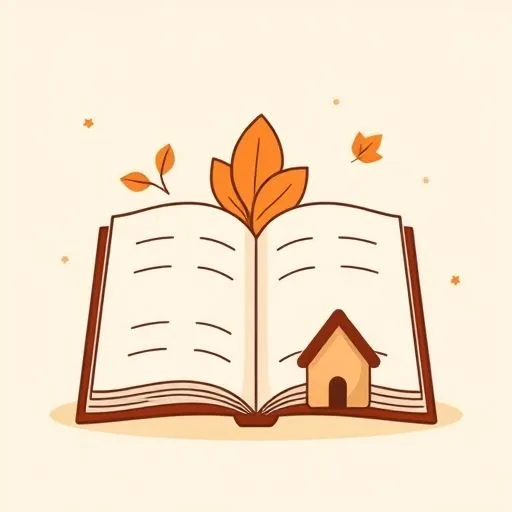
AI時代に必要な子育ての新基準|アジア協力精神が教える未来づくり
9月20日、ソンドウの22.5度の晴天—アジア映画市場ACFMのAI協力ニュースを見て「子育てに通じる」と気づきました。AI時代の親が学ぶべきヒントを共有します。
協働力の育て方は?アジア映画産業が示す子育てのカギ
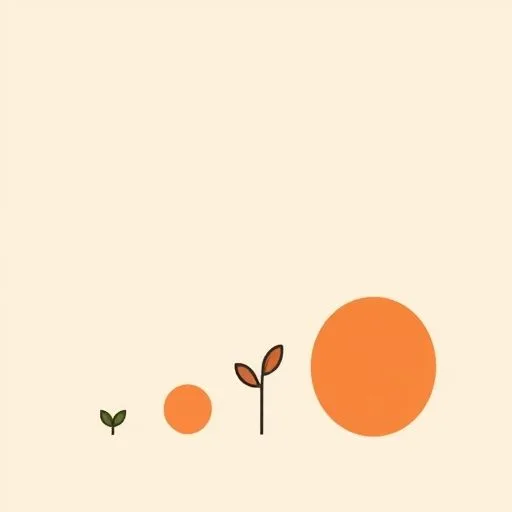
ACFMの新しいプログラム「The A」は、アジアの映画産業間の真の協力の基盤を築くことを目的としています。この「協力」っていうのは、実は子育ての大事な部分に関わるんですよね。AI時代の子育てでは協働経験が特に重要です。
私の娘は、今ちょうど小学校低学年。この時期、子どもは友達と協力することの喜びを自然に学んでいきます。先日、娘は近所の公園で他の子どもたちと一緒に大きな積み木で城を作っていました。まさに、AI時代の子育てで大切な「協力」の精神を体現していました。一人ではできない大きな夢を、みんなで力を合わせて実現する。まさに「The A」の精神そのものです!
アジアの映画産業がデータを共有し、成功事例を学び合うように、私たちも子どもたちが自由にアイデアを交換し、互いの才能を認め合う環境を作ってあげたいものです。そうやって育った子どもたちは、将来グローバルな社会で協力し合う力を自然に身につけることができるでしょう。
AI時代、親の役割はどう変わる?技術との向き合い方

ACFMが注目するもう一つの柱は「技術とコンテンツの融合」です。特にAI技術の進化は、私たち親にとっては「どう接すればいいのか」悩ましい問題ですよね。AI時代の子育てって、バランス感覚が大事ですよね。
最近、娘がAIを使って簡単な物語を作るアプリに夢中になっています。最初は「AIって怖いよね」と思っていましたが、娘がAIと遊びながら自分の想像力を表現している姿を見て、考え方が変わりました。
ACFMが創作者向けに実践的なツールと教育を提供しているように、私親も子どもがAIを楽しみながら学べる環境を作るべきだと感じました。大切なのは、AIを「敵」ではなく「パートナー」として位置づけること。子どもがAIを通じて新しい発見をし、クリエイティブな思考を育む手助けをしてあげたいですよね!
特に「AI教育」を意識しながらも、現実世界での体験や人間との触れ合いが一番大切だってことを、親として痛感しています。だから、私たち親は、AIを「敵」ではなく「パートナー」として位置づけ、子どもたちが新しい発見をし、クリエイティブな思考を育む手助けをしてあげたいですね。
グローバル思考を育むコツ|境界を越えた子育て実例

