
夕暮れ時のリビング。テーブルにはクレヨンで描かれた太陽の絵が置かれている。線はゆがんでいるけれど、その生命力に胸が熱くなる。AIが生成する完璧な画像にはない温かさが、色とりどりの画用紙の上で脈打っているのを感じる夜でした。
「なんで?」が未来を創る

この間、公園で4歳の子が石を拾い上げて「なんで丸いの?」と尋ねるのを見かけたんです。隣でお母さんが「そうだね、どうしてかな?」と逆に問い返している。
AIは答えを教えてくれるけれど、問いを紡ぐ力こそが人間の特権だと気づかされる瞬間です。
親として大切にしたいのは、すぐに正解を教えることより、「一緒に考えよう」という姿勢かもしれません。
空を見上げて「雲が動くのは風さんがお散歩してるからかな?」と想像を膨らませるあの温かな時間——テクノロジーでは代替できない宝物です。
画面の向こうと手のひらの温度
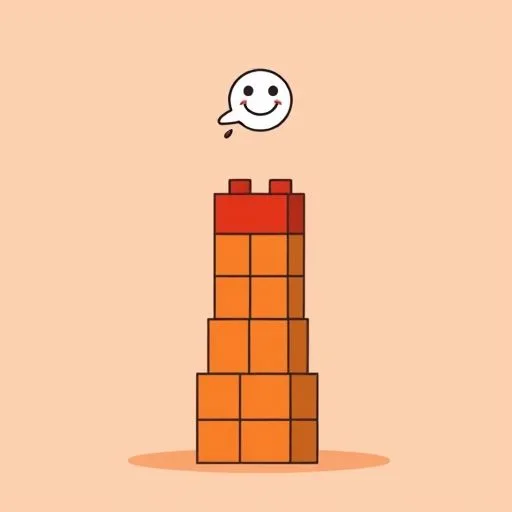
先日、図書館で面白い光景を見ました。タブレットで恐竜の動画を見ていた男の子が、突然「折り紙でティラノサウルス作りたい!」と言い出したんです。
お母さんがスマホで折り方を検索しながら、一緒にチャレンジし始める。
デジタルツールを入り口にしながら、最後は自分の手で形にする——このバランスこそが現代の子育ての鍵だと感じます。
完全なCG映像よりも、自分で作った少しふにゃふにゃの作品に、子どもはなぜか特別な愛着を持つものですね。
不完全さが育む絆

スーパーのレジでこんなことがありました。母親が「AIスピーカーで聞いてみようか」と提案すると、5歳くらいの女の子が「でもママに聞きたいの」と答えていた。
機械の正確な回答よりも、大好きな人の言葉を選ぶ子どもの選択に考えさせられました。
私たち親にしかできないこと——それは完璧なアドバイスではなく、失敗した時に「大丈夫だよ」と背中を撫でる手の温もりかもしれません。
描いた絵の形がいびつでも「この色づかい素敵だね」と認めてあげられるまなざしは、AIでは再現できない優しさです。
布団の中の未来会議

寝る前のわずか15分間、子どもの「今日の不思議」に耳を傾ける習慣があります。「ロボットはお友達になれるの?」「AI先生は宿題を手伝ってくれる?」——子どもたちの質問は、そのまま未来社会の設計図のように感じられます。
答えよりも、一緒に考えるプロセスが大切だと改めて思うのです。
タブレットで調べて終わるのではなく、その後で実際に絵を描いたり、粘土で形作ったりすることで、デジタルとアナログの架け橋ができる。
明日からできる小さな一歩は、この対話の時間をほんの少しだけ大切にすることかもしれません。子どもの掌からこぼれる創造の輝きを、これからも見守り続けたいと思います。
引用元:Variety(2025年9月21日)『Big Tech is Under Pressure From Emerging AI Giants. How Will This Change Hollywood?』
