
最近、新しいツールが仕事のペースを変えていると感じませんか?ある朝、コーヒーを片手にデスクに向かった時、隣の席の同僚が『AIでこのタスク自動化されたんだ』とぽつり。じっとり汗ばむ手をふきながら、ふと疑問が浮かびました。技術のせいで仕事を失うの?技術のせいだと嘆く前に、一緒に紐解いてみましょう!いや、違う――本当に動かしているのは…AI時代の働き方を考えます。
「AIの神父」が突きつける現実とは?

ノーベル賞受賞者でもあり『AIの神父』と呼ばれるGeoffrey Hinton氏が、金融時報へのインタビューで深い警鐘を鳴らしています。
『富裕層はAIで従業員を代替し、大量失業と莫大な利益を生むだろう』と。
技術そのものが悪いわけじゃない――それが資本主義システムの問題だと言います。
確かに、新入社員の機会が減っているという声を耳にします。でも気になるデータがあります。ご存じですか?AI導入企業が生産性向上で製品価格を下げ、結果的に需要拡大で雇用を増やした例もあるんです。
職人さんの包丁のように、研ぎ方で可能性が広がりますね!刃物は使い方次第で傷つけも助けもする。
隣の席の同僚も、結局そのツールで退屈な作業から解き放たれ、顧客と向き合う時間が増えたんだとか。
『自動化された部分に、実は救われてるかも』と笑っていました。
自分にも思い当たる節が…AIとどう向き合うか、改めて考えてみましょう。
システムの歪み、光を見る目をどう持つ?

Hinton氏は『失業はAIのせいじゃない』と強調します。
システムが労働者の尊厳より短期利益を優先する限り、技術は道具に過ぎないと。
一方、ある研究では明るいシナリオも。企業がAIと協働する社員を育て、新規事業で共に成長したケース。
これぞ真の〈win-win〉ですね。考えてみてください。
伝統工芸の職人さんが新技術を取り入れる時、道具は手の延長になる。機械が作品を作り出すのではなく、人の想いを形にするサポート役です。
仕事でも同じ。『AIのせい』と嘆くより、『どう使いこなすか』に意識を向ける。ほんの少し視点を変えるだけで、暗いトンネルの先に光が差し込みます。
みんなで作る選択が未来を変える――そう信じてAIと共存する道を探りましょう。
あなたの強みは消えない――どう活かす?
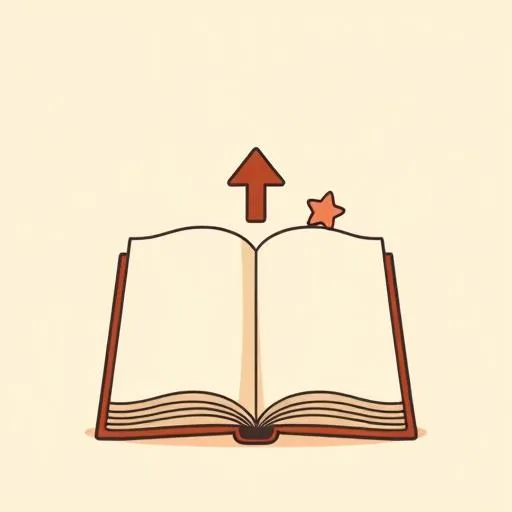
Hinton氏はUBI(ベーシックインカム)でも『労働の尊厳』は補えないと言います。確かに、ただお金を配るだけでは心の空隙は埋まりません。
でも、だからこそ。人と機械の役割を線引きする必要はないのです。
AIが得意なのはデータ処理。あなたが得意なのは、目の前の相手のため息に気づき、『大丈夫ですか?』と声をかけること――こういうスキルは永遠に失われません。
さっきも、新入社員がAIツールで資料を作りながら、『最終チェックは先輩の目が勝る』と。その温かい心遣いこそ、技術では再現できない宝物。
子育てと似てますね。子どもの見えない不安に気づく親の目は、どんなセンサーより鋭い。「この作業、AIに任せたら何が生まれる?」と自問する習慣。小さな問いが大きな変化を呼びます。
希望を紡ぐ一歩をどう踏み出す?
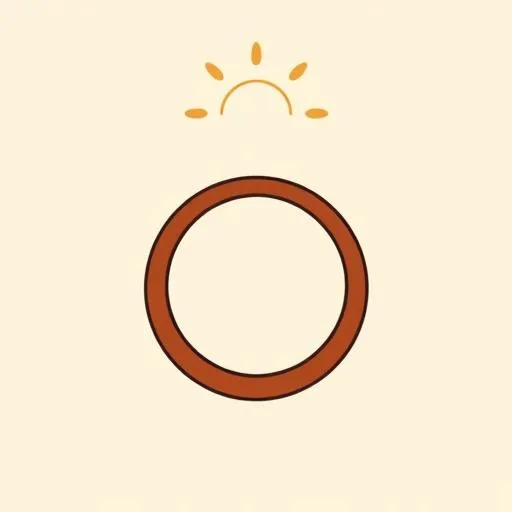
朝の通勤道で、いつもよりゆっくり歩くことにしました。駅前の公園では、子供たちが落ち葉を集めて工作。
AIと同じで、素材は自然にある。必要なのは『どう活かすか』の創造力です。
Hinton氏が心配する未来を変えられるのは、みんなで作る選択。研究が示すように、企業が労働者と協力すると雇用は増える。
だから今、あなたにできる今日から試せるアイデア:
- 目的を確かめる:『このツール、お客様のためになるか?』と自問
- 人との繋がりを育む:週1回、同僚とコーヒーを囲んで「最近何が嬉しい?」と聞く
- 小さなチャレンジ:AIで省かれた時間、新しいスキル学習に20分回す
初秋の風が頬を撫でる朝、同僚と『これからどうなる?』と話しました。答えは出ませんが、その会話自体が力になりました。
技術は流れる川。私たちの価値は、その流れの中で輝く石のようなもの――動かされることはありません。10年後、どんな役割で笑っていたいですか?
Source: 「AIのせいじゃない、資本主義システムのせい」 『AIの神父』が雇用喪失と利益拡大を警告, Windows Central, 2025/09/08 11:41:35
