
夕暮れ時に公園のベンチで見つけた落書きが胸に刺さりました。クレヨンで描かれた不恰好な虹の下に「AIさん、空ってなんで青いの?」と書かれていたんです。娘が通う小学校のすぐ横にあるその公園では、毎日子供たちの無邪気な疑問が風に乗って聞こえてきます。最近読んだ記事で、AIを倫理的に使うことの大切さが強調されていて、それがこの落書きと重なったんだ。デジタルネイティブ世代の親として、この子たちが作る信頼と創造性の未来にどう寄り添えばいいのか、桜の葉が舞う小道を歩きながら考えたことをお話しします。
AI時代の子育てでどう信頼を築く?落書きが教えた方程式

先月、娘が学校から興奮して持ち帰った「魔法の宿題帳」というアプリは、問題を解くとキャラクターが成長する仕組みでした。ところが三日後、突然「どうせ私よりAIの方が正しいんでしょ?」と口にしたのです。その言葉、まるで雨上がりの公園の落書きみたいに、色褪せない力強さがあったんだ。
UNESCOのAI倫理指針が求める透明性を家庭で実践するとしたら、「パパのスマホはなぜそんな答えを出すの?」という質問に、仕組みを一緒に調べてみることかもしれません。私たち親がデジタルの『なぜ?』に丁寧に向き合う時、子供はテクノロジーを信頼する術(すべ)を学んでいきます。
「機械だって助け合いが必要なんだね」
夕食のキムチチゲがぐつぐつ煮える音をBGMに、こんな実験をしました。絵を描くAIに「幸せな家族」と指示すると、どんなに試しても両親と子供二人の標準的な家族像しか出てこない。そこで娘が「じゃあ『犬とおばあちゃんと宇宙飛行士の家族』って入れてみよう!」と提案したら、驚くほど個性的で、もうビックリするような作品が完成したんだ!娘のつぶやきが、キッチンに灯(とも)った優しい明かりのように心に残りました。
多様性を育むには?ブランコから学ぶAI倫理の原点
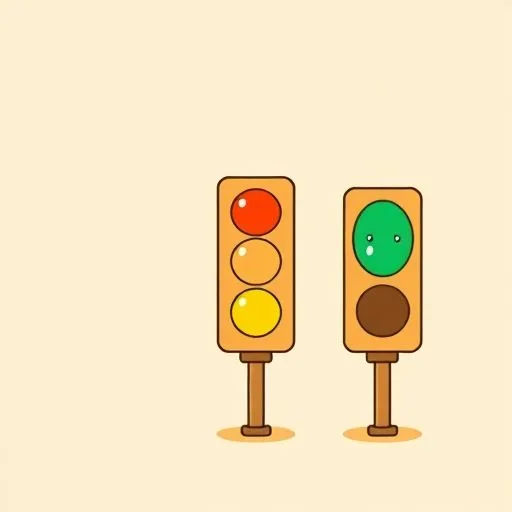
近所の公園でよく見かける光景があります。ブランコ順番待ちの列で、背の高い子がわざと小さな子の分まで地面を蹴って漕ぐのを手伝っているんです。こんな日常の小さな公正さが、AI倫理の核にある「公平性」の最初の教室かもしれません。
多様性って、実は身近なところ、例えばおもちゃ箱の中にもヒントがあるんだよ。娘の描く「ロボットの友達」の絵には必ず車椅子の子や眼鏡をかけた子が登場します。ある日彼女が言いました。「パパの仕事のコンピューターも、いろんな色のクレヨンで描かないとダメだよね」。そして、そういう小さな「公平」の感覚が、実はAIとの付き合い方にも繋がっているんじゃないかって思ったんだ。
ある雨の日、教育用AIが算数の問題で「弟が3個のチョコを持っていたら」という設問をいつも使うことに娘が気づきました。「妹じゃダメなの?おばあちゃんでもいいよね」。その気づきを開発元に伝えたら、一週間後には多様な家族形態を含むアップデートが届いたんです。小さな声が社会を変える実体験は、子供にとって何よりの倫理教科書でした。
未来とどう向き合う?シャボン玉が示す人間らしいAI活用

カナダ出身の祖母が送ってくれたメッセージ動画や、韓国の祖父母と繋ぐビデオ通話。これらのデジタル記憶が、娘の心に刻む「家族の形」は計り知れません。AI倫理が守るべき人間の尊厳とは、こうした小さな繋がりの積み重ねではないでしょうか。
フロンティアーズ誌の指摘する説明責任を、我が家では「AIクイズ大会」で実践しています。例えば推奨動画が表示された時、「なぜこれが選ばれたのか」を親子で推理するゲームです。先日、恐竜動画ばかり薦められる娘が「きっと僕が昨日図鑑でティラノサウルスを調べたからだよ!でも翼竜も見たいな」と気づいた時、機械と人間の協働関係の原点を見た気がしました。
青空の下で、シャボン玉を追いかける子供たちの笑い声が、倫理的技術革新の最高の指標だと信じて。
最終的に子供に残すべきは、テクノロジーに使われるのでも、振り回すのでもない、「共に成長する力」です。公園の砂場で娘が作った「AIロボットの家」には必ず充電器と本棚があります。彼女の言葉を借りれば「疲れたら休んで、分からないことは本で調べるのよ」。この無邪気な知恵こそが、人間中心のAI社会の核心かもしれません。
