
歴史はAI時代に何を教える?蒸気機関から学ぶ希望の声
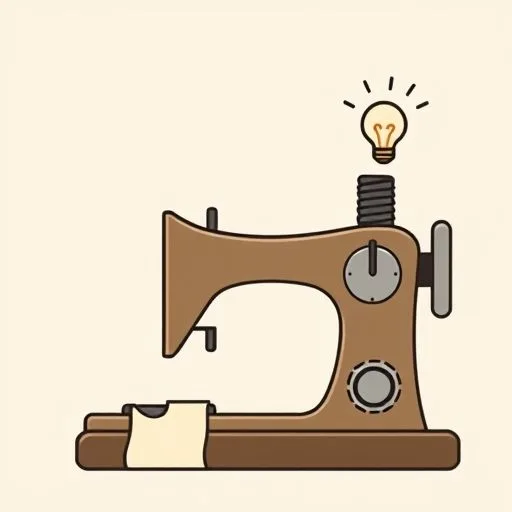
ソフトクリームを頬張りながら博物館を歩いていた週末、1850年代の織機の前で娘が叫びました。「すごい!まるで巨大な楽器みたい!すごい!」確かに昔の技術革新は、人々を恐懼させつつも新しい音楽を生み出していました。
移民としてのルーツを考える時、曾祖父がカナダで鉄道建設に携わった話を思い出します。当時「蒸気機関が仕事を奪う」と騒がれたものの、実際には鉄道沿線に新たな町が生まれ、教師や店員、医師の需要が爆発的に増えたのです。
現代の研究でも示唆されています(ScienceDirect論文参照)技術は特定の仕事を消すけれど、全体として雇用を生む『補償メカニズム』が働くのだと。まるで子供が積み木を崩して、もっとすごいお城を建てるみたい!
AI時代に必要な人間の筋肉とは?子育てで育む力

雨の日曜日、新聞紙で巨大なタワーを作っていた時のこと。娘が突然「AIさんなら、もっと上手く作るんだろうなぁ?」と呟きました。その瞬間、凧揚げで学んだ教訓を思い出したのです。「ハイテク凧もいいけど、風を読む『感覚』がなければただのビニールだよね」
TIME誌の分析が指摘するように、AIが真に脅かすのは「信頼・共感・傾聴」といった人間の本質的な能力です。うちでは週に一度、デジタルデトックス日を設けています。
スマホをしまう代わりに、公園で拾った葉っぱの脈理を観察したり、近所のおばあちゃんに手紙を書いたり
娘が発明した『叶えたいことバスケット』には「アイスクリーム屋さんのお姉さんの笑顔を100個集めたい」という夢が入っていました。
日常で創造力を育むには?AI時代の子育て魔法

MITの研究(詳細はこちら)が示すように、1980年以降は技術による雇用喪失が創造を上回っている傾向にあります。でも子供の可能性を潰すのはテクノロジーではなく、固定観念かもしれません。
我が家で人気のゲームは『未来職業発明大会』。先日は娘が「クラウドの形を整える雲デザイナー」を提案してくれたんです!デジタル地図を見ながらお昼散歩する時、敢えて「ここにどんなお店が生まれたら街が楽しくなる?」と問いかけます。
焚き火の前でお餅を焼きながら「昔の人は、おばあちゃんが作ってくれたこのお餅みたいに、どうやって上手に火加減してたのかな?」と想像するのも大切なトレーニングです。
未来の仕事で不安を希望に変えるには?3つの子育てレッスン

世界経済フォーラムの報告書(原文)によると、実に40%の企業がAI導入で人員削減を検討中だそうです。でも歴史が教えるのは、危機の後にこそ新たな扉が開くということ。
- 「学び直し力」を育てよう:先月、近所の大工さんにDIYを教わった娘は「木の匂いで季節がわかるよ!」と発見しました
- 違いを力に変える:カナダと韓国のルーツを持つ我が家では「言葉のサラダボール」を作るのが遊び。英語と韓国語と日本語をミックスした新語の発明大会です
- 「人間らしいニッチ」を見つける:バス停で出会ったおばあちゃんの人生談義を絵本化するのが娘の最新プロジェクトです
未来を紡ぐ親子の絆:AI時代の人間らしさ育み方

あの夕暮れ、最後に自転車が勢いよく走り出した時、娘が叫びました。「パパの『がんばれ!』の声がブレーキになったよ!」。技術が急速に発展する時代こそ、人間同士の声の掛け合いが安全装置となるのでしょう。
世紀を超えて受け継がれるのは、単なるスキルではなく、人を思いやる心の温もりです。街路樹の紅葉が始まる季節、家族で落ち葉を集めて『未来の仕事予想図』を作るのが今年のプロジェクト。そこで描くのは、テクノロジーと共に生きる、優しい人間たちの姿です。
出典: AI Isn’t The First Job Killer: What 200 Years Of Work Teaches Us About The Future, Forbes, 2025-09-22
