
宿題の時間に隣に座る代わりに、タブレットの光をじっと見つめる子供の姿。そう思うと、複雑な気持ちになりませんか?AIがすぐに答えを教えてくれる便利な時代。でもふと、子供たちが鉛筆の先に感じた紙の感覚や、わからずに悩んだ時間の大切さを思い出してしまうのですよね。
AIに宿題を任せる時、覚えていて欲しいこと
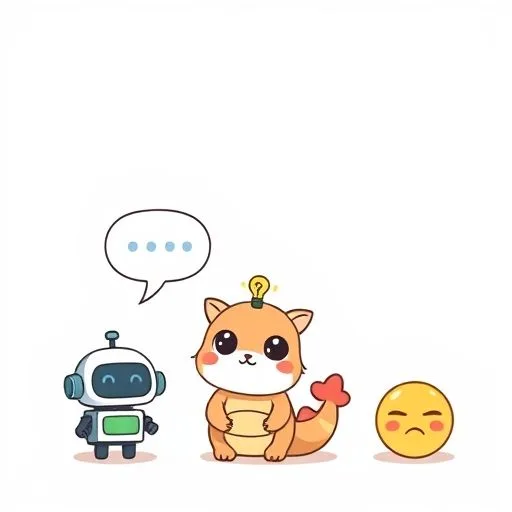
子供たちがAIを操作する指先の動きって、すごく早いですよね。あのスピードに驚きつつも、同時に感じるのは…。
私たちが小さかった時の「あれ、これどうやって解くんだっけ?」って唸りながら考えた時間の味。そう、AIは答えを教えてくれますが、悩みながら考えたプロセスでしか味わえない感動の瞬間は、自分で育ててあげるしかないのですよね。
任せられるものと任せないもののバランス
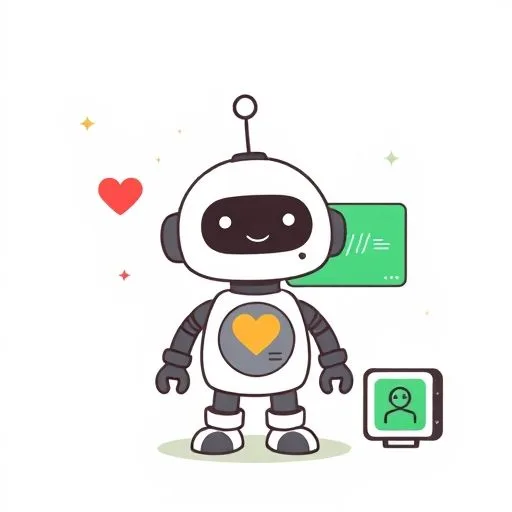
例えば、反復練習が必要な計算問題や漢字ドリル。AIのサポートはとても便利ですよね。
問題は、自分の考えをまとめる力が必要な課題にどう向き合うか。例えば、作文を書く時、AIがすぐに文章を生成してしまったら…。
子供たちは、自分の中の言葉を探す楽しみを失ってしまうかもしれません。そう思うと、ちょっとゾッとしますね。
AI時代の親子の関わり方3つのアイデア

- AIを使う時間と、1時間のうち15分はAIなしで考え抜きましょう:子供と一緒に考える時間のルールを作りましょう。
- 悩む時間を『宝物』と認める:間違った答えをノートいっぱいに書き散らした経験。あの時間が、実は脳を育てる黄金の瞬間だったのです。
- 『AIの苦手』を知る:AIの苦手は「人間の感情」の表現。悲しい時の涙、喜びの笑顔を描く宿題は、親子で一緒に発見してみましょう。
AIと共に、子供たちの『考える』を育てるために
大切なことは、AIと対立することではなく、使い方を学ぶこと。
そう思うんです。AIが答えを教えてくれたら、その隣に座って「どうしてそう思ったの?」と尋ねる時間を作ってみませんか。
子供たちがAIを超えた言葉で、私たちの知らない答えを発見する時が来るかもしれません。そう信じて、私たちは、子供たちの隣の『AIでもできない大人の役割』を守り続けたいのです。
Source: I Need AI to Write Better Lesson Plans So My Students Stop Using AI to Write Their Papers, McSweeney’s, 2025年9月30日
