
「これで大丈夫?」が「これなら楽しい!」に変わる
子どもが寝静まった後のリビングで、スマホの画面に浮かぶAIによる作文添削を見つめながら、ふと考え込むことがありますよね。『AIに頼りすぎじゃないか』『創造力が育たなくなるのでは』――そんな不安を抱えるお母さんの横顔を、そっと見守りながら思うのです。
バングラデシュの学生たちがChatGPTと築く意外な関係から、私たち家族の明日が見えてくることを。私たちはテクノロジーを恐れるのではなく、共に成長する方法を学ぶ時なのです。
AIが教えてくれた、バングラデシュの学生の柔軟な発想
限られたリソースの中で学ぶ彼らが、AIを「もう一人の対話相手」として使っている姿に驚かされます。詩を共同制作したり、物語の続きを予測し合ったり――まるで親友と遊んでいるような感覚でテクノロジーと向き合っているんです。
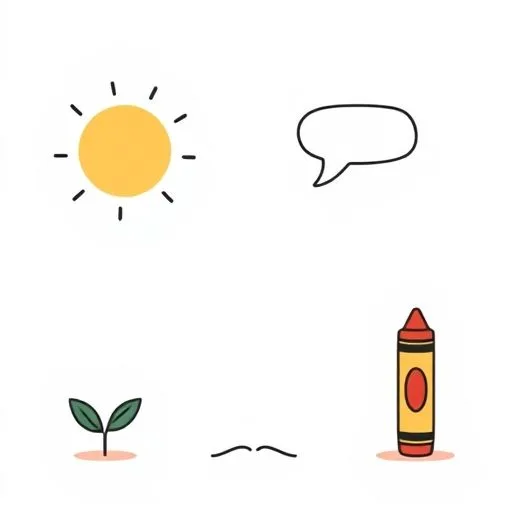
このスタイリッシュなアプローチ、私たちの家庭でも真似してみよう!夕食後の10分間を『AI探検タイム』にしてみませんか?子どもの『なんで空は青いの?』といった質問を、一緒にAIに投げかけてみる。大切なのは、正解を探すことではなく、問いかけるそのプロセスを共有することなんです。
私の娘は、AIからの答えを聞いて『もっと面白い答えがあるかも!』と新しい質問を考えるのが大好き。想像力の翼が広がる瞬間ですよ!
創造性の芽を摘まないAIの使い方
あなたが子どもに絵本を読み聞かせる時、最後のページをめくる前に『どうなると思う?』と問いかけるその優しさ――それこそがAI時代に必要な接し方なんです。
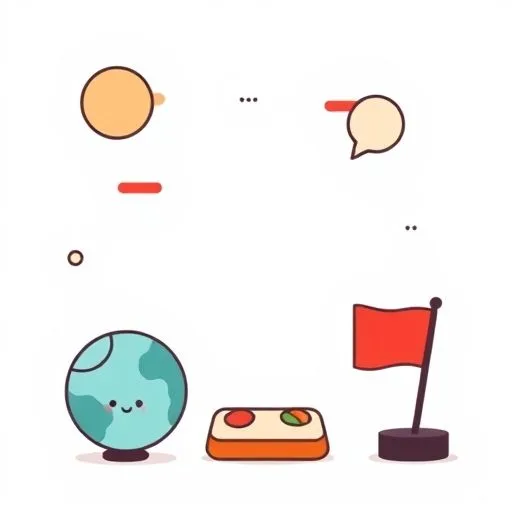
バングラデシュの学生たちはAIの回答を鵜呑みにせず『本当にそうかな?』『別の考え方は?』と問い返します。週末に家族で『AIおかしな回答選手権』を開いてみたらどうでしょう。変な答えを見つけて笑い合ううちに、楽しく学びながら、批判的思考が育っていきます。
娘はAIが提案したキャラクターを『もっと可愛くできないかな?』と変えるのが得意。子どもたちはAIを先生じゃなくて、一緒に遊べる友達だと思ってるみたいです。
10年後に必要なのは、AIよりも人間らしさ
テクノロジーが発達すればするほど、大切になるのは人間特有の感性です。
バングラデシュの若者が教えてくれたのは、経済的・文化的な違いを超えて通じる『学ぶ楽しさ』の本質でした。

朝の忙しい時間に、AIと会話する5分間を設けてみては?『今日の天気は?』ではなく『今日はどんな面白いことがあるかな?』と質問してみる。そこで得た答えをもとに、家族の会話を広げていく――それだけで子どもたちの好奇心の種が育ち始めます。
私たちはこのテクノロジーが、子どもたちの想像力の扉を広げるツールとして使できるのでしょうか?
明日から始める、AIと共に育む家族の習慣
週末の夜、家族で物語を作ってみませんか?誰かが最初の一文を話し、AIが続きを提案し、また誰かが続ける――バングラデシュの学生たちからヒントを得た共同創作ゲームです。
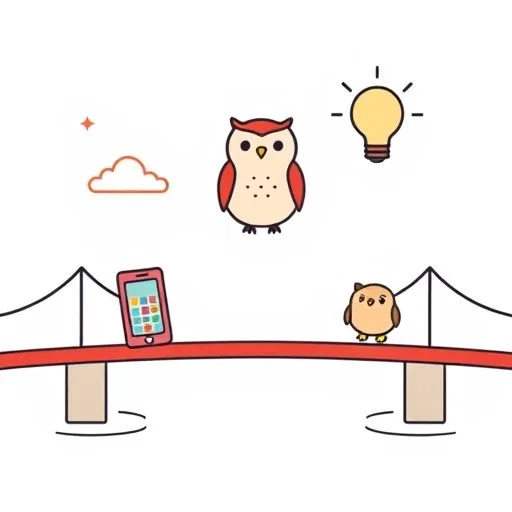
AIが提案してきたキャラクターの性格を『もっと優しくしようか』『このセリフは本当に言うかな?』と家族で話し合う。その過程で自然と、倫理観や想像力が育まれていきます。
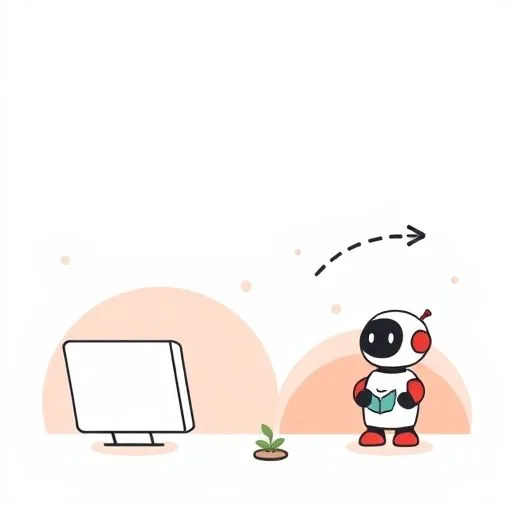
テクノロジーは、あなたがずっと大切にしてきた家族の温もりを深めるツールになり得る――そんな希望を、今日もそっと胸に抱きながら。
AIと共に育む家族の未来は、もっともっと豊かで楽しいものになるはず!私たちの好奇心と愛があれば、どんなテクノロジーも家族の絆を強める助け手になってくれるんですよ!
出典: バングラデシュの大学生がChatGPTをどう活用しているかの質的研究(PLOS ONE, 2023年)
