
いや〜、今日の天気、なんだか気分が上がらない? でもね、そんな時こそ、ちょっと未来の話、してみない?
国家運営そのものがAIの支配に…?アルバニアに続き、日本の自治体間でも驚きの動きが。
うちの娘の小学校まで徒歩100mという近さも、AIの恩恵なのかもしれん!?しかし親として、果たしてどんなバランスが最善だろう?
さあ、この気になる話題を一気見ていこう!
AI大臣登場—裏通りの便利が本丸に、親の役割とは?
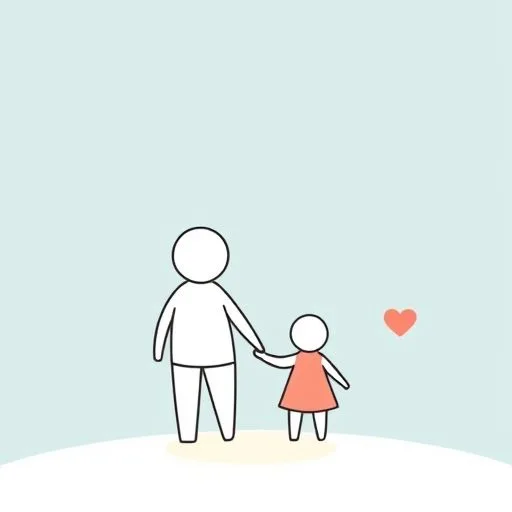
「閣下、返済督促が13万件重なってます」なんて会話が国会であるだろか?
朝霞市ではAIが都市計画ツールとして親たちに愛されている。うちも使って園児のアレルギー情報を市役所に届けるのに30秒で手続き完了さ!
しかし娘に教えたこと——「デジタルは便利でも、最終的には人間がチェックするガッツが必要」と。
これは、僕たちが大切にしてること、つまり、AIを便利に使いつつも、最終的な判断は人間が、という僕たちの信条にも繋がる気がするんだ。
AI時代の親の役割を考えるきっかけになった。
さて、AIが国を動かすとなると、私たちの家庭はどうなるんだろう? 特に、子育て世代としては、ちょっと気になることがあるんだよね。
教育の未来にAIが舞い降りた!?今すぐ使える2つのツールパス

地元のショッピングモールでAIプログラミングワークショップ見かけたことあるか?あの張り紙、「子どもの可能性がキーボードの向こうにある」ってキャッチがヤバくない?
だが現実。自治体の課金システムが暴走して保護者の財布を絞らぬよう、音声アプリのチャットで市教委にチェックできるようになったんだ。
ESAの報告にある「AI×市民体験向上」完全に叶ってるやろ?
うちの娘にはロボットごっこが好きなもんで、早速役所のAIツールを真似してポリシー文書作成の真似事をさせてみた!AI時代の教育の未来を感じさせる体験だ。
守るべき3つのプレーン—日本のパパたちからの警告信、子育てのヒント
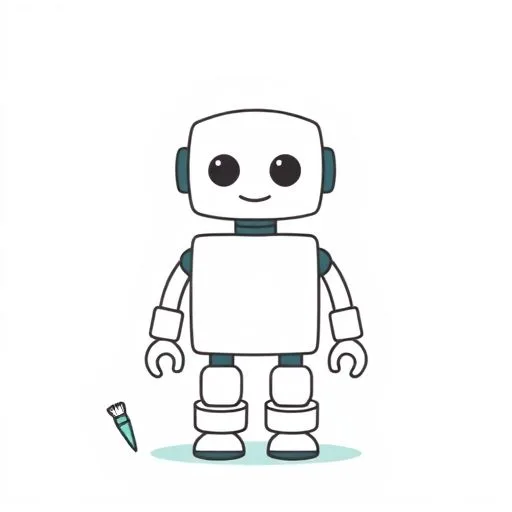
警視庁はじめ数多く部門がAIで業務簡素化ってのはいいが、「守る」というサガに入らないと危険。
うちの奥さんが、娘の咳についてAIの健康アシスタントに『ちょっと風邪かな?』と軽く聞いてみたら、『呼吸困難の可能性があります!即刻救急車を!』と返されて大騒ぎに(笑)。でも実際は保育園でちょっと遊んだだけだったんだ。
実話を基にエーテックパパとしての心得。
第一に子どものプライバシー。
第二にメンバーコントロールの感覚を持つこと。
第三はAIに投げ捨てず「どこまでやらせるか」を家族会議で決めるべき!
下町の親の会で共有したら、『うちの子もAIで変な答えを聞いてびっくりしたことがある!』と共感の笑顔をもらえたんだ。
AI時代の子育てのヒントとして参考に。
完璧なAI≠完璧な国—パームツリー並木の教訓、AIと人間の調和

東京の駅で体験したAI案内ロボットの話。地下鉄のホームで『雨が降りそうなので傘を貸します』と優しく声をかけてきた。でも実際は、ただ単にカメラのレンズが曇っていただけだった(笑)。
そんな小さなミスも、家族との会話のきっかけになるんだよ!
正解率90%でも10%のハズレを全部否定するより、「そこを手当てする町づくり」、これこそNo.1の革新ハイ!
NTTの神様話みたいだけど、アルゴリズムには「家族との会話のきっかけになるような優しさ」が必要だよね!
AIと人間の調和を考える良い例だ。
子どもとAIの交差点—三行警告システム解説、親としての備え
娘が土曜日の朝、大はしゃぎで「お部屋のお掃除ロボットが、なんだか変な動きをしたんだけど!」って報告してきたんだ。
ただの遊び心で、科学番組で見たようなAIに質問したみたい(笑)。
完璧やけど…この現象、親ならではの恐怖なくせえ!?
最近、家族会議で「AIと上手につき合うルール」を決めたんだ。その時のメモをシェアするね!
- マイナンバーカードを子どもの手にさせん
- 地域のAI接待員(案内ロボの愛称)に政治の話をさせるのは危ない
- 子どもチャットのログを一週間に一回確認する習慣を持て
- 学校の選択制授業ツールの価値を金銭換算するな
- AI育児を完全に信用する前に「購読ママ話」をチェック。
親としての備えが大切だ.
Source: Grok, how do I run a country? Here’s how AI is quietly taking over governments, RT.com, 2025-09-14
