
夕飯の支度をしながら、ふと気づいちゃった。リビングでタブレットを握りしめている娘がAI教材の声に嬉しそうに応えている姿に。
先週ニュースで見た「児童虐待判定AIの導入見送り」の記事。10億円のシステムがもたらす葛藤が台所に立つ私の背中に重くのしかかって。
『便利さ』という名の漂流物にわが子の未来が流されてしまわないか。親としてのワナにはまっていないか。柔らかな夕暮れ時に、そんな疑問が胸をよぎりました。
家庭に溶け込んだ「デジタル同居人」
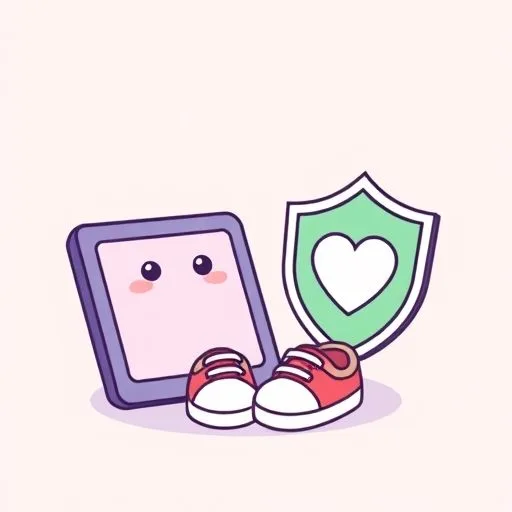
子供たちがAI教材で遊ぶ声が聞こえる朝。それはまるで新しい家族が増えたような温かさで、でもふと気づくのです。
テレビの音声認識機能が子供の会話を拾っているかもしれない。おもちゃのプログラミングロボットが行動パターンを記録しているかもしれない。
公園のブランコに安全基準があるように、デジタル遊び場にも見えない柵が必要な時代。私たち親はその境界線をどこに引けばいいのでしょう。
便利さの陰に潜む親のジレンマ
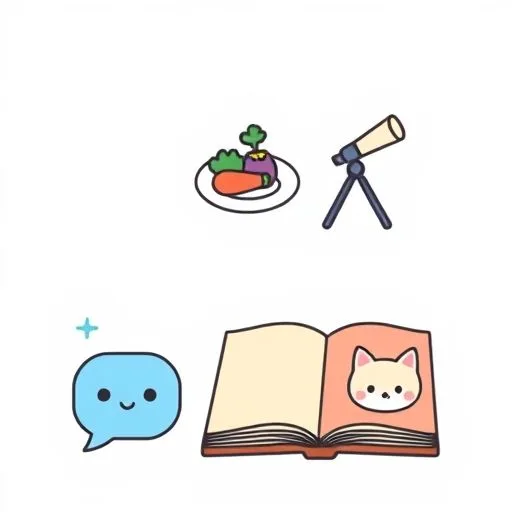
先日子供が私に質問しました。’パパのスマホ、なんで毎回パスワード変えるの?’その言葉を聞いて、二人で真剣に考えた。AI育児アプリの利用規約を読む夜更け…その真っ直ぐな瞳が今でも鮮明に覚えている。
AI育児アプリの利用規約を読む夜更け。同意ボタンを押す指が止まることがあります。『これ、子どもの将来を縛り付けちゃわないかな?』。
ベビーゲートを設置するときの慎重さでデジタルの扉の開け方を考えてみませんか。子供の可能性を育てつつ見えないリスクからも守るバランスとは。
共働き家庭のデジタル保母さん

仕事から帰ると、妻がため息をついていました。’AI保育ロボットの導入、結局見送りになったらしい’その表情に共感できる部分と疑問が入り混じっていました。
共働き家庭の強い味方であるはずの技術が、時に人間の判断を超えた不安を生むことも。
自転車の補助輪を外す時のように、AIのサポートから自立へのステップをどうデザインすれば良いのか。子育ての新しい課題がそこにあります。
未来を生きる子供たちへ贈る盾

先日幼稚園の図書コーナーで見つけた本。’AIと友達になろう’というタイトルに最初は戸惑いました。でも中身を読んで思わず頷いてしまったのです。
現代の子供たちにとってテクノロジーは空気のように自然なもの。禁止するのではなく賢く付き合う術を教えることが本当の意味での安全対策なのかもしれません。
子供部屋の窓に取り付けた防犯センサーと同じ感覚でデジタル空間の見守りシステムを考えてみる。過保護にならず、無防備にもならない絶妙な距離感を見つける旅が始まっています。
テクノロジーと子育ての共存点

寝顔を眺めながらふと思う夜があります。この子が大人になる頃、AIはどんな存在になるのだろう。
危険を過剰に警戒して可能性を摘むより、リスクを理解した上で可能性を育む勇気。
妻が子供の転びそうな場所にクッションを置くように、私が自転車のヘルメットを調節するように、デジタル世界にも適度なクッションと緩衝材を。
テクノロジーの発展と子供の成長は似ています。完璧を求めず、でも手を抜かず、今日も少しずつ前進していくことが現代を生きる親の役目なのかもしれません。
リビングで充電中のタブレットの明かりが、柔らかな夜の帳りの中で、家族の新しい形をそっと照らしているようで。
出典:Globe Newswire(2025年9月30日)
