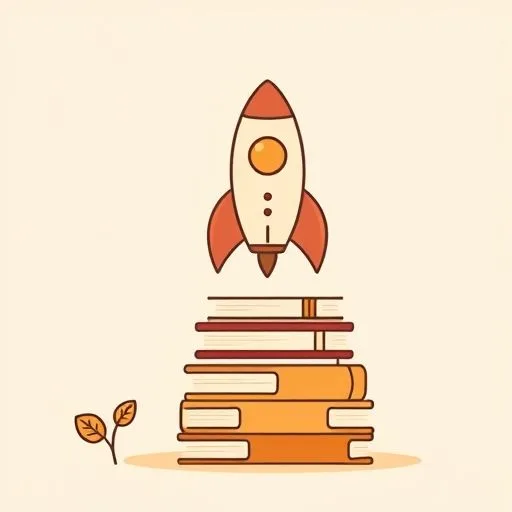
先日、娘が学校から持って帰ったアサガオの観察日記を見てハッとしました。2週間前に種をまいたばかりなのに「どうしてまだ花が咲かないの?」とイライラしていたのです。それを見た瞬間、私の職場で続いていたAI導入プロジェクトの失敗が頭をよぎりました。まさに同じ失敗をしていたんです!
実は、Forbesが2025年9月16日に報じたところによると、AIプロジェクトの失敗の多くは、焦って土台作りを怠ったことに起因するそうです。なんと企業のAIプロジェクトの約80%が成果を出せずに終わっているというから驚きですよね!これはまさに子育てそのもの!
今日は、皆さんにぜひ知ってほしい、データ管理が離乳食作りに似ている理由や、子どもの好奇心を育てる接し方がAI活用のコツに通じる意外な関係について、ワクワクしながらお話しさせてください!
「まだ咲かないの?」アサガオを引っ張る子どもたち~企業のAI導入失敗パターン~
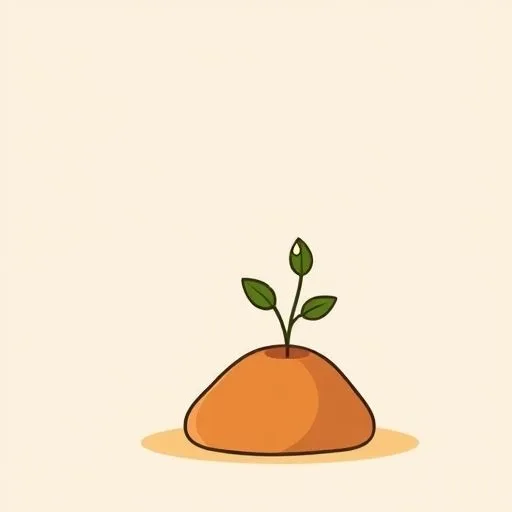
娘が毎日水をやりながらアサガオの鉢を揺らしていたのが思い出されます。「早く芽を出せよ~!」と言わんばかりに。この光景、実は企業のAI導入失敗例とそっくりなんですよね。
専門家の調査によると、多くの部署が「とにかく急いで成果を出さなきゃ!」と、データの整理整頓も中途半端なまま華やかなAIシステムだけを導入しているそう。それがまるで、土づくりも肥料も十分でないのに「なぜ花が咲かないんだ!」と怒る子どもと同じ状態だと気づいたんです。
ある税務部門の事例では、部署内のデータが古いフォーマットでバラバラなのに気づきながら、とりあえずAIを導入。結果的にシステムが正確な分析できず、かえって作業時間が増加したそうです。これは家計簿をつけるときに、レシートをぐしゃぐしゃにポケットに入れたままで「アプリで自動計算!」と期待するようなものかもしれませんね。
離乳食作りが教える「下ごしらえ」の重要さ~AI成功のカギはデータ整理~
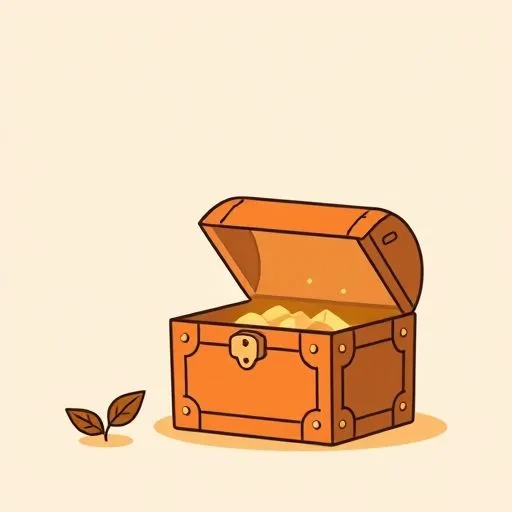
我が家の離乳食作りで学んだことがあります。茹でた野菜をスムーズにペーストにするには、品種選びから皮むき、火加減まで全てが重要だと。AIプロジェクトのデータ整理も全く同じだと最近気づきました!
成功している企業のCTOの80%が「最初の3ヶ月はひたすらデータのクリーニングに費やした」と回答しているのです。
子どもに新しい習い事を始めさせる時、いきなり本格的な道具は買いませんよね。まずはお試しレッスンで様子を見る。AI導入もまさにそれです。特に会計データは、昔の紙の帳簿からExcelデータ、クラウドシステムまで形式が混在しがち。まるで我が家の冷蔵庫で、瓶詰めベビーフードと手作りストックが入り混じっているような状態です。
砂場遊びに学ぶ「小さな成功体験」の積み重ね~焦らず一歩ずつ進むAI活用術~
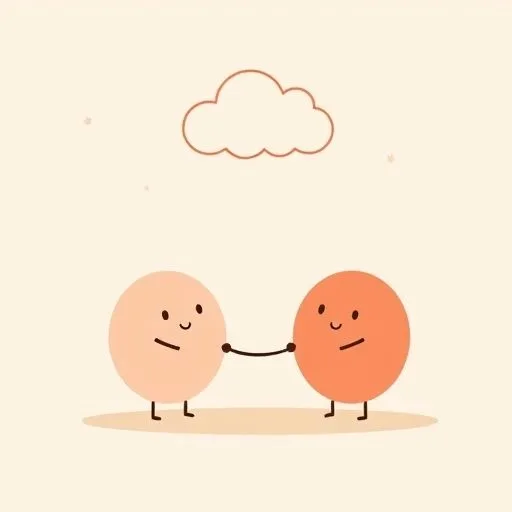
公園の砂場で、娘が小さな山を作るところから始めて、最後には立派な城を完成させるのを見ていて気づきました。実はAIプロジェクト成功の秘訣も「小さな山から始めること」らしいのです!
あるグローバル企業では、最初に「メールの自動仕分け」という小さいタスクからAIを導入。成功体験を積んでから本格的な経理処理に応用したそう。幼児教育で「今日はクレヨン1本でいいから絵を描こう」と小さな目標から始めるのと同じですね。
特に日本企業は完璧を求めがちですが、AI活用は「75点主義」で臨むのがコツ。これは、完璧を目指さなくても大丈夫、という考え方です。まずは部署内で使えるデータを部分的に整理し、1つの業務からデジタル化してみる。それが砂場で小さなトンネルを掘るような成功体験につながります。
「できない」を「やってみよう!」に変える魔法の言葉~人的サポートがプロジェクトを成功させる~

娘が自転車の補助輪を外した時、ただ「頑張れ!」とだけ応援するのは逆効果だと学びました。最初はサドルを支えながら「右足こいで!」と具体的な指示が必要でした。AI導入における人的サポートも全く同じだと調査結果が示しています。
一つの事例では、AI導入に抵抗感のある社員に対して「このツールがあなたの残業時間を2時間減らせます」と具体的なメリットを伝えたところ、導入スピードが3倍に向上したそう。
第2のデジタルデバイドが生まれないように、教育現場ではAIリテラシーが重要と言われますが、企業でも同様です。AIを「怖いもの」ではなく「新しい文房具」と考える環境作り。子どもに「保育園で使うクレヨンは何色が好き?」と聞くように、社員に「AIに任せたい業務はどれ?」と質問することから始めるのが効果的かもしれません。
