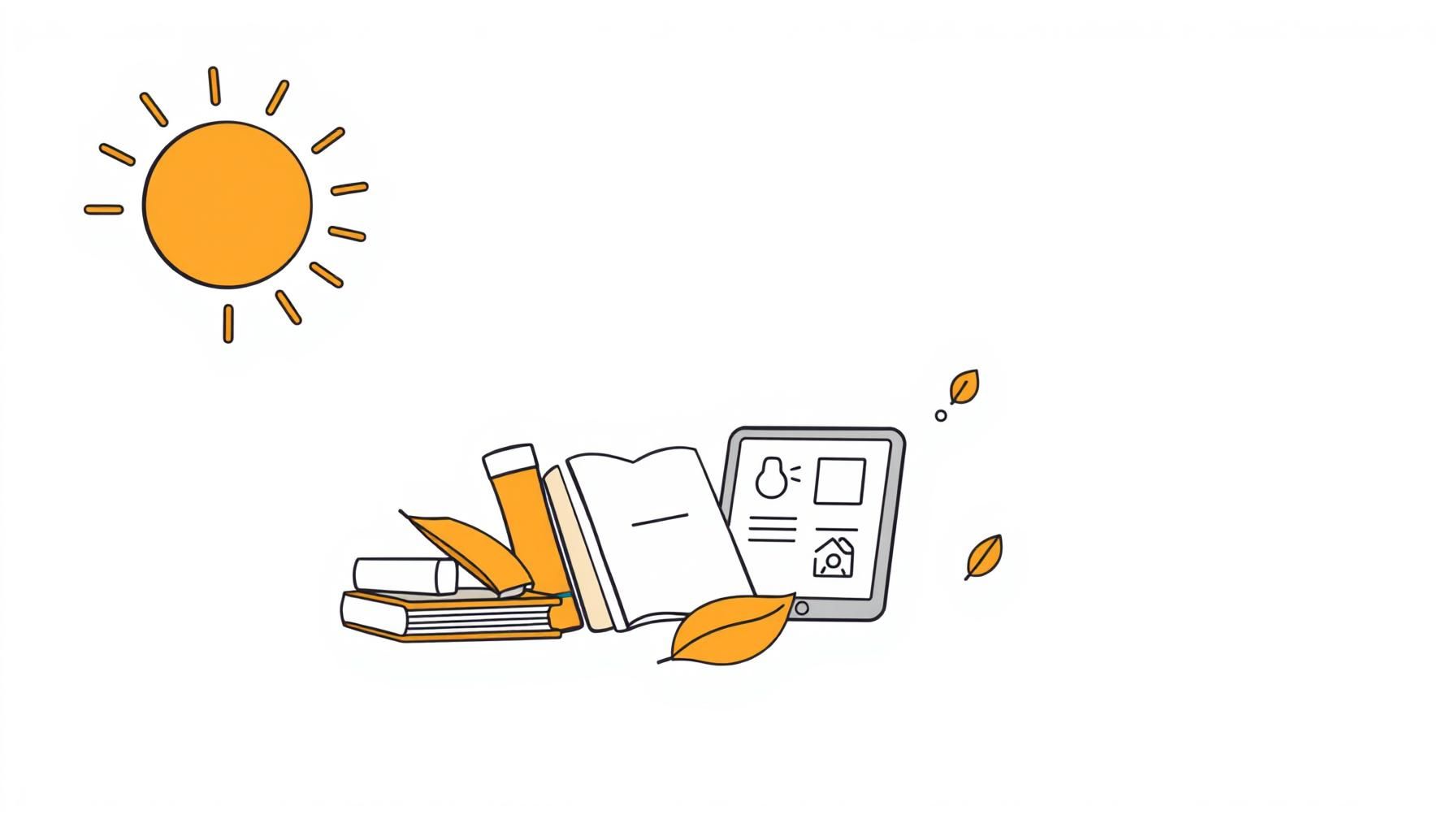
真夏の蝉しぐれが響くなんて日には、カナダの教育現場が動き始めているってニュースを見て「ああ、そうか…未来の学び方にも『温かい活用』ってものがあるんだな」と痛感するんですよ。うちの7歳娘が宿題中にAIアプリでお絵描きしててさ、やっぱ「学校の教育」と「家庭の関わり」のちょうど良いバランスってどうすればいいんだろうって悩みませんでしたか?
無責任な依存じゃなく、どう育む?

本当に最近だと、教育現場も家庭も同じようにAIとの付き合い方を模索してる気がします。例えばさ、うちの子が『AIで夢日記を描いた』って誇らしそうに持って来たときのこと。悪気があるわけじゃなくて、単に『AIとかの便利さ』に惹かれてしまうのはわかりますが、でも怖いのがその無意識な使い方じゃないですか?「何を使うか」よりも大切なのは「どう使うか」みたいな意識を育てるために、親子でナチュラルな会話をしてることが大切かなって単純に思ったりします。
家族で作るルールで芽を伸ばす
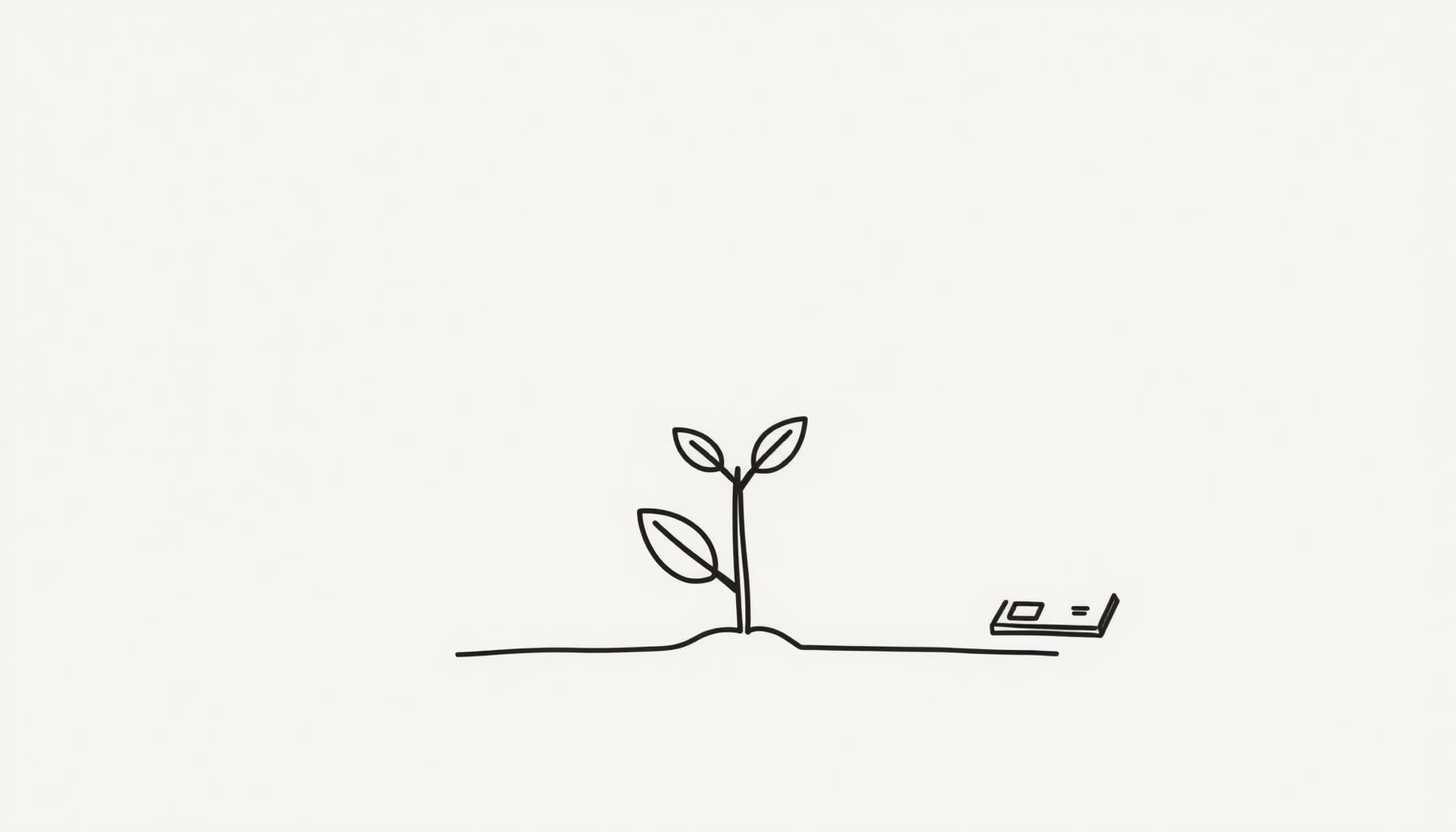
そんな中で気がついたのが、娘と私がAI絵アプリでけん玉のようにやり取りした時のことです。いくつか教えたルールを守らせた結果、AI補完機能を自由に活用しながらも「手書きで隙間を思い描く」動作が生まれたんです。こうした小さな瞬間って、AIだけでなく家族との価値観をどう『みんなで考える』かって、肝心な時間町ではないかと思います。
暗記より、すべては共創から

日本の小学校でも短期記憶よりもAIと『共に作る』発想を大切にする動きが出てきたとか。できる限り手書きの価値を感じさせようと、うちの子の音楽レッスンでも対話を重ねてます。AI楽譜よりね、「ちょっとひと筆足してみよう?」って手作り感を気づかせることで、彼女の音楽への探究心が笑顔でもっと深くなったんですよ。たかが小学校でもしれっと家庭の務めはこんなところにあるかもしれません。
静けさと向き合うことの価値
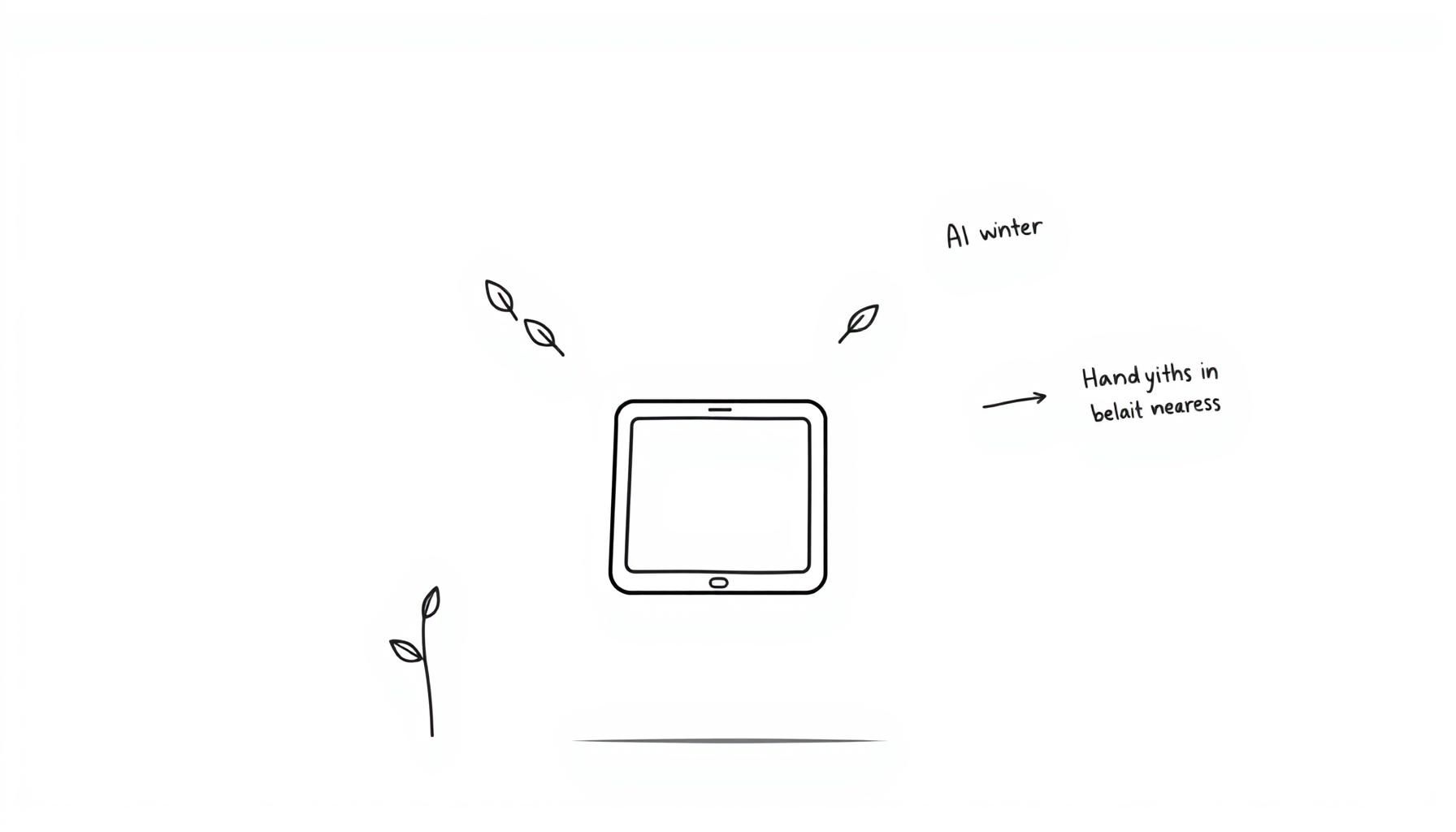
前にも言ったかもしれませんが、これからの時代のAI活用に必要なのは信頼とバランスですよね。娘が「AIで描いた絵じゃつまらない」って衝撃的な一言を放った瞬間、彼女の瞳にはAIという冷たい技術より“家族”的なぬくもりを自然と求めるような深い気づきを垣間見ました。今の子たちにAIに振り回されない力は、こうした静かな家庭の時の中で培われるのかな。
未完成な今の暮らしを〈芽〉にする
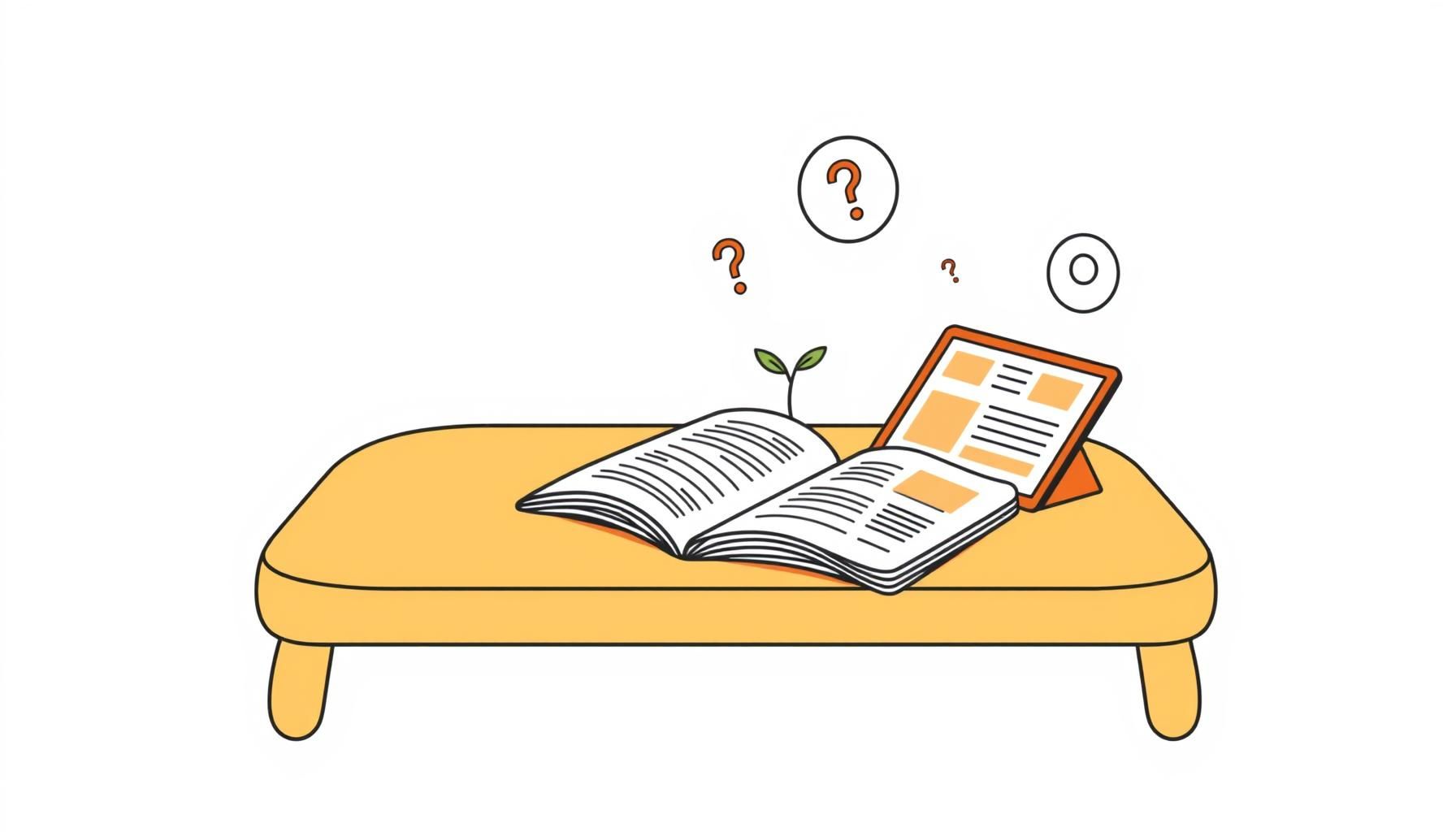
実は教育指針が固まるまでは「まだ模索中」の段階。だからこそ、今夜もアイツとニュース記事で一緒に議論してたんです。「もし先生がAIで授業を作ったらどうしたい?」って質問を娘に向けたら、「じゃあ、お父さんと作った方がいいよね!」って照れ笑いで返してきました。時に、こうした風景こそが時代の変化を家庭で『生温かく』乗り越えるバロミーターかもしれません。
温かい活用がどう言うことか?
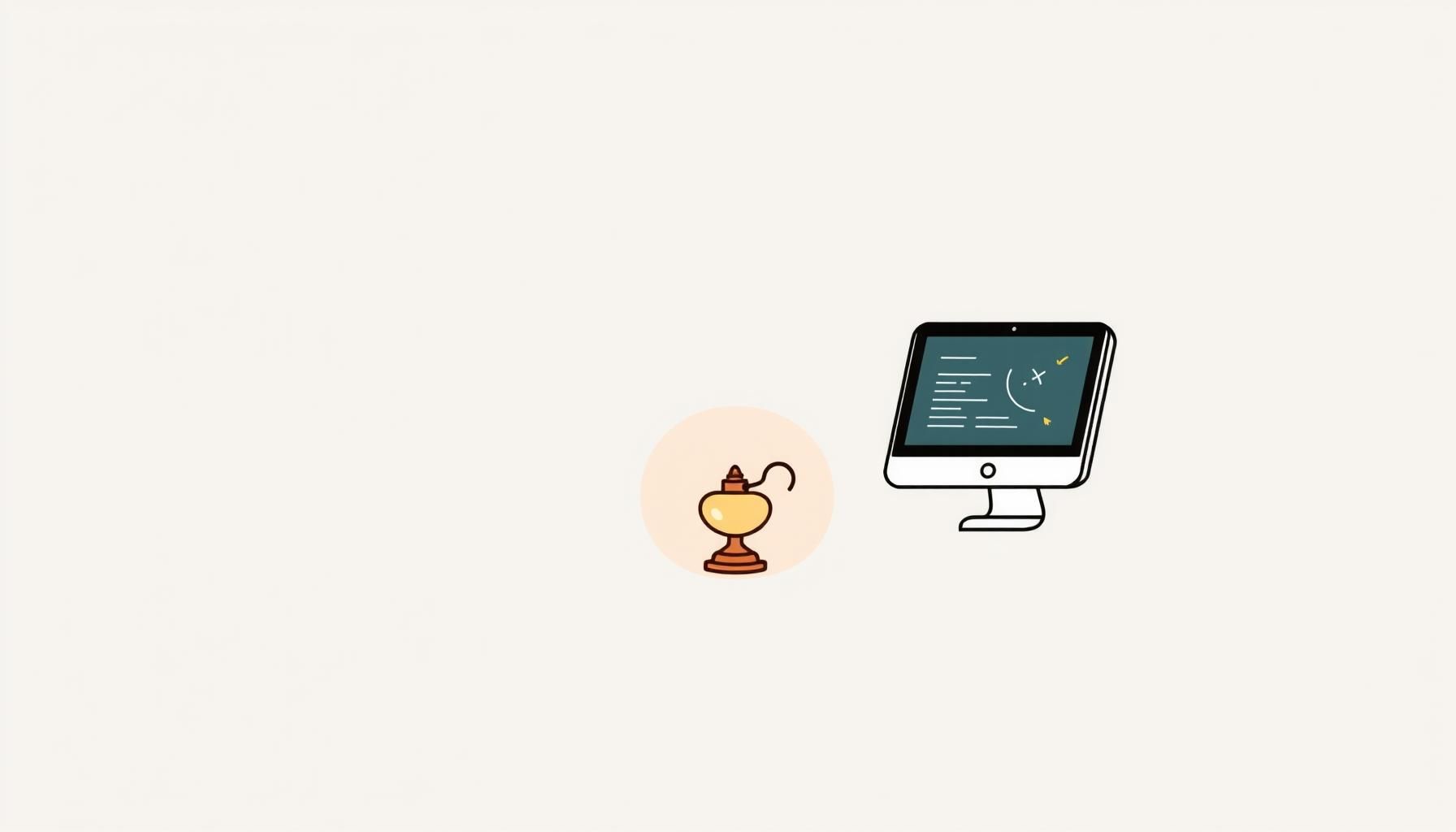
そう言ってるうち、娘が『消しゴムとAI描画の違い』まで話し始めました。さあ、「AI禁止」なんて殺風景な対応より、「アナタの描きたいこと、広げて׃頭のリミッターはずしてみない?」って柔らかく子供たちと向き合う姿勢がきっといいんだと思います。最終的には、「嘘のデータに気づくチカラ」が必要ってことに気づきませんでしたか?私たち親世代にはAIに無法な『生きる知恵』がどう主流になるのか、近所の街灯に向けていろいろ考えること。そして示唆する価値があります。
Source: マニトバ州でも今後の導入を検討中, 2025-08-15
