
最近、インドネシアの教育副大臣アティップ・ラティプラハヤト氏がAI教育に関する面白い発言をしていましたね。「AIは単なる必要性ではなく、未来への義務である」と。これ、すごく共感できるんです。だって、子どもたちが生きる未来では、AIは空気や水のように当たり前になるでしょうから。
さて、創新性について考えてみましょう。
なぜ創新性は子どもを「替えのきない存在」にできる?

副大臣は大学卒業生に向けて「創造力を生かせば、替えのきない存在になれる」と語っていました。これ、子どもたちにも通じることですよね。AIがどんどん発達しても、人間らしい創造力や独創性は代替できないからです。
お子さんの創造力、どう育んでいますか?
例えば、うちの娘が最近、ブロックで飛行機を作るのに夢中なんです。副大臣が例に挙げていた「アルミニウムが飛行機に変わる」という創新の話を思い出しました。原材料はそのままでは価値が低くても、人間の創造力で高価値なものに変えられる——子どもたちの遊びや学びにも、同じことが言えるんじゃないでしょうか。
AIはあくまでツール。それをどう使うかは人間の創造力次第です。子どもたちがAIと一緒に何かを生み出す力を育むことが、これからのAI教育で大切なんだなと感じます。
AI教育を「楽しみ」に変えるには?

副大臣は「AIが人間の存在を消す技術を作ることはない」とも語っていました。確かに、AIは私たちを助けるためにあるのであって、脅かすためにあるわけじゃありません。
子どもたちとAIの付き合い方も、同じですよね。怖がらせるのではなく、楽しみながら学べる環境を作ることが大事。例えば、AIを使って一緒に絵を描いたり、物語を作ったりするのはどうでしょう?うちでは時々、AIが提案するお話の続きを考えながら、親子で創作遊びをしています。これがまた盛り上がるんです!
AIを「敵」ではなく「味方」として捉えることで、子どもたちの世界はもっと広がるはずです。
AI教育で人間らしさを育むバランスの取り方は?

インドネシアではAI教育を選択科目として導入し、学生が時代の進歩を掌握できるようにする方針だそうです。これってすごく賢いアプローチですよね。
子どもたちにも、テクノロジーと人間らしさのバランスを学んでほしい。AIを使いこなすスキルも大切だけど、同時に情緒的な知性や誠実さ——副大臣が言う「高貴な性格」も育てることが重要です。
週末にはなるべく画面から離れて、公園で走り回ったり、友達と一緒に工作をしたりする時間も大切にしています。AIは便利なツールですが、それだけに頼らない豊かな体験が、子どもたちの人間性を育むのだと思います。
未来を生きる子どもに必要なAIとの付き合い方とは?
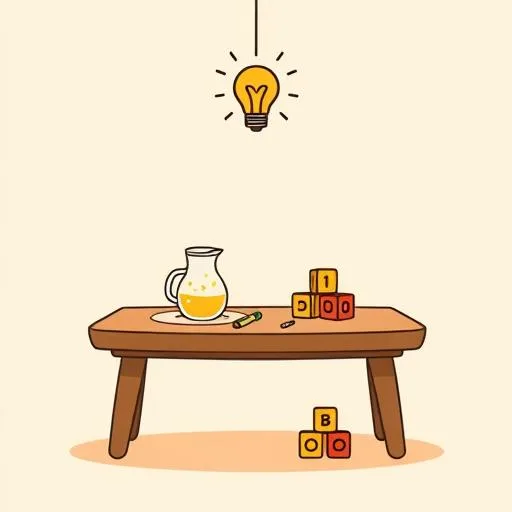
結局のところ、AI教育で一番大切なのは「人間らしさ」を忘れないことかもしれません。インドネシアの大学学長も「称号だけでなく、意味や価値を追求する真の学習者であれ」と卒業生に語っていました。
子どもたちがAIを使いこなす技術者になるだけでなく、創新性と思いやりを持った人間に成長してほしい——それが親としての願いです。
最後にひとつ、家族でできる簡単なアイデアを。夕食の時間に「AIが今日一番感謝したいことは何?」と問いかけてみてください。子どもたちの答えから、また新たな会話が生まれるかもしれませんよ。それでは、素敵な家族の時間をお過ごしください!
ソース: Indonesia: AI a must, not a threat, deputy minister says, Antara News, 2025/09/06
