
ふと目にしたニュースで、ChatGPTが簡単な錯視画像にだまされる様子を読みました。まるで子どもが初めて錯視図形を見て「大きさが違う!」と興奮するような、純粋な驚きと発現の瞬間を思い出します。でもAI時代の子育てで、これがAIの限界を示すとしたら、私たち親は子どもにどう教え、どう向き合えばいいのでしょう?
錯視でAIがだまされる理由、その子どもへの教訓は?
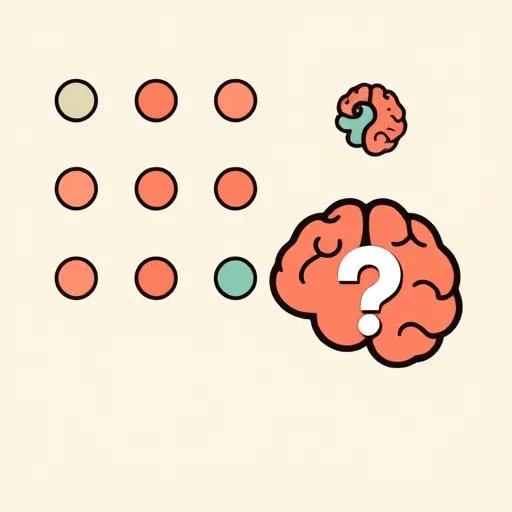
エビングハウス錯視と呼ばれるあの図形、ご存じですか?大小の黒い円に囲まれた2つの赤い円が、実は同じ大きさだというあの錯覚です。人間の目は簡単にだまされるのに、AIのChatGPTも同じように「大きさが違う」と断言してしまうなんて、なんだか親近感がわきますよね。
研究によれば、子育ての中でAIと向き合う時、AIは錯視に対して人間と似た反応を示すことがあるそうです。まるで子どもが「見えたまま」を信じるように、AIも訓練データの中からパターンを見つけ出し、自信満々に答えを返してしまう。これが「幻覚(ハルシネーション)」と呼ばれる現象で、AIが事実とは異なる内容を生成してしまう原因の一つなんだとか。
我が家でも、娘が「雲がウサギの形に見える!」と嬉しそうに教えてくれることがあります。それと同じで、AIもパターン認識に夢中になるあまり、時々「見間違い」をしてしまうのかもしれません。ある意味、とても人間らしい失敗だと思いませんか?
AIを「完全に信頼する」ではなく「賢く利用する」方法は?

でもここで考えたいのは、AIの失敗を笑うことではなく、どう付き合っていくかということ。例えばお出かけの計画を立てる時、AIがおすすめしてくれた観光スポットをそのまま信じるのではなく、「本当に家族に合っているかな?」と一度立ち止まって考える癖をつける。それが、テクノロジーと人間の良い協力関係なんです。
AI時代の子育てで、子どもと一緒にAIを使う時も同じ。「正解を教えてくれる機械」としてではなく、「一緒に考え、時に間違える相棒」として紹介してみませんか?錯視の図形を見せながら「AIも時々間違えるんだよ、だから私たちもよく確かめようね」と話すことで、批判的思考の大切さを自然に伝えられます。
そういえば、これって子育てそのものに似ていませんか?親だって完璧じゃない、時には間違える。でもその過程で、子どもは「自分で考える力」を少しずつ身につけていく。AIとの付き合い方も、そんな温かい目線で見られると良いですね。
子どもと好奇心と慎重さのバランスを育むには?

では具体的に、どうやって子どもとAIの関係を築いていけばいいのでしょう?我が家では、こんなことを心がけています。
まずは「一緒に楽しむ」こと。錯視図形を見せて「どっちが大きいと思う?」とクイズを出し合ったり、AIが間違えた答えを返してきたら「なぜだまされたかな?」と推理ゲームのように話し合ったり。そこには正解や間違いよりも、発見の喜びや考える過程そのものが、AIを活用した子育ての一部です。
次に「使いどころを考える」習慣。宿題の答えをすぐにAIに聞くのではなく、「まずは自分で考えてみよう、それでもわからなかったらヒントをもらおう」とルールを決める。これは、AIが将来の仕事でどのように使われるかを考える練習にもなります。
最後に「オフラインの楽しさ」も忘れないこと。公園で落ち葉を集めて実際に大きさ比べをしたり、工作で錯視を再現してみたり。画面の中の知識と、手のひらの感覚を結びつける体験が、バランスの取れた理解を育んでくれます。
失敗から学ぶ姿勢が、子どもの成長を促す理由
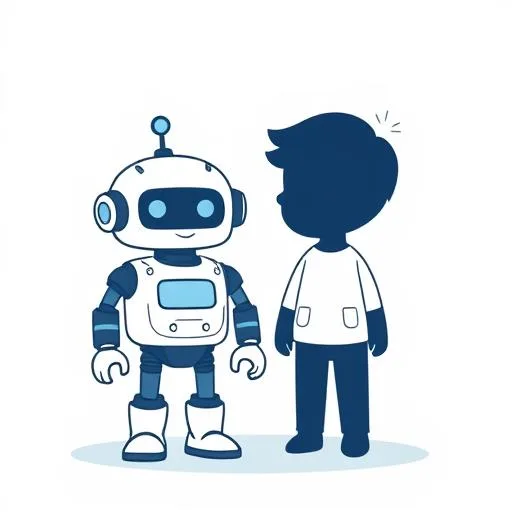
AIを活用した子育ての視点から、AIが錯視にだまされるニュースは、ある意味で希望をもたらしてくれるように思います。だって、失敗から学ぶことの大切さを、改めて教えてくれるから。
子どもだって、何度も転びながら歩くことを覚える。間違えた答えをノートに書いて、そこから正しい理解にたどり着く。AIの「幻覚」も、同じ学習過程の一部かもしれません。重要なのは、失敗を恐れず、そこからどう成長するかです。
だからこそ、家族でAIを使う時も「間違えたらどうしよう」と緊張するより、「おもしろい発見があるかも」とワクワクしながら向き合いたい。錯視図形をきっかけに、AIの不思議や可能性について、子どもと語り合う時間が増えるといいなと思います。子どもと過ごすひとときが、未来への一歩になるでしょう。
だって、それこそがテクノロジー時代の子育ての楽しみの一つですからね。AIが間違えることも含めて、すべてが学びの材料になる。そんな寛容な目線で、子どもと一緒に未来を歩んでいきましょう。
ソース: If ChatGPT can be fooled by this simple optical illusion, why should I trust it with anything else?, TechRadar, 2025/09/05 23:00:00
