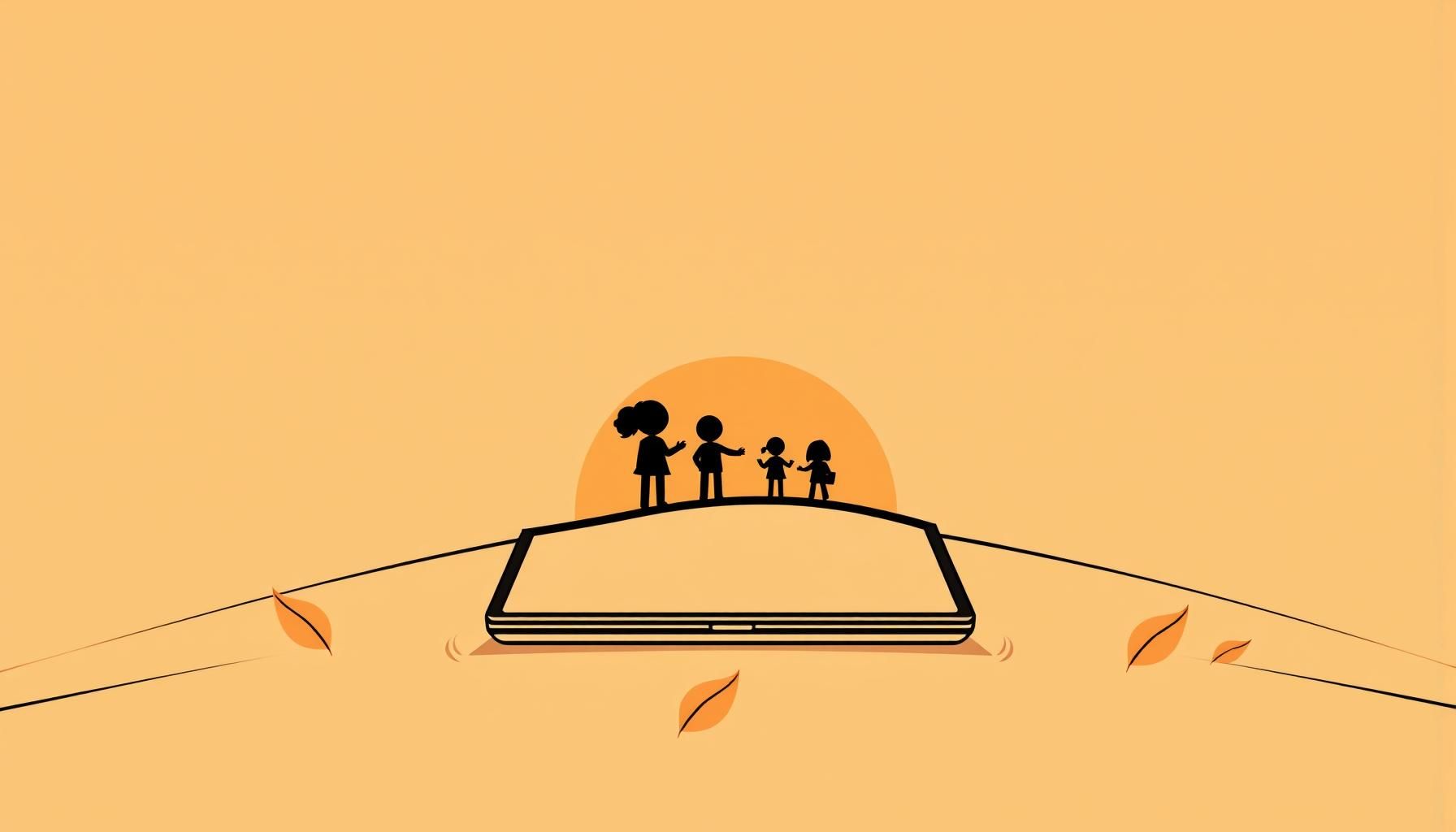
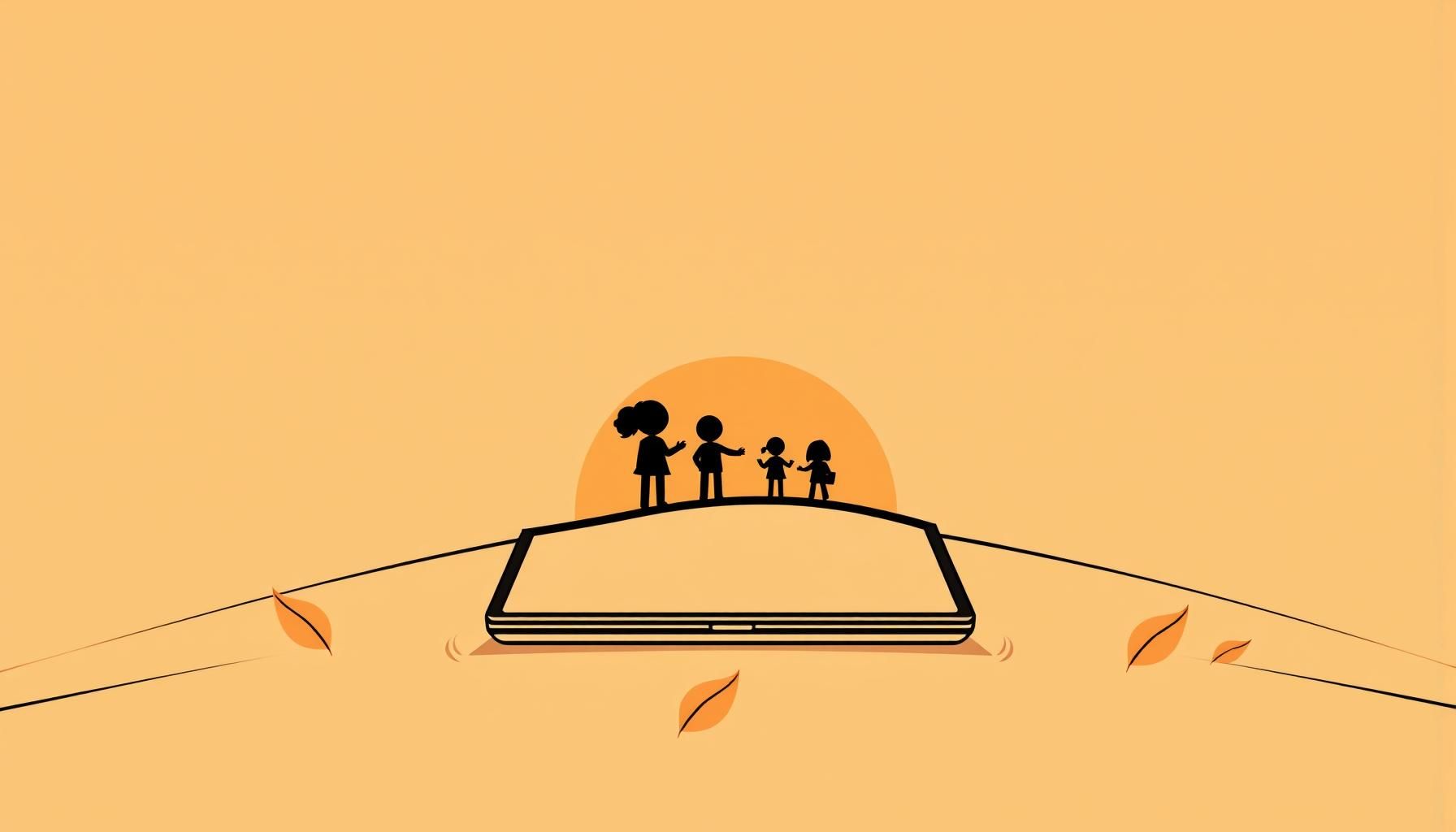
最近、娘が夕焼けを見ながら『なぜ空が赤くなるの?』『蝉の声はどうやって生まれるの?』と連続で質問してくるディスカッションがありました。この好奇心の連鎖がAI教育にも共通する部分があるんですよね。
対話式AIが問う|子どもの探究心をどう育む
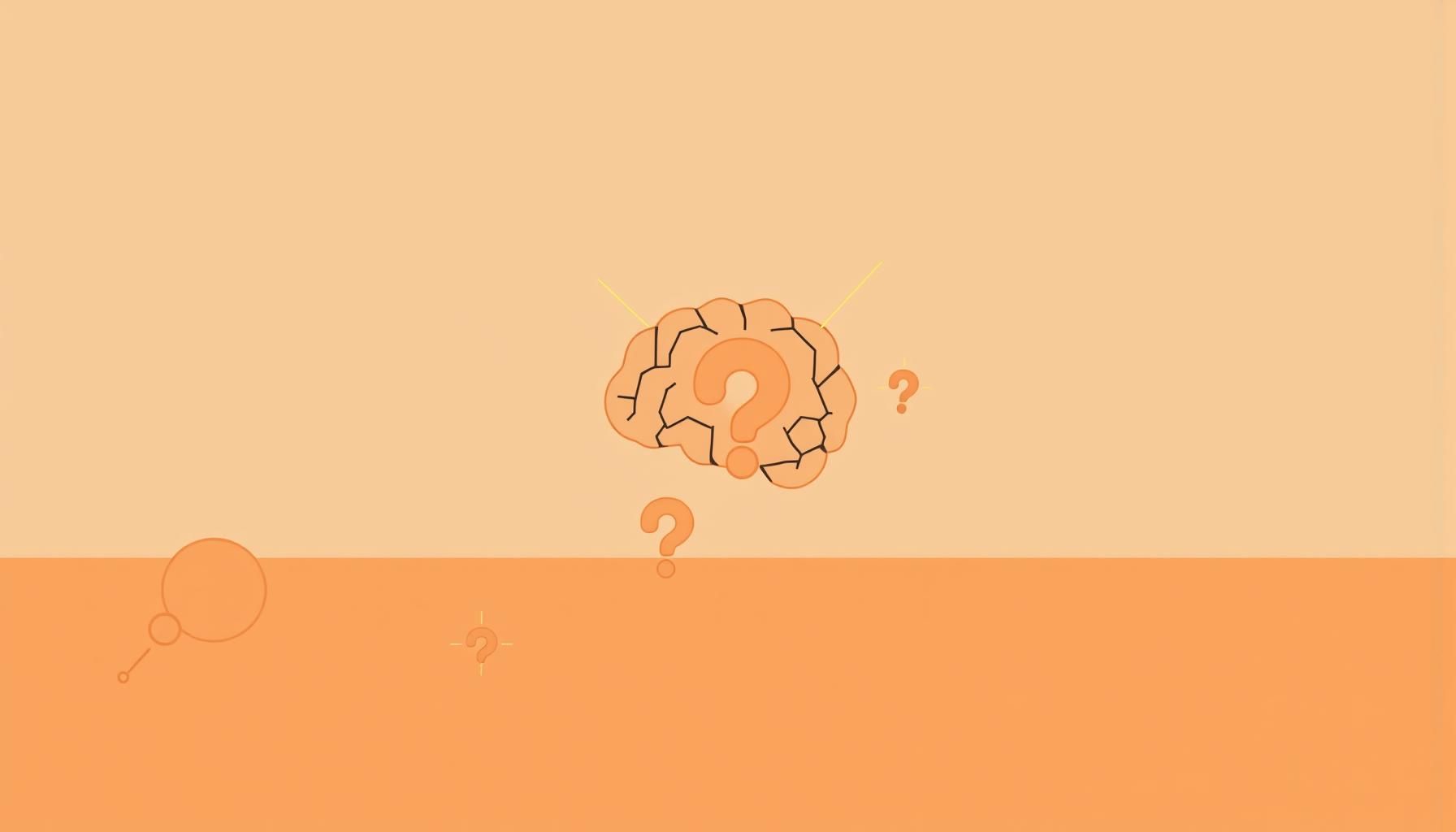
娘の『何で?』攻撃が空を裂くように広がる様子をSocratic法の教育現場と比較してみましょう。ビルのピースが組み合わさるように、プログラム思考も自然と育まれていきます。
教育モードの親和性は、レコード針のようにスッと知識に触れること。我が家では朝食時間にiPadで新月の動画を観ながら、でも夕方にはテレワークの合間に蝉の抜け殻を観察する生活です。
“2019年米国教育技術学会”調査で73%の学生が理解深化を報告했습니다。文部科学省のデータでも56.3%が学習効果を実感しています
銀河の黄金比:子ども向けAI教育のバランス論
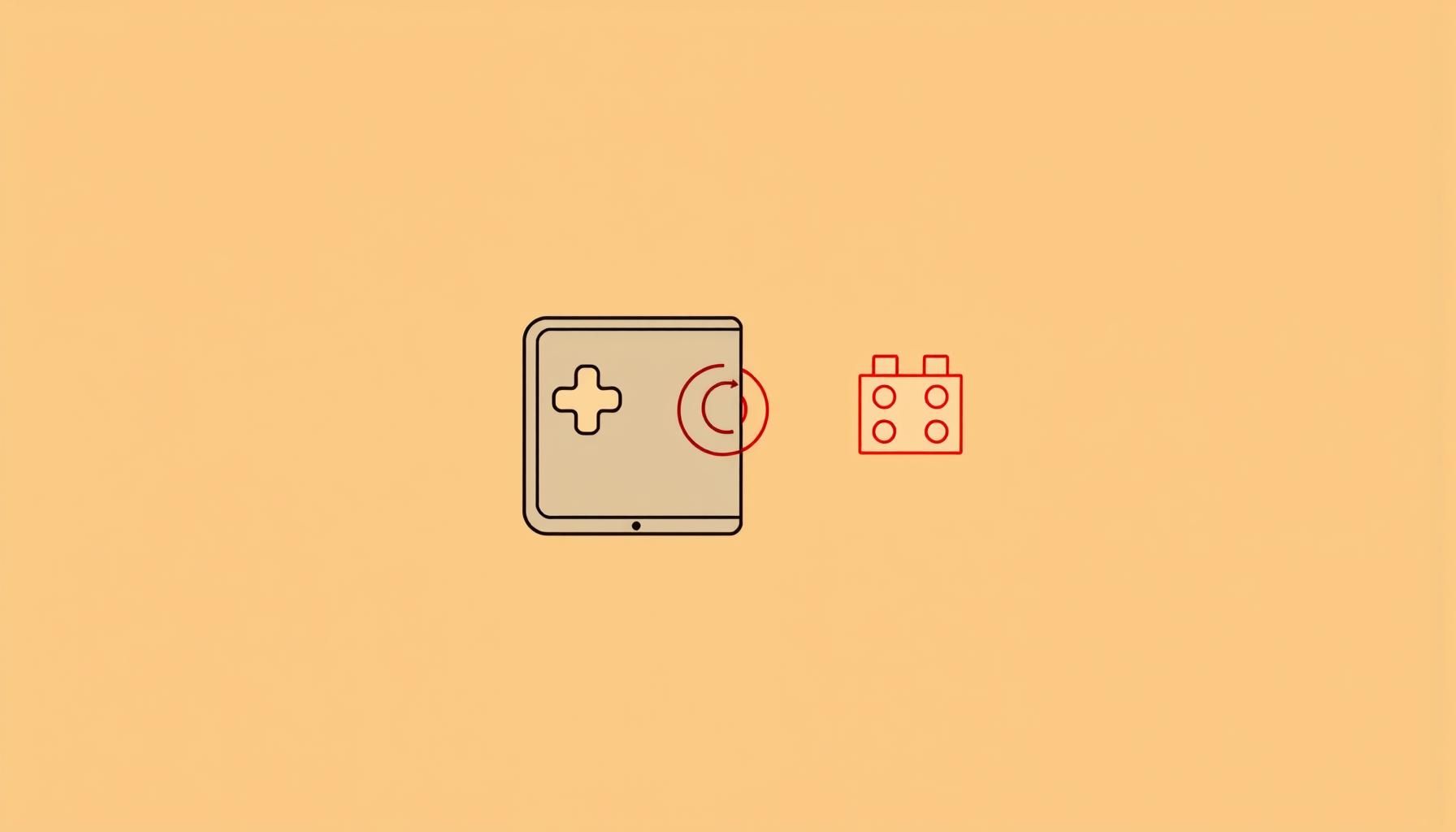
iPadの使い方については完全に放任するのではなく。スクリーンタイムとリアルの遊びを1:1.618の黄金バランスで。
娘の学校では初夏に多文化ルーチンを取り入れたプログラミングワークショップがありました。フラワーアレンジのようにビジュアルコークスで考えていたのが印象的です。
ロボ相撲と未来学習:AI導入の遊び心教え方
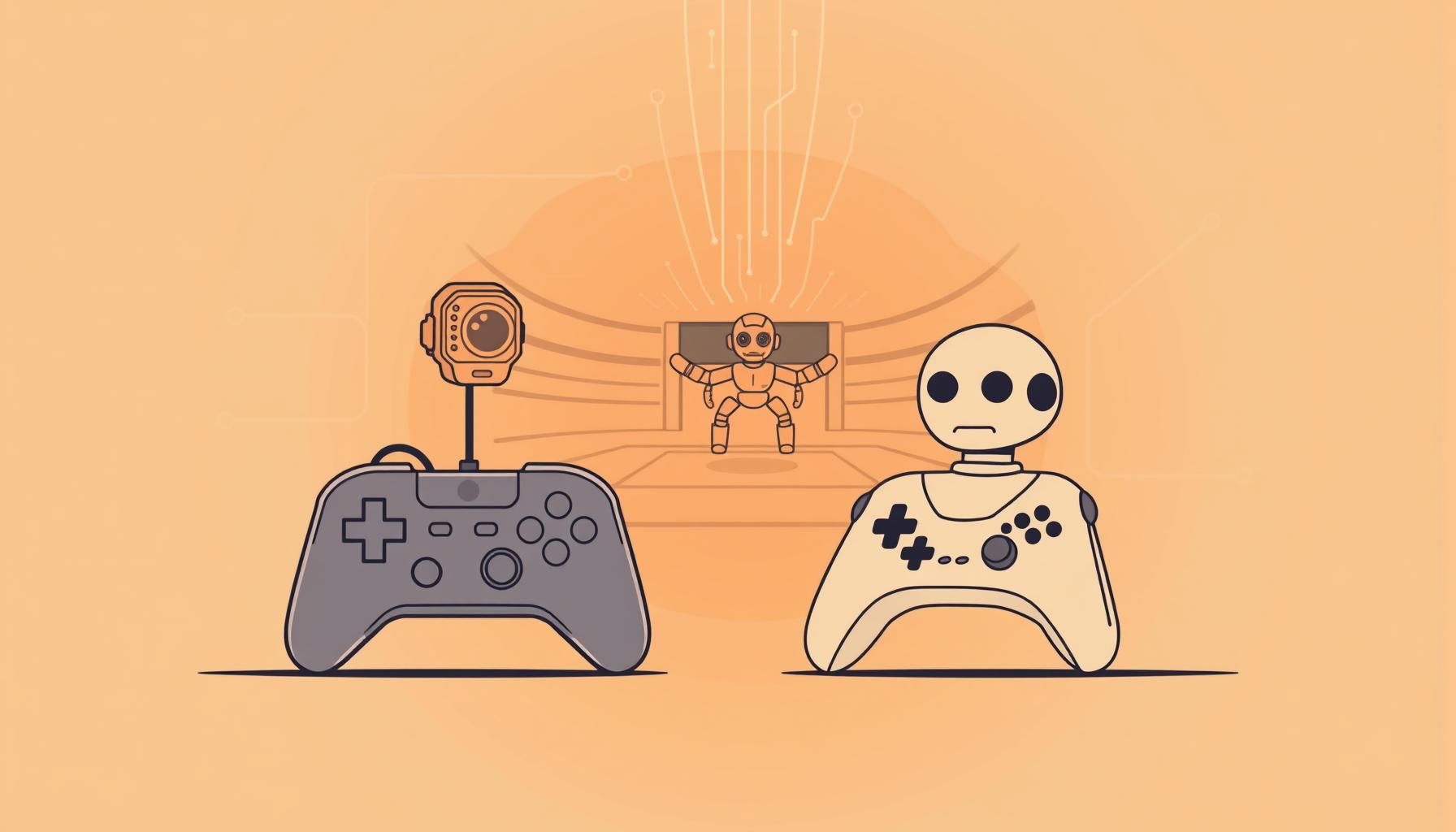
- まずは根拠に基づいた議論の考え方から
例えるならお絵描きの前に配色理論を教わるようなもの。7歳の子どもがAIと向き合う際は話し合いながら自然体で。
- レトロゲーム的導入法
過去の経験が活かされるニューテック活用法。学校帰りのプチ散歩中によく昭和ゲームの話題が出てきます。
- 新時代の「付箋学習」
クードゥで物語の流れをまとめてもらったら?娘は反復のシャドーワークより pundektor的視点を豊かにする方を歓迎しますよ。
AIリスクと家族の絆|安全を守る伝統流儀

娘と一緒に作るPBSLAB計画をご存知ですか?実地測量の経験とAI相談をミックスする「新・地図活用法」です。
ポケモンGO世代が学ぶウェルネスコントロール。我が家では「QUITボタン」ではなく「お月見タイム」の習慣づけが基本です。
心に響くAI導入|振り返りの時間

娘と蝉のメカニズムを追いかけていたある夜、改めて気づいた大切なこと――これはアケミックな方法よりファミリーのディスカッションこそが真の未来教育だということ。
プログラミング学習もロボット相撲大会と同じで。ルールは知っていても、相手の動きに合わせる《応用力》が勝負ですからね。
