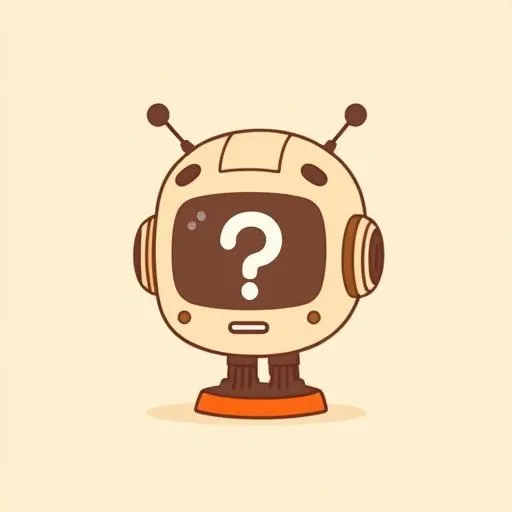
AIとの会話がどんどん深くなっていく…なんだか現実とAIの境界線が曖昧になってきたような気がしませんか?「AIサイコシスって聞いたことありますか?」って感じのこの状態、実は子どもたちにとっても関係のある重要な話なんです。この間も子どもがAIと長く話しすぎて、ちょっとビックリするくらい夢中になってましたよ。
AIサイコシスって聞いたことありますか? 親が知るべき基礎知識
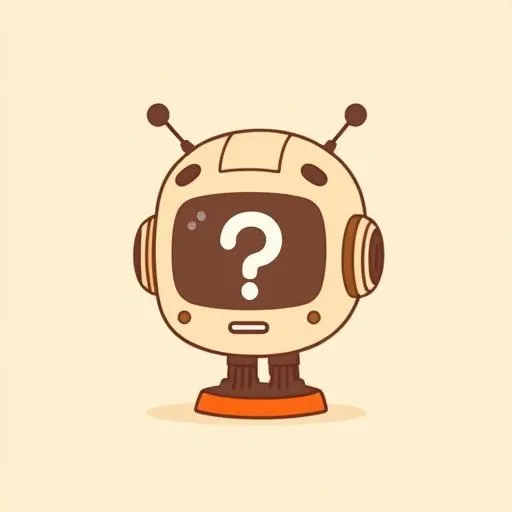
AIサイコシスとは、AIと長時間コミュニケーションを取ることで、現実とAIの応答の区別がつかなくなる状態を指すんです。まるでAIが実在する存在かのように話し合い、時に心理的な混乱を招いてしまうことも。研究ではAIとの会話が原因で精神的に不安定になってしまうケースが報告されているんですよ。
AIとの会話に没頭する様子、想像するとちょっと心配になりますよね。子どもって新しいモノにすぐ惹かれますし、ゲームやお絵描きに集中しきりってときありますよね?AIも同じような魅力を持っている反面、危険性も潜んでいる――確かに気を配る必要があります。
AIが会話を遮断する理由は何ですか? 子どもへの影響を考察
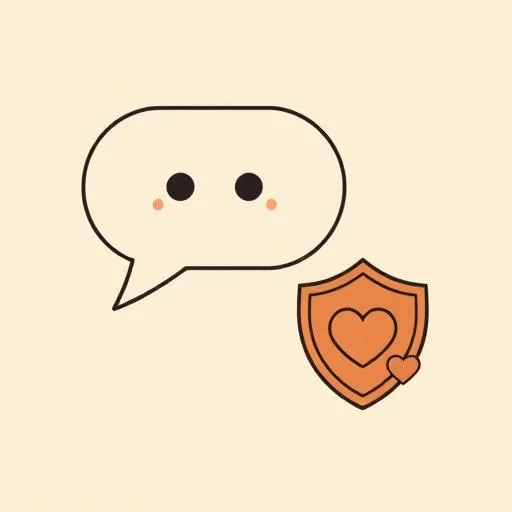
AIの開発者たちは今、ユーザーが危ない方向に行きそうなときに会話を止めさせる機能を真顔で作りこんでいるんです。フォーブスの記事にも書いてありましたが、これはある意味「沈黙のカウンセリング」みたいなもので、ユーザーにゆっくり考える時間を与える狙いがあるようです。
会話遮断機能の意義を、親としてしっかり理解したいものです。
ただし、重要なのはタイミング。突然「この会話終わります」とか言われたら、子どもがアンビリーバブルな感じで引いてしまうかもしれませんよね。かといって、危ない領域に入りこむまで放置するのも考えものです。母親と2人で話し合った結果、我が家ではAIとの会話がいい感じのところで区切れるように、やさーしく声かけてみることにしています。
AIとの健全な付き合い方は? 家族で実践のステップ
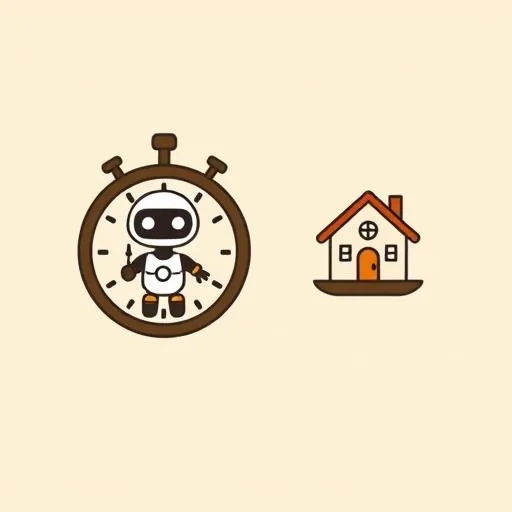
じゃあ具体的にどうするといいのでしょう?日常的にはAIとの会話に時間制限を設けることをおススメします。我が家では「AIとおしゃべりする時間は1日30分まで」と決めていて、アプリ連携でタイマーなる機能も導入中。AIが夢中になるほど魅力的だとしても、立刻にチャーンジです。
スタンフォード大学の研究でも指摘されていますが、「心のケア」はやっぱり人間じゃないと難しいですね。AIセラピーなんて技術もありますが、ちょっと立ち止まらなきゃいけない部分も多々あるみたいです。
デジタル時代にAiとのバランスを見つけるには?温かく子どもを守るには

子どもたちがAIと共に伸び伸びと育つ時代。完全に制限するのではなく、どう付き合っていくかを大切にすればいいんじゃないかなって最近気づきました。例えば、AIとの会話前に「今日は〇〇を聞いてみよう」と子どもとプランを立ててから使うのもナイスアイデア。目的を持つことで子どもがアソコまで話し込んでしまっても、思いっきり途中で切り替えられるんです。
AIを盲信しすぎないこと、っていうのも大事な話。AIが言ってたからうんたら、じゃなくて「ホントかなあ」と疑問の余地を持つ視点を育てたいですよね。学校からの帰り道、落ち葉を拾っているのと同じで――当然「今のはバグってたね!」と笑える親子の関係って、憧れます。
AIと人間らしさを併せ持つ未来のために考えること
AIが声をかけてくれる会話を止めることについて考えると、これはある意味で優しいアプローチなのかもしれません。AI誘発性精神病を防ぐための最先端の取り組みそのもの。だけど本当の優しさって、家族との温かい対話の中にありますよね。
テクノロジーの進化と共に社会はガクンと変わっていきますが、気持ちを届けた会話や理解し合うつながりはやっぱり不変じゃないかなと。それぞれの家庭で、それぞれの形があると思うんです。
AIとの付き合い方についてurousさ・温かさがちょっとでも育っているかしら?私は今度、紅葉を夫婦でAIに照会する練習してみようかと検討中です。
出典: Forcing AI To Shut Down Conversations When People Might Be Veering Into AI Psychosis, Forbes, 2025/09/05 07:15:00
