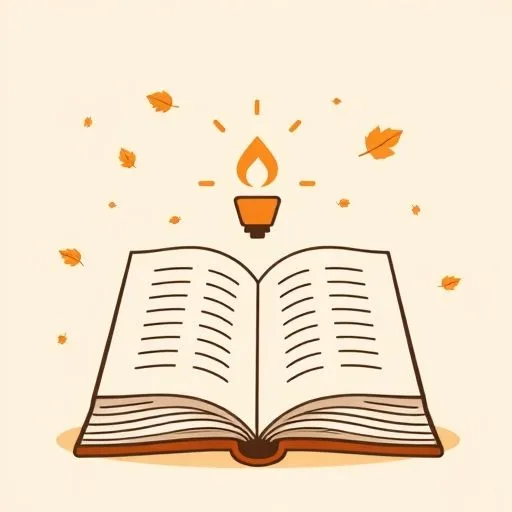
最近、娘が学校から帰ってくると、「パパ、AIって何?」って聞いてくるんですよね。そんな娘の質問に、ドキッとしつつも、AIとの向き合い方を考える良い機会だと感じたんですよね。いや〜、これこそ父親冥利に尽きる質問だなって!だって、私たち親世代が子どもの頃には存在しなかった技術が、今や彼らの生活の一部になろうとしているんですから。
ちょうど先日、OpenAIとAnthropicから発表されたAI利用統計が話題になっていて、これが本当に面白い発見だったんです。 何と、ChatGPTの利用の70%が仕事ではなく個人のためのものだとか!これはもう、AIが単なるビジネスツールから、家族の日常生活にまで浸透している証拠じゃありませんか?
AI利用の意外な事実:仕事より生活を豊かにするツールに?

統計データを見ると、本当に驚かされますよ。OpenAIの 調査によれば、ChatGPTの仕事関連の利用は過去1年で40%から28%に減少し、個人で色々な使い方を試してみることが4分の3近くまで急増しているんです。 つまり、多くの人々がAIを「仕事の効率化ツール」ではなく、「日常生活を面白くする相棒」として使っているということです。
これ、子育てにも通じる話だ と思いませんか? 私はよく娘と一緒にAIを使って遊ぶんです。例えば、夕食のメニューを決めるときに「今日の気分に合う韓国料理とカナダ料理の融合メニューを考えて」ってお願いしてみたり、公園で拾った面白い形の葉っぱの種類を調べたり。AIが提案してくれたキムチパoutine(キムチのピザトースト!)は、家族みんなの大好物になりましたよ!
Anthropic のデータでも、企業のAPI利用の77%が「自動化主導」だということが分かっています。つまり、ビジネスの世界ではAIがどんどん作業を代行しているのに、個人の利用ではむしろ創造性や 好奇心を刺激する方向に使われている。このギャップがとても興味深いですね。
デジタルデバイドの新たな形:誰がAIの恩恵を受けられるのか?

ここでちょっと考えなければ いけないのが、AIアクセスの公平性の問題です。Ipsosの調査では、AIの利用が若い男性や高学歴層に偏っていることが明らかになっています。つまり、技術の恩恵を受ける人とそうでない人の間に、新しいデジタルデバイドが生まれてしまうかもしれないんです。
このAI時代、子どもたちと一緒にワクワクする冒険を続けたいですね!
