
夕食の支度をしていると、ふとリビングから聞こえてくる子どもの声。「AIさん、ティラノサウルスはどうして絶滅したの?」。
画面に向かって真剣に質問する後ろ姿を見ながら、いつも思うのです。この子の好奇心の種は、どんな形で育っていくのだろうかと
もちろん、最初は戸惑いもありました。画面ばかり見せることで、子どもの思考力が奪われてしまうのでは、と。
でも気づいたんです。問題はデジタルそのものではなく、私たちの関わり方にあるのだと
今日は、そんな気づきの中で見えてきた、デジタルと共に歩む子育ての話をしてみたいと思います。
子育ての神話、一緒に考えてみませんか?

よく耳にする『画面時間=悪』という考え方。本当にそうでしょうか。
わが家で気づいたのは、一緒に画面を見ている時と、一人で見させている時の大きな違いでした。
あのね、子どもがゲーム実況を見ている時。「ママ、『respawn』ってどういう意味?」という質問が飛んできて、そこから英語の話に発展することがある。そんな時は、画面が会話のきっかけとなっているんです。
「AIが思考力を奪う」という意見もありますが、うちの子はAIに恐竜の生態を質問しまくって、そこから「なぜ?」「どうして?」とどんどん深掘りしていく。むしろ質問力がメキメキ育っている気がするんだよね〜。
この「デジタル採集×アナログ標本」方式、実は研究で記憶に残りやすいと言われています。
大切なのは、ツールをどう使うかなのだと気づかされました
家でできる小さな実験
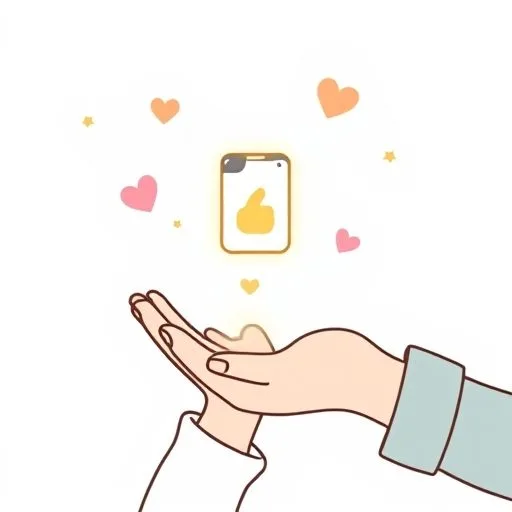
週末によくやっていることをご紹介します。まずは「15分間の探検タイム」。
Google Earthで世界を旅したり、料理動画を見ながら「今度作ってみようか」と話し合ったり。その後に、気になったことをノートに絵や文字で書き留めるんです。
ある時、空の色について質問されたことがありました。「ねぇパパ、どうして空は青いの?」。AIで調べた後、実際に夕焼けを見に行って、「じゃあ火星の空は?」「1億年前の地球の空は?」と想像を膨らませたことが。
そんな時、子どもの目が本当に輝いているのがわかります。
そして、「家族でふりかえりタイム」も習慣にしています。月末に「今月はどんな発見があった?」と話し合うと、子ども自ら「次の週末は公園に行きたいからスクリーンタイム減らそう」と言い出すことも。
少しずつ、自分で選択する力を育んでいるのかな、と感じています。
未来の学びの種をまくために
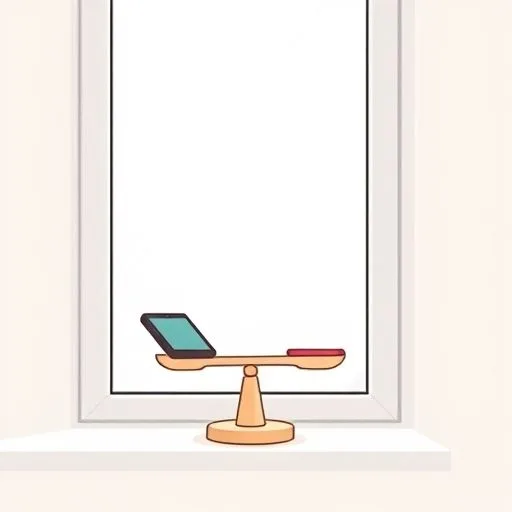
子育てをしていて実感するのは、デジタルと自然体験が意外につながっていることです。
森で珍しい虫を見つける時の目と、オンラインで新しい情報を見つける時の目が、とても似ているんです。
「『学びの体温計』という考え方。数字や時間で測るのではなく、子どもの目の輝きや「もっと知りたい」という欲求を基準にする。」
失敗しても大丈夫。「今月のスクリーンタイム、多かったね」と話し合った後、子ども自身で改善策を考えさせるプロセスが、実は大きな学びになっていると気づきました。
もう一つ嬉しい発見が、祖父母とデジタルを通じて繋がる方法。「スマホ孫先生プロジェクト」と呼んでいるのですが、子どもが祖父母にスマホの使い方を教えることで、異世代交流が自然と生まれるんです。
小さな気づきが、いつかどんぐりのように大きな学びの木になる…そんな未来を思うと、今この瞬間が愛おしくなります。
Source: Tech fears vs smart practice: 7 myths parents must ditch to embrace healthier learning routines for kids, Times of India, 2025/09/15 10:49:38Latest Posts
