
先週の夜、子どもたちが寝静まった後、コーヒーを飲みながら妻と話していたときのことを思い出す。ニュースで流れる世界の変化を見て、妻がそっと呟いた言葉が胸に残っている。『この子たちには、もっと色んな角度から世界を見てほしい』。確かに難しそうに思えるけれど、よく見ると私たちの毎日にこそ、その種がたくさん散らばっていることに気づいたんだ。
台所で広がる世界地図
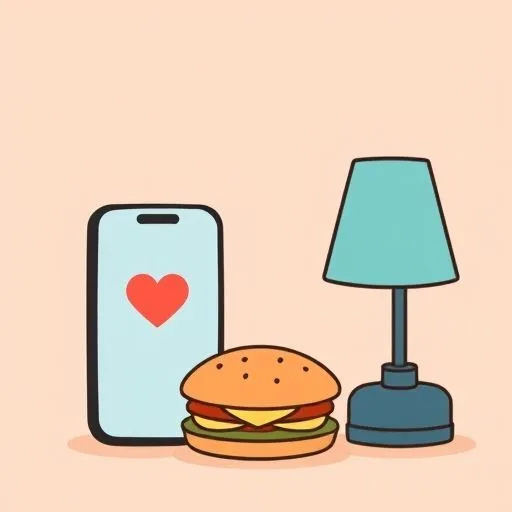
夕食の時に子どもが『なんで国によって食べるものが違うの?』と聞いてきた日のこと。スマホで地図を開き、その国の話を始めた。あの瞬間、国際理解の第一歩は机の上ではなく食卓で始まるんだと感じた。
週末の家庭料理は最高のグローバル授業になる。スーパーで食材選びをするとき、『このスパイスはどんな国から来たかな?』と自然に問いかける姿。レシピを読みながら失敗しても笑い合える空気が、子どもたちの好奇心をそっと支えている。
特に好きなのは、料理にまつわる小さな物語を添える瞬間だ。『このトマトの原産地は南米なんだよ』という言葉が、食卓を世界につなぐ架け橋になる。そういう些細な会話こそが、視野を広げる栄養になると信じている。
画面越しの異文化交流

先日、妻が子どもとタブレットを使って海外の友達と話している姿を見て気づいた。テクノロジーを怖がるのではなく、『世界は繋がっている』と教える道具として使いこなす姿に感心した。
新しい言語アプリに挑戦する奮闘が胸を打つ。『この発音難しいね』と笑いながら何度も繰り返す姿は、子どもたちに挑戦する勇気を教えている。子どもたちから改めて教わったんだ。
オンライン交流の後、必ず家族でその国の話をする習慣が素敵だ。画面越しの体験を現実の学びに変えるそのバランス感覚は、デジタル時代に必要な知恵だと感じる。
不確かな時代を生き抜く力

夜、子どもの寝顔を見ながら『この子たちの未来はどうなるんだろう』とつぶやく声に、時代の変化を感じることがある。それでも恐れずに明日の一歩を踏み出す姿が、家族の支えになっている。
世界が複雑になればなるほど大切なのは柔軟な考え方だろう。子どもたちと話す時、『こうしなければ』ではなく『こんな道もあるね』と言える余白の作り方は見習いたい。
毎日の小さな積み重ねが子ども達の未来を形作っていること。世界とつながる子育ては特別なことじゃない。
食卓の会話、日常の選択、そして子どもたちの疑問に丁寧に向き合うこと。その一つ一つが彼らの心の中に世界への扉を開いているんだ。
