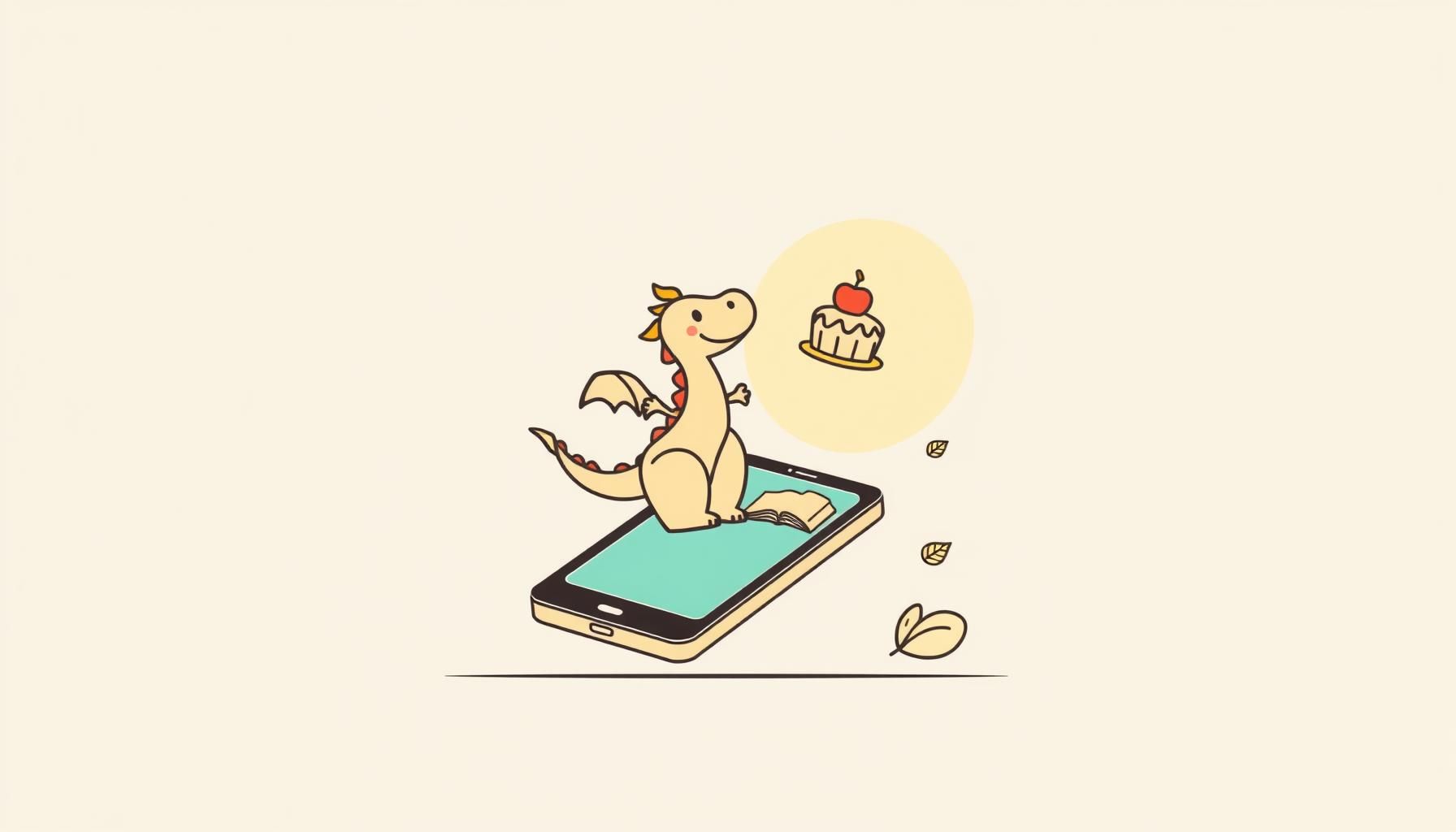
昨夜、7歳の娘がぼくのスマホを覗き込んで「ねえ、ドラゴンとケーキ屋さんが友達になる話が聞きたい!」って急に言い出したんだ。そこで思い出したのが、Google Geminiに追加された新機能「Storybooks」。5分後には、虹色のドラゴンがケーキを焼いて街中に幸せを配るオリジナル絵本ができて、娘はもう大興奮!画面に広がる色鮮やかなイラストを見ながら、「次は私もセリフ入れて!」って自分でナレーションを足してくれて…。そんな魔法みたいな夜を、ぼくは「これは他のパパママにも伝えたい!」って思ったんだ。さあ、今日はスマホひとつで、子どもの想像力を爆発させるコツを、今日はリアルに解説!
Gemini StoryBookとは?スマホ1台でできるAI教育体験
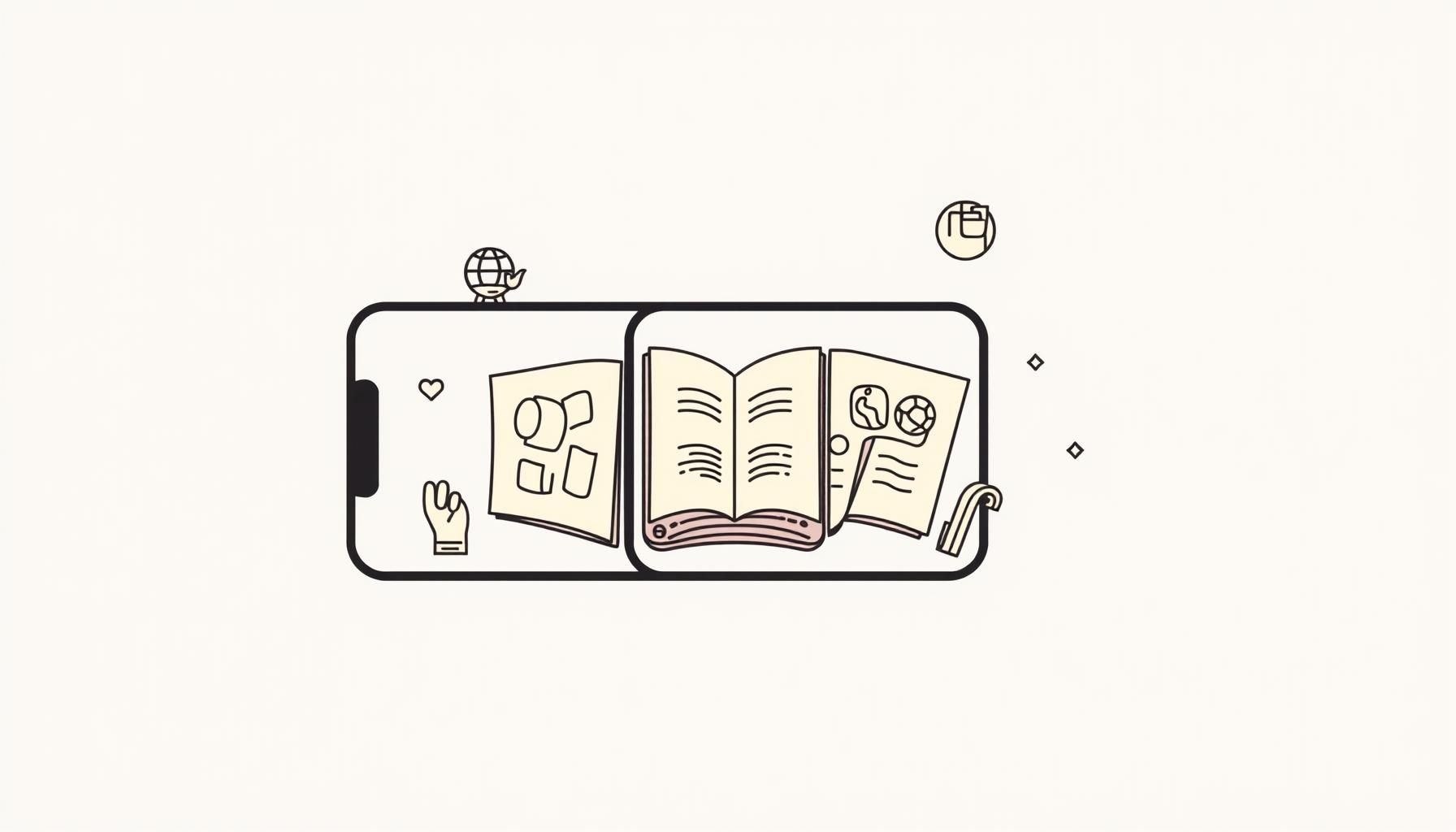
シンプルに言うと、Geminiに「ある日、ねこだった宇宙飛行士が…」みたいに一文送るだけ。するとAIが自動でストーリーを膨らませて、イラスト付きのページ立て続けに作ってくれるんだ。
驚いたのは「キャラクターの見た目を固定」できる機能。最初に描いた虹色ドラゴンは、次ページでも同じ姿で登場。だから子どもは「あの子また出てきた!」って安心しながら物語を追える。
そして日本語で「読み聞かせモード」をオンにすると、ゆっくりしたナレーション音声が流れてくれる。寝かしつけタイムにぴったり!声のスピードも「ちょいゆっくり」「ふつう」「ちょい速め」と3段階あるから、小1の娘でも余裕でついていけるよ。
家族で実践!失敗しないAIストーリー創作3ステップ
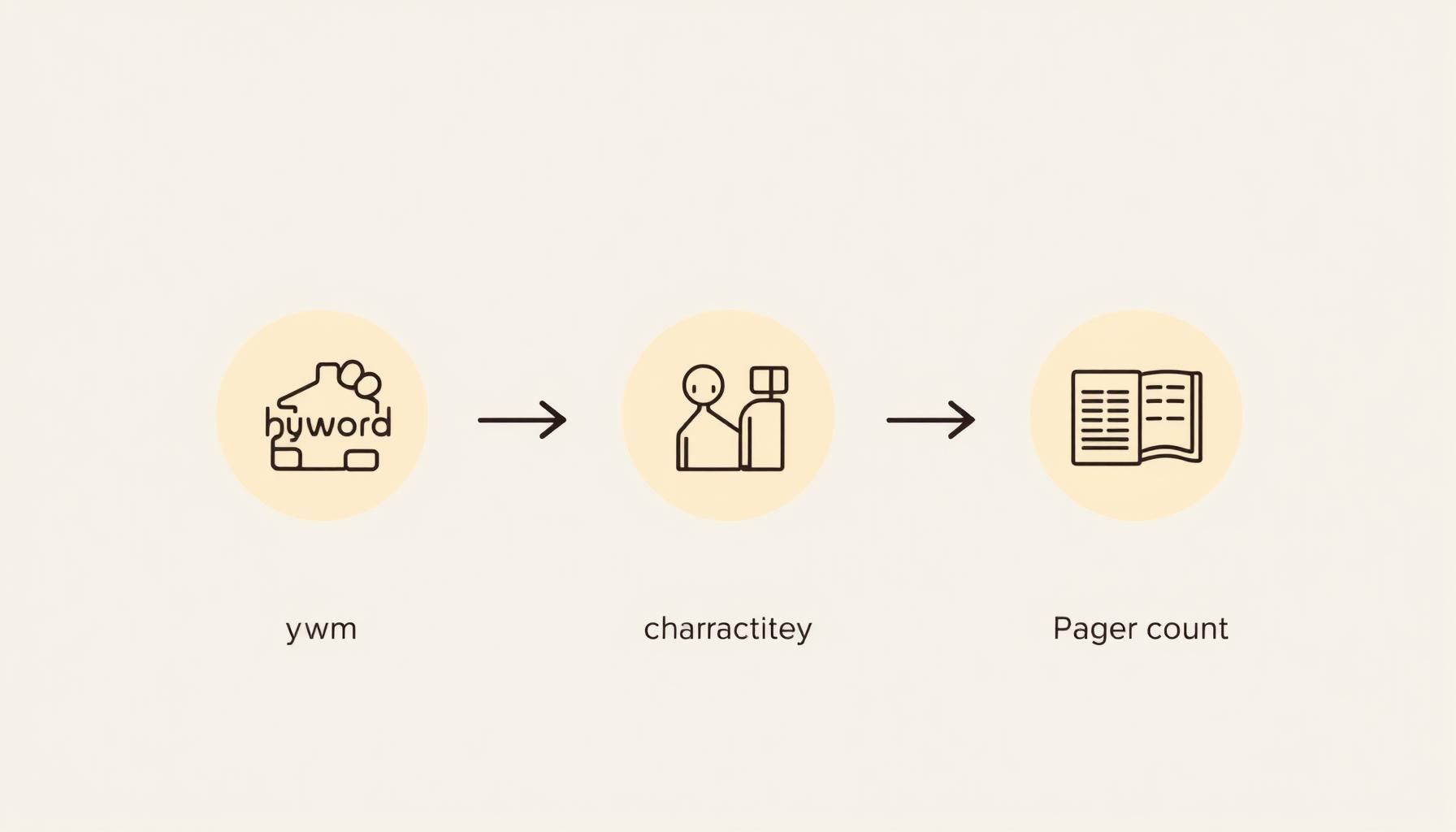
ステップ1 キーワードは短めに
最初は「北極で寿司を作るペンギンの話を作って」って長文で送ったら絵柄がバラバラになってしまったんだ。経験から「北極のペンギンシェフ」だけで十分キレイにまとまるのがわかった!
ステップ2 キャラ固めは1枚目で決める
「この子はずっと赤いリボンがポイント」って最初に指定しておくと、物語が進んでも髪型や色が変わらない。子どもが「あれ?前とは違う!」と混乱しないコツだよ。
ステップ3 ページ数は5〜7枚がベスト
長すぎると寝る前に間に合わないし、短すぎると盛り上がらない。「5ページお願い」ってリクエストすると、分量調節もうまくいくよ!
どう活かす?親子の会話を物語に変換するワザ
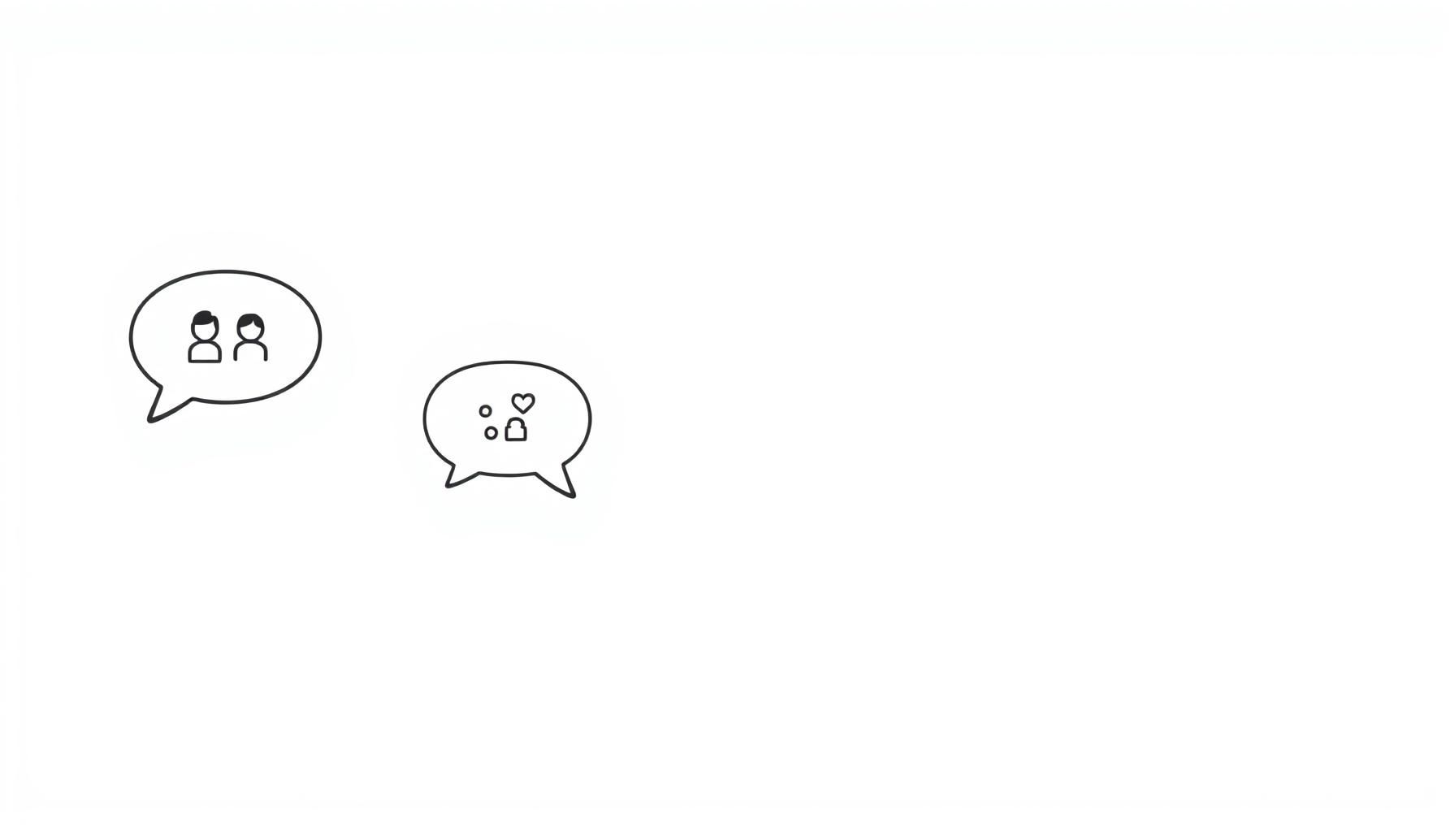
Geminiは画像だけじゃなく、吹き出しにも対応してるんだ。ぼくたちはこんな遊び方を発見した:
娘の好きなフレーズ「やったー!」をドラゴンセリフにするようリクエストしたら本人爆笑。そして「次は私も言葉考えたい!」って意気込むようになった。
コツはGeminiに「最後のページに子ども本人の名前を登場させて」とリクエストするだけ。すると「○○ちゃんも一緒にケーキを食べました」みたいなエンドロールが自動生成される。名前入り絵本は宝物級だよ!
作った絵本を日常でどう使う?AI絵本のちょい足しアイデア帳

朝の短時間活用
通学路で歩きながら「今日はどんな冒険する?」って話しかけるんだ。その答えをGeminiに入力して帰宅時には新作絵本完成!短い距離でも会話が弾む。
おやつタイム×物語展開
今日のおやつがクッキーなら「クッキーを探す妖精の話」にすれば食べながら読むだけで世界観ダブル楽しみ。
週末プロジェクト
家族4コマ漫画風にしてプリントアウト。冷蔵庫に貼るだけで、来週の朝ごはん会話が自然と盛り上がるんだ!
AI教育は創造力をどう育てる?親としての気づき
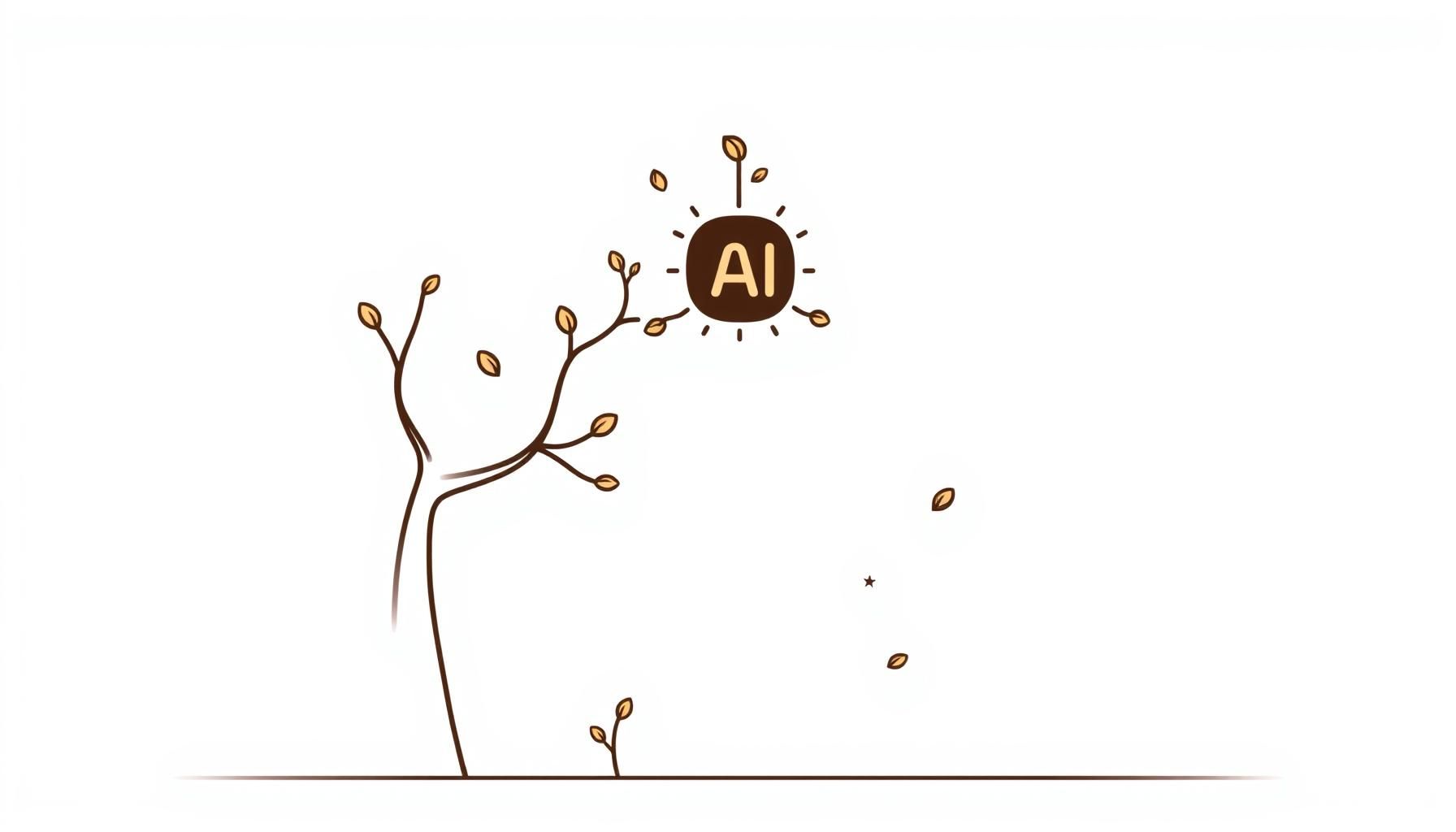
正直最初は「AIって難しそう…」って思ったけど、使ってみたらこれは単なる道具じゃなくて“共創パートナー”だった。
娘は今、「AIさんに頼らず自分でも描いてみる」って挑戦し始めた。AIのアイデアを真似して→自分色にアレンジ→またAIに戻す。この往復で創造力は加速度的に育ってる気がする。
大事なのは「AI教育」だからといって人間の感性を置き換えるんじゃなくて、あくまで“花火の火薬”みたいに使うこと。火薬だけじゃ音も光も出ないけど、人間のアイデアと混ざれば夜空を彩る大輪の花火になるんだよね。
だからこそ僕たち親は、子どもがAIや教育テクノロジーから受け取った刺激を「じゃあ実際に紙に描いてみよう」「公園でドラゴンの鳴き声真似して遊ぼう」とリアルにつなげてあげる役目だと思う。
Source: How to Create AI StoryBooks with illustrations in Gemini, Techviral, 2025-08-10
