
今日は子どもを寝かしつけた後、ベッドでiPadの設定を見ていると娘が『パパ、これで間違えなくてもいいの?』って質問してきた。その瞬間、AIより大切なのは、学ぶことへの好奇心だと思った。
冷めた紅茶をすすりながら、今日読んだ調査結果がよぎった。
「保護者の7割がAI技術の発展による子どもの将来に不安を感じている」。数字の向こうで、自分が子どものタブレットを設定していた姿を思い出した。
世の中は「AI教育のリスク対策」と騒ぐけど、本当の支えは子どもの横でそっと手を差し伸べる日常。
私が気づかれないまま織りなす「選び取る力」——それが、機械にはできない子どもの強さの土台なんだと、改めて感じた夜だった。
不安の数字が伝えるママの本当の役割

『中学生のAI利用率が親の9.0%を上回っている』と知った時、胸がざわつきましたね。
便利さばかりが語られるけど、私がそんな統計の裏側で確かな仕事をしているんです。
子どもの宿題にAIを導入する時、単に答えを出すのではなく『どうしてこの結果が出たと思う?』と問いかける。
文部科学省が指摘する『AI教育の7つの深刻な問題点』——そのひとつ『思考力の低下』を私が気づかれないところで防いでいる。
AIが『国語が苦手』と言われるのも、ロジカルな指示じゃなく子どもの言葉に耳を澄ませるから。
『AIを使うと子どもが考えなくなる?』なんて心配より、私が実践する『あなたならどうする?』という問いかけが、子どもの主体性を形作る。
この繰り返しが、大人になっても通用する『生きる力』の種になるんだと気づかされました。
画面越しに育む“人間らしさ”の基盤
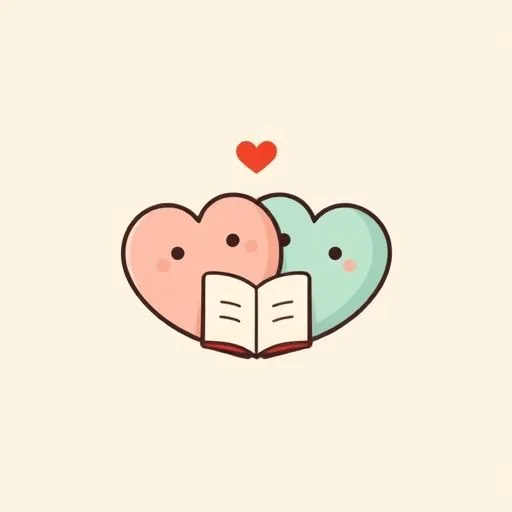
子どもがAI翻訳を使おうとしたので、一度止めて「自分で訳してみよう」と提案しました。彼の興味がAIの理解を深める一歩だと感じたんです。
『自分で訳してみて、AIと比べてみよう』と。すると翌週、子どもが『辞書引くほうがおもしろい!』って言うようになった。
技術指南書にない知恵——それが私の強みです。
専門家の調査でも『幼少期から学童期の環境が、大人の生きる力を決める』と。
お弁当のメニュー考える時も『バランスは自分で決めてみて』と伝える。
この日常の積み重ねが、『AIに負けない子ども』を作る。
技術は変わるものだけど、子どもが『問いを立てる力』を失わないよう、私がいつも静かに導いている。
画面の向こうのAIがどれだけ進化しても、子どもの心が揺るがないのは、この温もりがあるからなんだと。
今夜もママの手のひらが未来を照らす

『AI時代を生き抜く子育て』って難しいことじゃないんです。
子どものスクリーンタイムを決める時も、私がルールを作るより『一緒に考えてみよう』と提案する。
その背中を見て、子どもが学ぶのは他者への配慮。
配達のおじさんへの「お疲れ様です」という声を聞いて、AIにない温かさを感じました。僕がおじさんに挨拶するのを見て、子どもが自然と真似するようになった。見守るだけで、小さく育む絆の強さですね。
明日、子どもが『将来ロボットが全部やる時代になったら?』と尋ねたら——私がきっと『あなたの興味こそが道しるべ』と答える。
見えない作業と思われるこの積み重ねが、実は子どもの核になる。
だから今夜も、私が子どもの頭を撫でながらAIのニュースに目を通す。
そのそっと触れる指先に、未来への希望が宿っている。
…それが、私たち家族を守る最も強いセキュリティなんだと、最近ようやく気がついたのだった。
AIも進化するけど、家族で作る小さな日常のビッグな力。それがすべての未来を照らすんだ。
