
今朝も息子を小学校まで送ってきました。空は薄曇りで、ひんやりとした9月の風が頬を撫でます。
ほんの2分、手を繋いで歩くだけなのに、この日常が世界の大きな転換点と繋がっているなんて、最近読んだ衝撃の記事で目が覚めたんです!
気候変動がもう逆行できない段階に達し、AIが生活の隅々まで浸透する今、私たちは気づけば「自分で考える力」を失いつつあるというのです。
でも心配しないで!この危機こそが、家族で「主体性」を育むチャンスだと気づいたんです。
朝の通学路で息子が突然「お父さん、空の色が変だね」と指差した瞬間——その小さな一歩から始まる、希望に満ちた物語を、パパ目線で熱くお伝えします!
主体性の退化とは?お弁当箱でわかる親子の日常

ニュースで耳にする「気候・AIの二重ターニングポイント」——なんだか難しそうですが、朝のお弁当づくりで実感しました。
息子が今月から給食に加わった「環境クイズ」で、「台風の進路予測はAIが担当してるの?」と質問してきたんです。
そこで気付いたのですが、私たち親子も「主体性の退化」の罠にはまっていました。
先週、天気予報アプリに頼りすぎてランドセルを濡らした日。
本来なら、空の色や風の匂いで“雨の予感”を掴めたはずです。
もっとも研究で指摘される「認知的オフローディング」——AIに思考を預けすぎて、五感のアンテナを鈍らせていたのです。
親なら誰でも、特に「出勤ラッシュで判断疲れ」の日々。
でも諦めないで!台所が最高の実験室なんです。
昨日の夕飯時、息子と「お味噌汁の温度で天気予報」チャレンジを始めました。
熱すぎたら「晴れ」、ぬるかったら「曇り」と、科学的な裏付けはありませんが(笑)、「自分の感覚で推測する習慣」を育む小さな実践。
この「主体性の保存」こそが、二つの危機に立ち向かう原動力になると確信しています!
主体性を育む子育てのヒントとして、日常で実践できる方法を探ってみませんか。
考える力を育む3つの魔法:散歩道から生まれた実践例
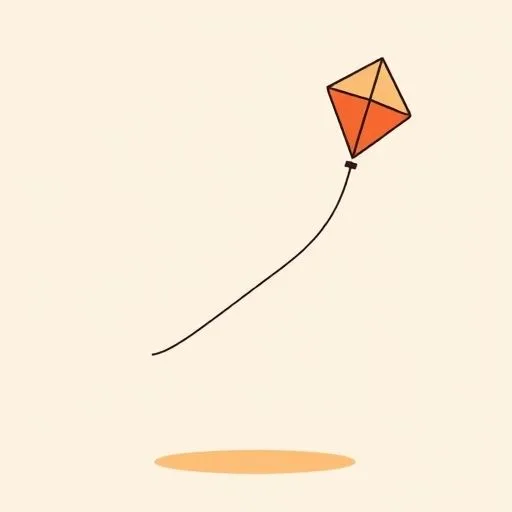
通学路の散歩で学んだ、AIと気候変動の波に踊らされない生き方。
息子と「森の教室」を始めたら、想像以上にハマりました!
① 「AIは相棒、支配者じゃない」作戦
公園の木の実を集めるルールを「Googleレンズで調べてから手で触る」に変更。
画像認識で名前を特定した後、「でも本当は触るとどう感じる?」と質問。
研究で示される「スキル衰え防止」の極意は「ツールと自分のバランス」にあります。
まるで「道案内はカーナビ任せ、でも景色は自分で見る」の旅のように!
② 里山で体感する「気候危機」
週末は近所の里山で「昔と今の大根畑」観察会。
祖母が「秋の収穫日が3週間早くなった」と教えてくれ、「おばあちゃんの記憶が気候データ」だと実感。
「システムの相互作用」を学ぶには、
家族の会話が最強のツール
③ デジタル断食の“和”流テクニック
「月に2回、スマホをおまにしまう日」を設定。
代わりに「絵手紙天気図」を作成——窓から見た雲をスケッチし、「明日の気温を五分で予報」と遊ぶ。
「モッタイナイ」精神がAI社会のサバイバル術に進化しています!
主体性を育む子育て、本当に家族の絆を深める素晴らしい実践ですよね!このドキドキするような家族の冒険に、これからも一緒にワクワクしていきましょう!
Source: Double Tipping Points: Agency Decay in the Climate-AI Nexus, Psychology Today, 2025/09/14
