
子どもが眠りについたあと、リビングの片隅で、コーヒーカップを手にすることがあります。ふと、その子の小さな手がスマートフォンの画面を滑る様子を思い浮かべるんです。公園で見つけた虫の動画を嬉しそうに話してくれたあの日。あのときの質問が、私たちが渡すべき最後のコンパスのようでした。「デジタルの中の、本当のことを見つける方法」を、一緒に探す旅が始まっています。
デジタル公園の砂場に潜む、嘘の貝殻
寝る前に、ベッドの中でスマホを覗き込む子どもの横顔を眺めます。星のない夜空の光のように、画面に反射するその瞳の奥には、どんな情報が映っているのでしょうか。
私たちは、幼い頃に「知らない人に付いて行っちゃダメ」と教えたように、今度は「デジタル世界の知らない人」をどう伝えるか。考えさせられるのです。ママがよく言う、子どもの「ちょっと変な言い訳」の表情を聞き分けるような、あの繊細さを。今度は、検索結果と向き合うときに、同じように尋ねてみようよ。
親子の実験室は、食卓から始まる

夕食の後で、子どもが突然「この動画、本当?」と聞いてくる日がありました。ママは、隣でお皿を片付けながら、静かに提案します。「一緒に確かめてみようか?」。
こんな風に、私たちは3年間、5分間の「デジタル探偵ごっこ」を続けてきました。たとえば、ネットで見つけた珍しい動物の話を、実際の図書館の本で調べる。その小さな発見は、子どもにとって、本物の動物を確かめる手探りの冒険だったんだ。
この子の疑問は、一緒に育てるための種なのです。
「信頼のアンテナ」は、親子の手紙で作られる

夜の寝る前の時間、子どもが「今日の動画の投稿者は誰?」って聞くことがあります。そんなとき、ママは「そっと、ネット上の投稿者の気持ちを想像してみよう」と提案します。
私たちは、一緒に「デジタル郵便受け」の話をすることがあります。情報の送信者の顔を、家族で想像してみる時間。それは、まるで運動会の後、親しか知らないエピソードを語り合うような感覚。
子どもの「なぜ?」という小さな火花が、自然に広がっていく。そんな瞬間を見つめています。
明日の朝ごはんには、疑問の種を添えて
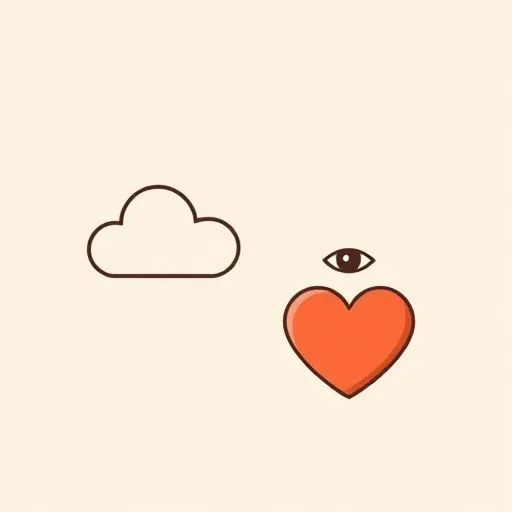
最近、ソファでくつろぐ子どもが、自分で「この情報、おかしい?」と考えるようになりました。その隣で、ママが小さく微笑みます。「自分で疑問を持つようになってきたね」って。
私たちは、デジタルの信頼性を伝えるのは、答えを教えることではなく、その問いの味を一緒に感じることだと思うのです。
あの夕食のテーブルで、子どもが「この動画の作り手は?」と聞いてきた60秒の静けさ。その沈黙こそが、私たち家族の、新しい信頼の始まりだったのです。
Source: NHK「デジタルリテラシーの基本」2025/09/20
