
先週、子どもが学校から持ち帰った世界地図のプリントを見ながら、ふと考えました。国境を超えたニュースが飛び交う現代で、私たち親子はどんな『地図』を手にしているのだろう?海外では親がどんな関わり方をしているのか、スマートに見える子育ての秘密は何か――そんな疑問がふと浮かぶこと、ありませんか?
家庭で育む国際感覚は、特別なことではなく、毎日の小さな選択の積み重ねなのかもしれません。
子どもの好奇心が作る国境なき教室
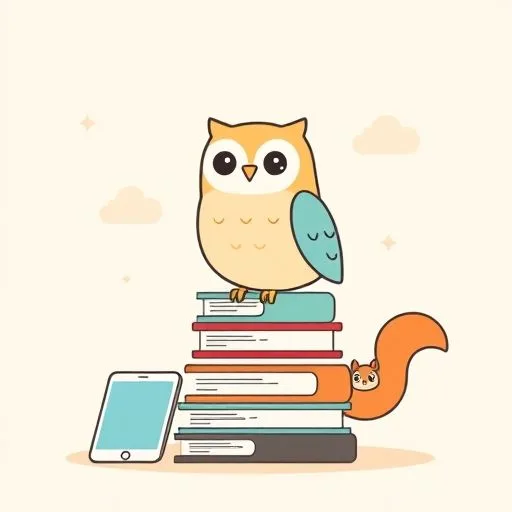
夕食時に流れるニュースで子どもが質問してきたことはありませんか?
なぜあの国では戦争が起きているの? そんな時こそ、会話のチャンス。
海外の家庭でよく見られるのは、「一緒に調べてみよう」と導く姿勢。
子どもの疑問をそのまま尊重することで、自ら学ぶ力が育ちます。
家庭での国際感覚は、地図を広げるのではなく、子どもの視野を広げることから始まるのかもしれません。
習い事の選択が語る文化の違い

そこである日気づいたんです。公園で自由に遊ぶ子どもたちを見ながら、日本の習い事事情を眺めていると、興味深いことに気づきます。
水泳にピアノ、学習塾…どれも大切ですけど、つい子どもの「未来」ばかり考えちゃいませんか?
一方で海外では、「今の楽しさ」を重視する傾向が。
公園でサッカーに夢中になる子どもを見ながら、この違いに気づいた方もいるでしょう。
重要なのはどちらが正しいかではなく、子どもの個性に合った選択を尊重できるかどうか。
その選択こそが、子どもをひとりの人間として認める第一歩だと思うのです。
海外と日本をつなぐ日本語教育

「日本語を忘れてきている」と悩む海外在住の家庭があります。例えばカナダの日本語補習校で出会った方々は、苦労しながらも、日々の絵本読み聞かせでルーツをつなぐことを実感しています。
でも考えてみてください。言葉は道具でありながら、アイデンティティそのものでもある矛盾。
大切なのは「追いつく」ことより「やめない」こと。
たとえゆっくりでも、自らのルーツと向き合い続ける姿は、子どもに確かな自信を与えます。
毎晩の絵本読み聞かせが、海を越えた伝統の架け橋になる——そんなシンプルな真実に気づかされます。
世界情勢を親子で読むコツ
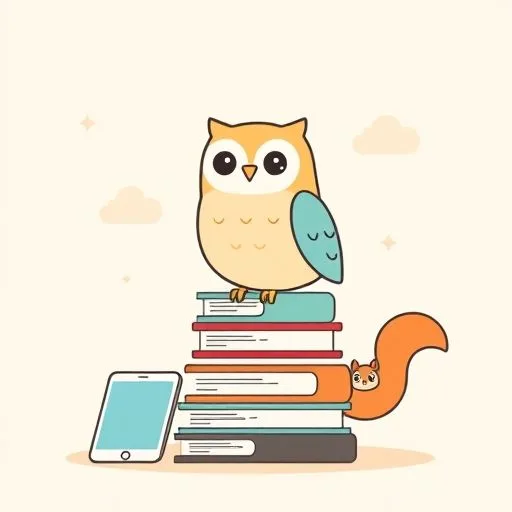
難しい国際問題も、子どもの視線で見ると違う側面が見えてきます。
朝食のパンを例に取ってみましょう。
「この小麦はどこから来たと思う?」 そんな問いかけが、世界とのつながりを気付かせます。
ニュースの背後にある人間ドラマに触れながら、「もし自分だったら」と想像する時間を作る。
それだけで、毎日が国際感覚を養う教室に変わります。
親と子が共に学ぶ「世界情勢タイム」の始めかた、考えてみませんか?[1]
【出典】High Growth Tech Stocks To Watch In Asia September 2025, Yahoo Finance, 2025/09/14
